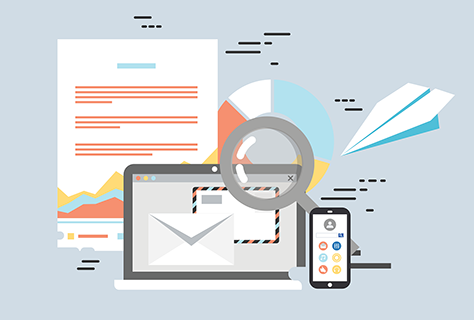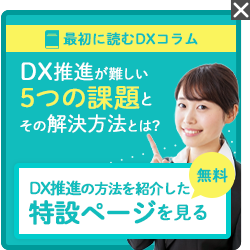更新日:
働き方改革における業務効率化とは?結果がすぐ出るアイデア6選!

「働き方改革における『業務効率化』って、どんな方法があるの?」
「働き方改革の一環で『業務効率化』を図りたい。参考になるアイデアはないかな?」
あなたは「働き方改革」のために「業務効率化」に取り組む予定なのではないでしょうか。
しかし「どんな方法があるのか」がわからず、困っているのかもしれませんね。
結論からいえば、以下のようなアイデアがあります。
- 業務の「割り当て」を変更する
- 業務を「マニュアル化」する
- 業務の「テンプレート」を作成する
- 「テレワーク」を推進する
- 「業務効率化ツール」を導入する
- 業務効率化につながる「知識」をシェアしあう
これらのアイデアのなかから、貴社に合ったものを選ぶことで「業務効率化」できます。
しかし「業務効率化」を推進する際には「正しい進め方」も知っておかないと、業務効率化が失敗してしまう可能性がありますから、注意が必要です。
そこで本記事では、アイデアに加えて「失敗しない『業務効率化』の進め方6ステップ」も解説します。
ステップ1:現状の「業務内容&業務フロー」を可視化する
ステップ2:「業務」のムダを洗い出す
ステップ3:ムダを減らすための「解決アイデア」を出す
ステップ4:「解決アイデア」の妥当性について従業員に意見を聞く
ステップ5:実行に向けた「計画スケジュール」を立てる
ステップ6:「効果測定」を行う
この記事を読めば、自社に合った「業務効率化のアイデア」を選び出せることに加え、滞りなく業務効率化を完遂できるでしょう。
「自社に合った『業務効率化』のアイデアが知りたい」
「滞りなく『業務効率化』を成功させたい」
といった方にとって、参考になる記事です。
また、業務効率化については下記記事でも解説しておりますので、より深掘りたい方はぜひ合わせてご覧ください。
それではみていきましょう。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.「働き方改革」における「業務効率化」とは?
まずは「働き方改革における業務効率化」がどのようなものかについて、しっかり押さえておきましょう。
「働き方改革における業務効率化」とは、誰もが働きやすい社会を作るために、働き方改革の柱の一つである「長時間労働の見直し」によって業務効率化を進めることです。
つまり「残業OK」「転勤OK」の正社員だけでなく、
- 小さな子供を育てるワーキングマザー
- 親の介護を抱える男性社員
- パートナーと離別し、3人の子どもを育てるシングルファーザー
など「働き方改革」の目的である「定型通りの働き方ができない人たちが働きやすい社会を作ること」をめざして「業務効率化」を進めることをいいます。
事情を抱える人も「貴重な労働者の一人」として活躍することで、「少子高齢化」による深刻な労働力不足に備えます。これが、働き方改革における業務効率化の最大のポイントです。
なお「働き方改革」は、次の3本柱で構成されています。
- 長時間労働の是正
- 非正規雇用の格差改善
- 多様な働き方の実現
そのうち「長時間労働の是正」が「業務効率化」にあたります。
本記事では「業務効率化」にフォーカスを当てて「アイデア」や「失敗しない進め方」などを詳しく解説します。
出典:「働き方改革のポイントをチェック!」
2.働き方改革推進による「業務効率化」で得られるメリット3つ
先述の通り「働き方改革」の目的は「どんな事情を抱えた人も働ける世の中を作ること」です。
誰もが働きやすい会社にするために業務効率化に取り組み、長時間労働を是正することで、以下の3つのメリットが得られます。
- 残業時間が減るため、従業員の「エンゲージメント」が高まる
- 「コアビジネス」に集中できるため「売上アップ」につながる
- ムダな業務が減るため、人件費等の「コスト削減」できる
一つずつみていきましょう。
2-1.残業時間が減るため、従業員の「エンゲージメント」が高まる
もっとも大きなメリットが「従業員のエンゲージメント向上」です。
業務効率化に成功すると、残業時間が減ります。
残業時間が減ることで、従業員は、仕事とプライベートのバランスを取ることができます(=「ワークライフバランス」の向上)。
メリハリをもって仕事に取り組めるようになるため「前向き」な気持ちで、仕事に向き合えるようになります。
それが、企業への「エンゲージメント向上」へとつながります。
実際、HR総研が2021年2月に行った「働き方改革に関するアンケート」では、働き方改革によって「エンゲージメントの向上」につながった企業が「12%」であったことがわかっています。
エンゲージメントが向上することで
- 離職率の低下
- 働きがいの創出
- 自走社員の増加
- 心地よい企業風土の醸成
など、さまざまな嬉しい効果が得られます。
これが、業務効率化で得られる1つ目のメリットです。
出典:日本最大級の人事ポータル「HRpro」:「HR総研:働き方改革に関するアンケート 結果報告『エンゲージメント向上』を目的とする企業の8割でテレワーク導入成功」
2-2.「コアビジネス」に集中できるため「売上アップ」につながる
業務効率化を推進する過程で、業務の「ムダ・ムリ・ムラ」が減ります。
その結果、売上に直結する「コアビジネス」に、労働リソースを投下できるため「売上アップ」につながりやすくなります。
例えば、業務効率化の一環で、人事部に「給与計算システム」を導入した場合。
以下のような効果が得られます。
| 削減できる「ムダ」 | 「給与計算」にかかる時間を大幅に削減できる |
|---|---|
| 削減できる「ムリ」 | 「月内に1000人分の給与計算を2人で手計算して行う」といったハードワークをなくせる |
| 削減できる「ムラ」 | 「給与計算」の入力ミスを防げる |
上記の結果、人事部の担当者は、「採用面談」や「従業員へのフォローアップ」などの業務に、時間を割けるでしょう。
「人材採用」や「就業環境の改善」などにしっかりと取り組めるため、従業員の「就労幸福度」が向上します。それが、売上アップなどの嬉しい効果につながるはずです。
以上の通り「コア業務に注力できる」というのも、業務効率化で得られる大きなメリットの一つです。
2-3.ムダな業務が減るため、人件費等の「コスト削減」できる
業務効率化を推進すると、人件費等の「コスト削減」できます。
これも、嬉しい効果の一つです。
例えば、業務効率化の一環で「帳票発行システム」を導入した場合。
サービスや顧客種別などに応じて、見積書や発注書などを自動出力できるようになるほか、印刷代や郵送費なども削減できるため、帳票作成にかかわる時間を大幅にカットできます。
「楽々明細」を提供する「株式会社ラクス」による興味深い調査結果があります。
仮に「500件/月」の帳票が発生している場合。
システム利用料と差し引いても、印刷代、紙代、封筒代、郵送費、人件費などを削減できるため「70万円/年」もの削減効果が得られるそうです。
月に500件もの帳票が発生しなくても、塵も積もれば山となります。
結果としては「大きなコスト削減効果」が得られるでしょう。
以上の通り、「コスト削減」も、業務効率化で得られる嬉しい効果の一つです。
なお、業務効率化につながるシステムは、帳票発行システムに限らず多数あります。
システムを利用することで、あらゆる経費を削減できます。
気になる方は、簡単に「業務効率化」を実現できるデジタルツールの解説記事「デジタルツールとは?初心者におすすめツール8選を解説 」をチェックしてください。
出典:楽々明細:「請求書電子化ソフトの実力!コスト削減効果編」
3.すぐに結果が出る!業務効率化の取り組み方&アイデア6つ
働き方改革の「業務効率化」は、さまざまなメリットが享受できる素晴らしい取り組みであることがわかりました。
続きまして、業務効率化につながるアイデアをご紹介したいと思います。
大前提として、業務効率化は「2つの軸」があります。
- ムダな業務を減らす・なくす
- 業務効率化につながる「知識」をシェアしあう
一つずつみていきましょう。
3-1.ムダな業務を減らす・なくす
業務効率化を成功させるには「ムダな業務を減らす・なくす」に尽きます。
基本となる取り組み方は、以下の5つのいずれかに集約されます。
押さえておきましょう。
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 業務の「割り当て」を変更する | 業務を「統合」して、作業時間を減らす |
| 業務を「分業」して、作業時間を減らす | |
| 業務をアウトソーシングして、作業時間を減らす | |
| 業務を「マニュアル化」する | 業務の進め方を解説した「マニュアル」を作成して、作業時間を減らす |
| 業務の「テンプレート」を 作成する | 定型化できる業務を「テンプレート化」して、作業時間を減らす |
| 「テレワーク」を推進する | テレワークを推進して、通勤時間を削減する |
| 「業務効率化ツール」を導入する | 「業務の自動化・簡略化」ができる業務効率化ツールを導入して、作業時間を減らす |
それぞれどういうことなのか、解説します。
3-1-1.業務の「割り当て」を変更する
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 業務の「割り当て」を変更する | 業務を「統合」して、作業時間を減らす |
| 業務を「分業」して、作業時間を減らす | |
| 業務をアウトソーシングして、作業時間を減らす |
ムダな業務を減らすためには「業務の割り当て」を最適化するのがおすすめです。
「業務の割り当て変更」には3つのパターンがあります。
3-1-1-1.業務を「統合」して、作業時間を減らす
「業務の統合」は、複数の従業員が担当していた業務を、一人の従業員が担うなどです。
例えば、ニュースメディアを運用していて、インタビュー記事を作成する場合。
「取材」を担当する人と「原稿」を執筆している人が分かれているならば、「取材」と「原稿作成」を一人の人が担当するといった具合です。
取材時の内容が頭に入っている人が原稿も書き上げた方が、スピーディに記事を仕上げられます。
このように「分業すると、却って作業工数が増える業務」は、統合しましょう。
3-1-1-2.業務を「分業」して、作業時間を減らす
「統合」とは逆に「分業」するのも、業務効率化を推進する一つの方法です。
例えば企業用のシステムを販売する会社があった場合。
顧客にシステムを提案する営業担当者が「アフターフォロー」も兼務しているようなケースがあります。
しかし、営業とアフターフォローを兼務すると、営業に割ける時間が減ります。
その結果、売上がダウンしてしまうといった事態が生じかねません。
そのため「営業部」と「サポート部」を切り分けて、分業するといったことが考えられます。
分業することで、その分野のノウハウが貯まりやすくなり、業務効率化が推進されます。
営業の業務効率化については下記でも解説しておりますのでより詳細に調べたい方はぜひご覧ください。
営業の業務効率化を進めるメリットは?業務効率化に役立つ4つの方法や進め方をご紹介!
営業の効率化にはワークフローが必要!具体的な4つのステップを解説
3-1-1-3.業務をアウトソーシングして、作業時間を減らす
会社の従業員数が限られていたり、社内にノウハウがない場合、業務をアウトソーシング(外注)することも一つの方法です。
例えば、ウェブサイトの立ち上げを予定しているが、経験者が社内にいない場合、ウェブサイト作成の経験が豊富な人材を「業務委託」のかたちで、雇用するのがよいです。
経験ゼロの人材が、イチから学びながらウェブサイトを運用していくよりも、経験がある人が担当した方が、スムーズに運用できるからです。
3-1-2.業務を「マニュアル化」する
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 業務を「マニュアル化」する | 業務の進め方を解説した「マニュアル」を作成して、作業時間を減らす |
業務の進め方を「マニュアル化」すると、業務効率化につながりやすいです。
例えば、カスタマーサポート部で、PC機器の「トラブルシューティング」を行う場合。
顧客からの問い合わせに応じて、質問内容などが「フローチャート」などにまとめられていると、スムーズな顧客対応が可能になります。
一方、「クレームが来た時の対応マニュアル」などもあれば、上長によるサポートがなくとも、オペレーターだけで解決できる場面が増えるでしょう。
「よくあるパターン作業」や「定型作業」については、マニュアル化するのがおすすめです。
3-1-3.業務の「テンプレート」を作成する
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 業務の「テンプレート」を 作成する | 定型化できる業務を「テンプレート化」して、作業時間を減らす |
マニュアル化とともに行いたいのが「業務のテンプレート化」です。
テンプレート化すると、ムダな業務が減らせて、業務効率化につながります。
例えば、PC機器を製造している会社があった場合。
「使い方」に関する問い合わせが、メールで送られてくることが予想されます。
そういった場合「使い方」に関する回答をあらかじめ作成しておき、必要なときにはコピーアンドペーストすれば良い状態にしておけば、メールを打つ手間を減らせます。
このように、機械的に対応できる作業は、テンプレート化して作業工数を減らしていくことが大切です。
3-1-4.「テレワーク」を推進する
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 「テレワーク」を推進する | テレワークを推進して、通勤時間を削減する |
業務効率化には「テレワークの推進」もおすすめしたい手法の一つです。
なぜならば、従業員は、会社に赴くまでの通勤時間を減らせて、すぐに業務に取り掛かれるからです。
電車通勤などのストレスがなくなることで、生産性が高まり、より業務効率化が促進されることも予想されます。
3-1-5.「業務効率化ツール」を導入する
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 「業務効率化ツール」を導入する | 「業務の自動化・簡略化」ができる業務効率化ツールを導入して、作業時間を減らす |
「業務効率化ツールの導入」は、業務効率化を実現するために行うべきことです。
業務効率化を推進する際には、自社のニーズに合ったツールを一つは導入してみることをおすすめします。
例えば「給与計算システム」があれば、給与計算にかかわる作業をほぼ自動化できます。
また、「営業管理システム(SFA)」があれば「過去の商談履歴」や「受注確度」「失注理由」などを一元で管理できるため「どのようなアプローチを行うべきか」に関して検討する時間を削減できます。
以上の通り、ツールを導入すれば、人間が行っていた業務を「自動化&簡略化」できます。
抜本的に業務効率化を推進したいときには、ツールの導入を検討してみましょう。
業務効率化にも役立つツールの導入に関しては下記で解説しています。ぜひご興味のある方はご覧ください。
業務効率化ツールとは?種類一覧、ニーズ別おすすめ10選など解説
3-2.業務効率化につながる「知識」をシェアしあう
業務効率化のもう一つの軸が「業務効率化につながる知識の共有」です。
一人ひとりの従業員がもっている「独自の業務効率化ノウハウ」をシェアすることで、業務効率化が加速します。
例えば、カスタマーサポートセンターで、各オペレーターが、以下のような「業務効率化の知識」をもっているとします。
Aさん:クレーム対応を「平均30分以内」に完了させる極意
Bさん:トラブルシューティングの対応スピードが「1.5倍」になる秘訣
その際、各人が自分の知識をシェアすれば、一人ひとりのオペレーターが保有する業務効率化のアイデア数は増加し、業務効率化をより一層推進できます。
4.簡単に導入できる!業務効率化を叶えるおすすめツール7個
3章「すぐに結果が出る!業務効率化の取り組み方&アイデア6つ」でご説明した通り、業務効率化においては、ツールの導入がおすすめです。
ツールを導入すれば、人間が行っていた業務を「自動化&簡略化」できるからです。
人件費や業務時間の大幅な削減につながります。
なかでも、おすすめの「ITツール」は、以下の7つです。
より簡単に導入できる可能性が高い順に並べています。
是非ご確認ください。
| ビジネスチャット | ・概要 LINEのような使い勝手で、やり取りできるコミュニケーションツール |
|---|---|
| ・メリット 「お世話になっております」などの挨拶が不要で、メールよりも気軽に送れる。社内外の人と、スムーズなやり取りが可能になるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 メールのやり取りが多いが、時間がかかっている リモートワークを導入予定である |
|
| ・おすすめしない企業 業務連絡のやり取りがあまりない(現場仕事が多いなど) |
|
| オンライン会議システム | ・概要 時間や場所を問わず、ミーティングや会議ができるシステム |
| ・メリット 会議の相手の居場所に関わらず、「移動時間ゼロ」で打ち合わせできるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 営業・商談・打ち合わせが多い 移動時間を減らしたい |
|
| ・おすすめしない企業 営業・商談・打ち合わせがほとんど発生しない |
|
| 電子契約サービス | ・概要 一連の契約締結を、Web上で完結できるサービス |
| ・メリット 書類の送付、契約書の読み合わせなどが発生しないため、スピーディな契約締結が可能になるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 契約業務が多い |
|
| ・おすすめしない企業 契約業務が少ない |
|
| 電子稟議システム | ・概要 稟議の申請・回議・承認を、Web上で完結できるシステム |
| ・メリット 稟議の承認に関わる人がどこにいても、承認作業ができるため、稟議可決までのスピードが上がるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 稟議が多い |
|
| ・おすすめしない企業 稟議が少ない |
|
| 勤怠管理システム | ・概要 「出勤・退勤・休憩・稼働時間」などをシステム上で記録・管理できるシステム |
| ・メリット 勤務状況の管理を自動化できるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 正社員、パート、アルバイト問わず、従業員数が多い |
|
| ・おすすめしない企業 従業員数が少ない |
|
| 経費精算システム | ・概要 経費(交通費・交際費・出張費など)の申請・承認を効率化するシステム |
| ・メリット 「精算額の計算ミス」などの人的ミスを防げるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 経費精算の頻度が多い |
|
| ・おすすめしない企業 経費精算の頻度が少ない |
|
| 帳票発行システム | ・概要 見積書、発注書、請求書などの帳票類を自動出力・自動送信できるシステム |
| ・メリット 帳票の記載ミスが防げるほか、作成時間も減らせるため、業務効率化につながる |
|
| ・おすすめする企業 帳票作成の頻度が多い |
|
| ・おすすめしない企業 帳票作成の頻度が少ない |
5.失敗しない「業務効率化」の進め方「6ステップ」
本章では「業務効率化」の進め方6ステップを解説します。
ステップに沿って業務効率化を進めないと、業務効率化に失敗するリスクもありますから、注意が必要です。
以下より業務効率化の進め方におけるステップをご紹介します。
| ステップ1 | 現状の「業務内容&業務フロー」を可視化する |
|---|---|
| ステップ2 | 「業務」のムダを洗い出す |
| ステップ3 | ムダを減らすための「解決アイデア」を出す |
| ステップ4 | 「解決アイデア」の妥当性について従業員に意見を聞く |
| ステップ5 | 実行に向けた「計画スケジュール」を立てる |
| ステップ6 | 「効果測定」を行う |
一つずつ、みていきましょう。
5-1.【ステップ1】現状の「業務内容&業務フロー」を可視化する
まずは、自社の「業務内容」や「業務フロー」を可視化しましょう。
「どのような作業が発生しているのか」を、一覧表や箇条書きなど明らかにすることで「どこにムダがあるのか」がわかりやすくなるからです。
例えば、飲食店のキッチンの場合。
以下のようにリストアップすることが考えられます。
「業務内容&業務フロー」の可視化(飲食店の場合)
- 朝礼(本日の売上目標の共有)
- 朝イチに行う「フロア・厨房内清掃」
- 野菜・肉・調味料等の受取
- ランチに向けた仕込み
- ランチの調理
- 新規メニューの開発
- ディナーの仕込み
- ディナーの調理
- 営業終了後に行う「フロア・厨房内清掃」
- ゴミ出し
5-2.【ステップ2】「業務」のムダを洗い出す
書き出した業務内容から「この作業は時間がかかりすぎている」「ムダだ」と思えるものを、洗い出しましょう。それらを、何らかの手法で「効率化」します。
その際、現場の担当者から意見を吸い上げるのがベストなため、討議の時間を設けるのがおすすめです。
従業員が答えづらい場合には「匿名のアンケート要旨」を配布して、意見を募るのもよいでしょう。
5-3.【ステップ3】ムダを減らすための「解決アイデア」を出す
業務のムダを洗い出せたら、ムダを解消するための「解決アイデア」を出しましょう。
例えば、飲食店で「ニンジンの千切りの仕込み」に時間がかかっており、業務時間を圧迫しているという意見があった場合。
ものの数秒でニンジンを千切りできる「自動千切り機」を導入するのが、一つの「解決アイデア」です。
この場合「ムダな業務を減らす・なくす取り組み方5つ」のうちの「ツールを導入する」に該当します。
| 取り組み方 | 概要 |
|---|---|
| 業務の「割り当て」を変更する | 業務を「統合」して、作業時間を減らす |
| 業務を「分業」して、作業時間を減らす | |
| 業務をアウトソーシングして、作業時間を減らす | |
| 業務を「マニュアル化」する | 業務の進め方を解説した「マニュアル」を作成して、作業時間を減らす |
| 業務の「テンプレート」を 作成する | 定型化できる業務を「テンプレート化」して、作業時間を減らす |
| 「テレワーク」を推進する | テレワークを推進して、通勤時間を削減する |
| 「業務効率化ツール」を導入する | 「業務の自動化・簡略化」ができる業務効率化ツールを導入して、作業時間を減らす |
「解決アイデア」を抽出する際には、「上記の5つのうち、どれに当てはまりそうか」について、目星をつけると、スムーズに解決アイデアを抽出できると思います。
5-4.【ステップ4】「解決アイデア」の妥当性について従業員に意見を聞く
「ムダな業務」に対する「解決アイデア」を挙げられるだけ挙げたら、アイデアの「妥当性」をダブルチェックしましょう。
そうすれば「解決アイデア」に有効性があるか否かを、しっかりと見極められるからです。
先ほどの例では、野菜の「自動千切り機」を導入するアイデアがありましたが、ニンジンを千切りする機会が、1年のうちでも、数回だったらどうでしょうか?
機器を導入すれば、ニンジンの千切り時間を削減できますが「費用対効果が合わない」といったことになりかねません。
このように「解決アイデアの妥当性」をよくよく検討したうえで、実行に移すことが大切です。
5-5.【ステップ5】実行に向けた「計画スケジュール」を立てる
「解決アイデア」の妥当性についてチェックできたら、実行に向けた「計画スケジュール」を立てましょう。
スケジュールを立てることで、うやむやにならず、確実に業務効率化を実現できます。
スケジュールを立てたら、従業員に周知し「今後、運用が変わる」ことを、アナウンスしておきましょう。そうすれば、心づもりができます。
例えば「〇月〇日にニンジンの千切り機を導入します。前日に使い方レクチャーを行うため、使い方を学んでいただけたらと思います」といった掲示を行うなどです。
5-6.【ステップ6】「効果測定」を行う
業務効率化のための「解決アイデア」を実行したら「効果測定」も行いましょう。
効果測定をすれば、今後また、業務効率化をする際のヒントが得られるからです。
例えば、ニンジンの千切り機を導入する場合。
導入前と導入後で「どれくらい仕込み時間が削減できたのか」を記録するといった具合です。
30分かかっていた仕込み時間が、5分以内に完了できたならば、導入効果が非常に高いでしょう。
このように、時間を計測するのが、一つの手です。
以上の「6ステップ」が、業務効率化を失敗なく推進するための進め方です。
業務プロセスの可視化は難しいと思いますが、下記で詳細を解説しておりますのでぜひ実際に取り組む方はご覧ください。
業務プロセスを可視化する4つのステップ|可視化へ取り組むメリットを解説
6.よくある業務効率化の「落とし穴」&「回避策/解決策」4つ
業務効率化を推進するうえで「よくある失敗を回避するための注意点」をお伝えします。
回避策や解決策も記載していますので、業務効率化に失敗するリスクを抑えることが出来るかもしれません。
是非ご確認ください。
| よくある失敗 | 「よくある失敗」の回避策/解決策 |
|---|---|
| 「業務効率化」のはずが却って「負担増」 につながってしまう | ・回避策/解決策 「負担増」につながっている原因を究明する |
| ・具体例 導入した「解決アイデア」や「業務効率化ツール」の問題点をヒアリングしたうえで、話し合いやアンケートなどの手段で「解決策」を再構築する |
|
| ミスが増える | ・回避策/解決策 「スピードを重視しすぎていないか」をチェックする |
| ・具体例 ミスが増えている場合「業務効率化=スピードアップ」という短絡的な結論に至っていることが少なくない。品質を維持しながら業務効率化を実現できる「ほどよいバランス」を見極める |
|
| 「業務効率化」につながっていない | ・回避策/解決策 推進されている「業務効率化」の問題点を報告できる環境を構築する |
| ・具体例 意見箱/意見フォームを設置する 定期的に面談の機会を設ける |
|
| 「業務効率化」のための業務効率化ツールが浸透しない | ・回避策/解決策 「ツールを導入する目的」を伝える 「ツールの使い方」を理解してもらうためのフォローを行う 導入するツールを再検討する |
| ・具体例 「ツールの利用マニュアル」を共有する 「ツールの使い方説明会」を開催する 導入するツールを解約して、別のツールを導入する |
ここまで記事を御覧いただいた上で、
「業務効率化が可能な箇所について相談したい」
「どのようなツールが自社にあっているかがわからない」
「同業界の業務効率化例を聞いてみたい」
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
7.まとめ
いかがでしたか。
「働き方改革における業務効率化」について、ご紹介しました。
ここで本記事の内容を整理します。
「働き方改革」における「業務効率化」とは?
誰もが働きやすい社会を作るために、働き方改革の柱の一つである「長時間労働の見直し」を行うこと
「業務効率化」で享受できる可能性のあるメリット3つ
- 残業時間が減るため、従業員の「エンゲージメント」が高まる
- 「コアビジネス」に集中できるため「売上アップ」につながる
- ムダな業務が減るため、人件費等の「コスト削減」できる
すぐに結果が出る!業務効率化の取り組み方&アイデア6つ
- 業務の「割り当て」を変更する
- 業務を「マニュアル化」する
- 業務の「テンプレート」を作成する
- 「テレワーク」を推進する
- 「業務効率化ツール」を導入する
- 業務効率化につながる「知識」をシェアしあう
簡単に導入できる!業務効率化を叶えるおすすめツール7個
- ビジネスチャット
- オンライン会議システム
- 電子契約サービス
- 電子稟議システム
- 勤怠管理システム
- 経費精算システム
- 帳票発行システム
失敗しない「業務効率化」の進め方「6ステップ」
ステップ1:現状の「業務内容&業務フロー」を可視化する
ステップ2:「業務」のムダを洗い出す
ステップ3:ムダを減らすための「解決アイデア」を出す
ステップ4:「解決アイデア」の妥当性について従業員に意見を聞く
ステップ5:実行に向けた「計画スケジュール」を立てる
ステップ6:「効果測定」を行う
本記事が「働き方改革の業務効率化」を成功させたい方のお力になれましたら幸いです。
また、プラリタウンでは他の記事でも業務効率化について解説しています。それぞれ各テーマについて詳細に解説しておりますので、ぜひご興味のある方はご覧いただけますと幸いです。