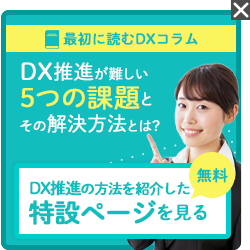更新日:
デジタルツールとは?初心者におすすめツール8選を解説
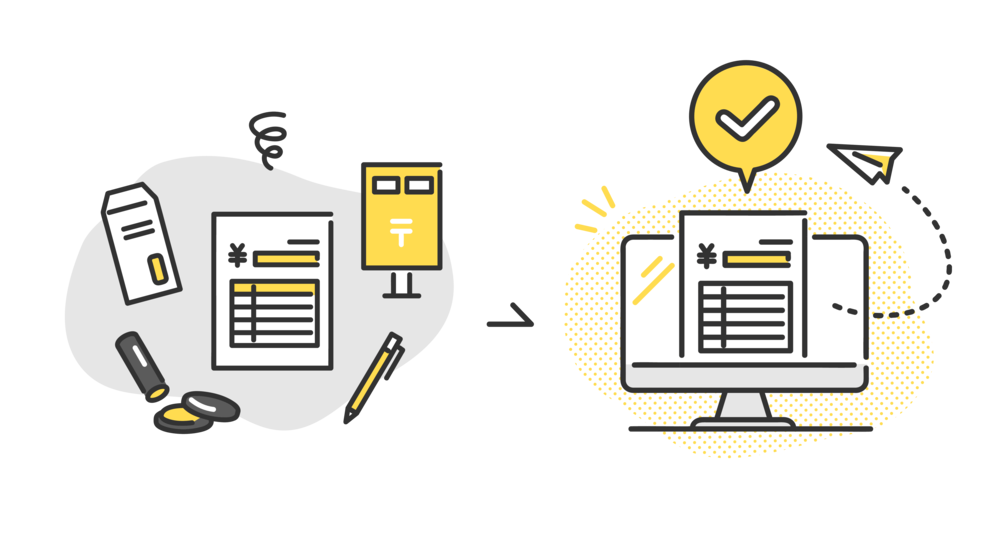
デジタルツールとは、紙文書や表計算ソフトなどで人手と時間をかけて行っていた業務をシステム上で行うことにより、
- 業務効率化
- 売上拡大
- コスト削減
などを実現可能なソフトウェアツールです。
デジタルツールの活用によりアナログな業務のデジタル化を図ることができます。
「自分の会社ではアナログで非効率と感じる業務が多い」などと感じている場合は、デジタルツールの導入による業務効率化等を検討してみてはいかがでしょうか?
その際、従業員が使いやすい簡単なツールなど、なるべくスムーズに導入できるデジタルツールから導入するのがおすすめです。
デジタルツールの中には、導入するための「要件定義※」に時間がかかるものや、利用ハードルが高い、高機能なツールもあるためです。
※必要な機能などを分かりやすくまとめていく作業
具体的には、以下に挙げる8つを、初めてデジタル化に取り組まれる企業の方へもおすすめのデジタルツールとしてご紹介しています。
これらのデジタルツールであれば、比較的簡単・スピーディに導入できて、デジタルツール初心者の方も業務効率化やコスト削減などの効果をすぐに得られる可能性が高いです。
本記事では、デジタルツールの利用経験が少ない初心者の方に向けて、
- 各ツールの特徴やメリット
- 導入をおすすめする企業
- 導入にあたっての留意点
などを分かりやすく解説していきます。
貴社の課題やニーズに合ったデジタルツールを選定するにあたって、ぜひ参考にしてください。
あわせて、本記事では「デジタルツールの選定・導入で失敗しないために押さえたい5つのチェック項目」も解説していきます。
デジタルツールの導入前に5つのチェック項目を確認しておくことにより、デジタルツールの選定・導入で失敗するリスクを低減することができるでしょう。
- ひとつひとつサービスの理解に時間をかけられない
- デジタルツールは種類や数が多すぎて選べない
- まずは詳しい人に話を聞いてから考えたい
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
また、下記記事でも、DX推進に役立つ16種類のツールをご紹介しています。ご興味がある方はぜひ合わせてご覧ください。
DX推進に役立つ16種類のツールを紹介!ツール選定時のポイントも
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.デジタルツールとは?なぜ導入すべき?
本章では、まず「デジタルツールとは何なのか?」という具体的なイメージを持つことができていない方へ向けて、分かり易く解説します。
デジタルツールとは
冒頭でご説明した通り、デジタルツールとは、紙文書や表計算ソフトなどで人手と時間をかけて行っていた業務をシステム上で行うことにより、
- 業務効率化
- 売上拡大
- コスト削減
などを実現するソフトウェアツールのことです。
なぜデジタルツールを導入すべきか
例えば、社内稟議の対応へ「ワークシローシステム」を導入した事例をみながら、デジタルツールがどのようなものなのかをイメージしてみましょう。
一般に、社内稟議の起案や決裁を行いたい場合、
担当者からの起案→決裁者へ回付→決裁者が内容確認→決裁者の承認(決裁)
という流れをたどります。
従来は紙面へ印刷された稟議書が、回覧板のように「担当者→課長→部長」という順番で渡っていく光景もよく見られていたかと思います。
デジタルツールの一つである「ワークフローシステム」では、紙面へ印刷した稟議書は用いません。
稟議書の作成から起案、承認までの一連の流れを、システム上で行います。
稟議内容はパソコンなどから確認できるため、担当者や決裁者がいつでも、どこにいても、稟議の起案作業や承認作業ができるようになります。
そのため、社内稟議の決裁にかかる時間や手間を削減し、業務効率化を実現することができます。
改めてDXの必要性について理解したい方は下記記事がおすすめです。
『DXはなぜ必要』の理由3点!読めば自社のDX推進メリットが理解できる
デジタルツールは、企業やビジネスモデルの変革や競争力の維持・向上において必要不可欠
このように、アナログで行われてきた業務のデジタル化を図ることが可能なデジタルツールですが、
「デジタルツールが魅力的なものだということはわかった。しかし、今のままでも特段課題を感じていないが、デジタルツールを導入する必要があるのだろうか?」
このような素朴な疑問を抱く方も、いらっしゃるかもしれません。
しかしながら、デジタルツールの導入・活用は、企業がビジネスモデルの変革や競争力の維持・向上を図りながら、中長期的に事業活動を継続していくために、非常に重要です。
デジタルツールを導入しない場合、導入している企業と比べて、企業業績や競争力などの面から、差をつけられてしまう可能性が高いです。
だからこそ、デジタルツールの導入検討は、会社規模問わず全ての企業にとって喫緊、かつ大切な問題なのです。
しかし、デジタルツールの導入を始めとしたDXは決して簡単ではありません。
- DXの難しDXが進みにくくなる3つの要因
- DXを成功させるポイント
などについては下記で解説しています。お時間ある方はぜひ合わせてご覧ください。
日本企業の9割はDXに至ってない?|失敗事例から学ぶ「1割の成功企業」になる方法
- 日本企業が抱えるDXの5つの課題
- DXを推進するためのロードマップ
などについては下記をどうぞ。
DX推進の課題とは?課題の対処法と具体的なDXの進め方を徹底解説
2.初心者の方へおすすめする「デジタルツール8選」
本記事では、その中でも比較的スピーディかつ簡単に導入でき、デジタルツールに慣れていない従業員でも使いこなしやすいであろうデジタルツールを8つご紹介します。
また、それぞれのデジタルツールについて
- 主な機能
- 主な導入メリット
- 導入をおすすめする企業
- 導入にあたっての注意点
を解説していきます。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
①ビジネスチャット
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
ビジネスチャットツールとは
ビジネスチャットは、社内外の関係者との業務連絡(電話、会議、訪問など)を効率化するコミュニケーションツールです。
普段、個人で利用しているコミュニケーションアプリのような使い心地でチャット形式でやり取りが可能です。
そのためITに不慣れな人でも利用しやすく、多くの企業が導入しやすいデジタルツールの一つです。
例えば、電話メモ一つとっても、机上にポストイット形式で連絡内容を残す形ではなく、チャットで当事者へすぐに連絡を入れる、といったことも可能です。
また、個人間によるやりとりに加えて、プロジェクトや部署ごとのチャットを作成することもできます。
- 伝えたい内容や共有したいファイルを関係者へ一斉送信する
- 特定の関係者のみへ閲覧を呼びかけることもできる
ことから、場所や時間を選ばずスムーズなコミュニケーションを実現できます。
ビジネスチャットツール導入の注意点
一方で注意点としては、誰もが気軽に使えるツールであるがゆえに、どのようなやり取りもビジネスチャットに残せてしまう点が挙げられます。
ビジネスチャットは、あくまで「文章」によるコミュニケーションツールです。
複雑な内容を伝えるときには、打ち合わせの機会を設けたり、電話で伝えたりする方が、意思疎通をうまく行える場合もあります。
重要な内容や複雑な話に限っては電話や対面で行うなど、伝えたい内容に応じてコミュニケーションツールを使い分けるよう、従業員へ事前に周知することも必要になるでしょう。
ビジネスチャットの主な機能やサービスの特徴について興味がある方はこちら
②経費精算システム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
経費精算システムとは
経費精算システムとは、
- 各種経費の立て替えに伴う精算
- 出張に際しての事前の経費申請
などを、デジタル上で完結できるようにしたシステムです。
アナログな作業フローでは
- レシートや領収書の原本をノートへ貼り付けて管理する場合
- 表計算ソフトなどで経費の合計金額を計算する場合
などで処理されていることが多いです。
しかしそれでは、
- 原本の誤廃棄や計算ミス
- 精算漏れなどの人的ミス
が発生する恐れがあります。
それらのリスクを経費精算システムを用いれば軽減できます。
例えば、立て替えた経費を精算する場合、「レシートや領収書をスマホのアプリで撮影する」だけで、「立て替えが発生次第すぐに経費精算の申請をする」ということも可能です。
また、従業員が社内にいなくとも経費申請から承認までを行うことが可能なため、リモートワークを推進したい企業にもおすすめです。
経費精算システム導入の注意点
経費精算システムが多機能すぎて使いにくいなど、利用ハードルが高いケースがあります。
そのため十分に社内へ浸透せず、「システムの導入効果が得られなかった」という事態を招くことも想定されます。
従業員のデジタルリテラシーに不安がある場合には、
- システムの操作方法を教える講習会の用意
- 誰でも直観的に使えるシステムを選定・導入
などの対策が必要です。
クラウド型の経費精算・管理システムについてご興味がある方はこちら
③帳票発行システム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
帳票発行システムとは
帳票発行システムとは、商品・サービス・顧客種別などに応じて、最適な帳票※を自動出力するシステムのことです。
※見積書・請求書・申込書・発注書など
- 企業で取り扱っている商品やサービスの種類が豊富である
- 帳票作成機会が多い
といった企業へおすすめのデジタルツールです。
また、取引先への帳票送信を行えるものや、特記事項や注意事項の「記載漏れ」などを防げるものもあります。
商品・サービス・顧客種別などに応じて、あらかじめ設定しておいた帳票データを自動出力できるため、帳票作成の時間を削減できます。
さらに、ペーパーレス化を推進できる点でもおすすめです。
帳票発行システム導入の注意点
なお、請求書などについて、取引先から紙面による郵送を引き続き希望するような声が上がることもあると思います。
そのような場合は、帳票類を一度に「帳票発行システム」へ一元化するのではなく、取引先の希望する発行方法に応じて、柔軟に対応することが大切です。
帳票発行システムにご興味がある方はこちら
ここまでご覧いただいたうえで、
- 既存の業務が忙しいのでデジタルツールをしっかり調べる時間がとれない
- デジタルツールは種類や数が多すぎて選べない
- まずは詳しい人に話を聞いてから考えたい
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
④勤怠管理システム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
勤怠管理システムとは
勤怠管理システムとは、社員・パート・アルバイト等の出退勤の時間把握や、労働時間の管理をサポートするシステムのことです。
社員のパソコンやスマホのアプリから、ワンクリックで出退勤時間を打刻できるようなシステムもあります。
分刻みで、かつ労働実態に基づいて正確に入退勤時間を管理できるようになるため、多くの従業員を抱える企業などでは、大幅な業務効率化を実現できます。
また、勤怠管理システムの中には、一人ひとりの勤怠時間を「給与計算システム」と連携させることができるものもあり、システム同士の連携によって給与支払い業務も効率化することが可能です。
勤怠管理システム導入の注意点
なお、
- 裁量労働制やテレワークを導入している会社
- 労働時間ではなく労働者の成果に応じて報酬を決定する会社
などの場合、自社の従業員の勤務体系により適した勤怠管理システムを検討・導入することが重要です。
導入しようとしているツールで利用が可能なのか、事前にチェックしましょう。
バックオフィス全般の効率化を図れる勤怠管理システムはこちら
⑤ワークフローシステム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
ワークフローシステムとは
ワークフローシステムとは、稟議の起案・回付・承認(決裁)といった一連のフローを、パソコンやスマホなどから確認・実行できるようにするシステムのことです。
- 担当者の起案作業
- 承認者の承認・差し戻し作業
- 承認状況の把握
などが、場所や時間を選ばず行えるようになるため、稟議が承認されるまでのスピードが向上します。
特に、稟議回付数が多い企業や、リモートワークを推進したい企業におすすめのサービスです。
既存の承認フローに応じた回付設定を行えるシステムを選ぶと、社内へスムーズに導入できるでしょう。
ワークフローシステム導入の注意点
- 一定の金額水準で承認フローが変わる場合
- 部署を跨いだ承認が必要な場合
など、細かい承認フローの分岐がある企業では、回付設定を柔軟に行えるシステムを選ぶ方が望ましいと考えられます。
社内稟議の申請・承認はPCやスマートフォンで。ワークフロー機能も備えたグループウェアはこちら
⑥電子契約システム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
電子契約システムとは
電子契約システムとは、契約書への押印・署名、締結などの作業を、インターネット上で行えるようにするサービスです。
従来の契約締結業務の中では、
- 取引先から送付された契約書に印鑑で押印
- 再度取引先へ返送する
- 契約書の控えは紙面からPDF化して自社で保存する
といったような作業を行う必要がありました。
電子契約サービスでは、そのような作業が不要となるため、迅速な契約締結が可能となります。
また、
- 契約書をテンプレートから作成する機能
- 契約書のカテゴリーごとにフォルダ管理を行える機能
など、業務効率化につながる機能が充実しているサービスもあります。
電子契約サービスで締結した契約書の場合、収入印紙が不要になる点でも、メリットが大きいといえます。
電子契約システム導入の注意点
円滑に電子契約サービスを導入するためには、システム上で契約締結を行うことについて、
- 契約締結先の理解が得られているか
- 既存の社内規定が電子契約に対応しているか
などを、事前に確認しておくことが重要です。
「紙と印鑑」で行っていた契約業務を「オンライン」で完結。電子契約サービスはこちら
⑦OCRツール
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
OCRツールとは
OCR(Optical Character Reader)ツールは、紙面に印刷された文字を、パソコンなどで読み取れるテキストデータへ変換できるツールです。
- 紙面に印刷された文字を文書ファイルや表計算ソフトなどに転記する作業が多い
- 紙面に記録されている大量の情報を『電子データとして保存しておきたい』
といった場合には、OCRツールを活用することで転記作業やPDF化の作業時間が削減でき、大幅な業務効率化が実現します。
転記ミスなども防ぐことが可能なため、ペーパーレス化を推進したい企業には、導入メリットが大きいデジタルツールでしょう。
OCRツール導入の注意点
OCRツールの中には、手書きで書いた文字もテキストデータ化できるものがあります。
しかし、文字の認識精度はOCRツールによって異なります。
導入前に、
- 認識精度は満足できるか、許容範囲か
- 費用感は問題ないか(文字認識精度が高まるほど費用が高額になる場合もあるため)
などについて、確認しておくと安心でしょう。
OCR機能も兼ね備えた電子帳票プラットフォームはこちら
⑧オンライン会議システム
| 概要 |
|
|---|---|
| 主な導入メリット |
|
| 導入をおすすめする企業 |
|
| 導入にあたっての注意点 |
|
オンライン会議システムとは
オンライン会議システムとは、インターネットに接続していれば、場所を選ばず打ち合わせや面談などが行えるようになるシステムです。
参加者が保有しているプレゼンテーション資料を画面上で共有できるほか、録画やチャットなどの機能があるシステムもあります。
取引先への移動時間を削減したい、といったニーズがある方にとっては、非常に利用価値のあるデジタルツールです。
とくに、移動や外出の多い営業社員の業務効率化には、大きな効果を発揮するでしょう。
例えば、取引先企業への往訪に合計二時間かかっていた場合、オンライン会議システムを導入すれば、社員はその二時間を別の業務に割くことが可能です。
その他、オンライン会議システムは、遠方にいる見込み顧客に対してアプローチしたい、といった場合などにも重宝します。
今までアプローチできていなかった見込み顧客へのアプローチを行うことも可能なため、うまく活用すれば、売上拡大につながるでしょう。
オンライン会議システム導入の注意点
多くのオンライン会議システムが、遠隔にいる相手とリアルタイムに会話するための機能が備わっていますが、システムによっては、機能の表示や配置などに使いにくさを感じるものがあるかもしれません。
必要に応じて、「デジタルに疎い社員でも、直観的に使いこなせるか」といった観点からも選定していただくことをおすすめします。
リテールに強い、電話を使ったオンライン営業システムはこちら
3.「デジタルツール」の選定・導入で失敗しないために押さえたい5つのチェック項目
デジタルツールの導入に関して、サービスの数や種類が多く、選ぶのが困難であると感じている方も多いかと思います。
そこで、本章では、デジタルツールの選定・導入で失敗しないための注意点を5つ、解説します。
「デジタルツール」の選定・導入で失敗しないために押さえたい5つのチェック項目
- 現場で働く従業員の困りごとを把握する
- 従業員のデジタルスキルに合ったツールを選ぶ
- 導入前に使い勝手や費用対効果、サポート体制などを確認する
- ツールの使い方を講義するユーザー講習会の開催や、ユーザーマニュアルを用意・配布する
- 自社が導入すべきデジタルツールが分からない場合は、専門家へ相談する
これらの5項目を押さえれば、デジタルツールの選定・導入で失敗するリスクを低減することができます。
それぞれについて詳しくご説明いたします。
①現場で働く従業員の困りごとを把握する
デジタルツールを導入する際には、現場で働いている従業員の声を聞くとよいでしょう。
デジタルツールの導入を検討している側が「実務上はこのようなことで困っていそうだ」と仮説を立てていても、従業員にとっては、大した困りごとではない場合があります。
- この作業に特に時間を取られているために、残業が減らない
- この業務をデジタル化できれば、コスト削減ができそうで嬉しい
といった、実体に基づいた具体的な悩みを、ヒアリングの実施やアンケートの取得などにより把握することが重要です。
②従業員のデジタルスキルに合ったツールを選ぶ
一定のデジタルスキルが従業員に無い場合、社内で使いこなせない場合があります。
高機能なツールを一気に導入してしまえば、
- 初期設定でつまずいてしまう
- デジタルに疎い従業員のモチベーションが下がってしまう
といった懸念もあるでしょう。
そのため、従業員の現状のデジタルスキルに合ったツールを選ぶようにしましょう。
「思い切ってデジタルツールを導入したが、ほとんど利用者がいない」という事態を避けるうえでも、この観点は非常に大切です。
③導入前に使い勝手や費用対効果、サポート体制を確認する
導入したいデジタルツールの目星がついたら、
- 本格導入前にデジタルツールの使い勝手や費用対効果
- ツールの提供事業者からのサポート体制
を確認しましょう。
「ホームページを見る限り、シンプルで使いやすそうだ」と感じても、実際に使い易いかどうかは、使ってみないと分からない場合もあります。
- デジタルスキルが高くない従業員にトライアルで実際に使ってもらう
- 一部の部署の利用から始める
など、まずは小さく導入してみることも大切です。
サポート体制の面では、
- デジタルツールの使い方について質問できるコールセンターの有無
- 気軽に質問できるチャットサポートの有無
などを確認しておくと、従業員が困ったときもすぐ問い合わせができ、社内へデジタルツールが浸透しやすくなるはずです。
また、デジタルツールの費用対効果についても、定量的に定点観測しましょう。
例えば、デジタルツールの一つである電子契約サービスは、業務効率化により人件費や郵送費の削減が可能なものですが、印紙税の納付が不要になる点でも魅力的なサービスです。
実際にどの程度の費用が削減できているのかを確認しておくと、他のデジタルツールを検討した際の社内説明時などでも役立つでしょう。
④ツールの使い方を講義するユーザー講習会の開催や、ユーザーマニュアルを用意する
いざデジタルツールを導入しても、「使い方が良く理解できないから使わない」と感じている従業員がいる可能性があります。
そのため、デジタルツールの導入対象となっている業務に関係する従業員を対象として、ツールの使い方を講義する「ユーザー講習会」を開催することはおすすめです。
使い方について、講習会の場で実際に質問ができるようにすれば、定着率が高まるでしょう。
また、使い方へ疑問が出てきた際に、従業員が自分で調べて解決可能なユーザーマニュアルを用意・配布することもおすすめです。
人に聞くまでもない不明点や疑問点を、各従業員の手元で解決できるようになるからです。
デジタルツールの提供者側で、ユーザーマニュアルを有している場合もあります。
ぜひ問い合わせてみましょう。
⑤自社が導入すべきデジタルツールが分からない場合は専門家へ相談する
「導入するデジタルツールの目星まではつけられたが、本当に必要かどうか自社で判断することが難しい」
そのような場合には、デジタルツールに精通している専門家へ相談してみましょう。
自社の困りごとや実現したい目標に応じたデジタルツールについて、アドバイスを貰うことが可能です。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
4.まとめ
ここまでお読みいただき、デジタルツールについて、少しでも理解は深まりましたでしょうか。
ここで本記事の内容を整理したいと思います。
デジタルツールとは?
アナログな業務のデジタル化を図ることにより、
- 業務効率化
- 売上拡大
- コスト削減
などを実現可能なツールのこと
デジタルツールの導入・活用は、企業がビジネスモデルの変革や競争力の維持・向上を図りながら、中長期的に事業活動を継続していくために、非常に重要となります。
とはいえ、どのデジタルツールから導入を検討すればいいか分からない、といった方も多いかと思います。
そこで本記事では、比較的スピーディかつ簡単に導入でき、デジタルツールに慣れていない従業員でも使いこなしやすいであろうデジタルツールを8つご紹介しました。
初心者の方へもおすすめする「デジタルツール8選」
ビジネスチャット
経費精算システム
帳票発行システム
勤怠管理システム
ワークフローシステム
電子契約サービス
OCRツール
オンライン会議システム
さらに、以下の5項目を押さえれば、デジタルツールの選定・導入で失敗するリスクを低減することができます。
「デジタルツール」の選定・導入で失敗しないために押さえたい5つのチェック項目
- 現場で働く従業員の困りごとを把握する
- 従業員のデジタルスキルに合ったツールを選ぶ
- 導入前に使い勝手や費用対効果、サポート体制などを確認する
- ツールの使い方を講義するユーザー講習会の開催や、ユーザーマニュアルを用意・配布する
- 自社が導入すべきデジタルツールが分からない場合は、専門家へ相談する
自社の課題やニーズに合ったデジタルツールを検討するにあたって、本記事の内容をぜひ参考にしてください。
また、もしSaaSの導入でご検討の方は下記記事もぜひご覧ください。
SaaS導入の効果的な7つの場面|87%の企業がSaaSの効果を実感