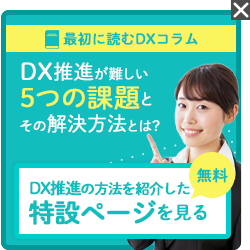更新日:
営業の業務効率化を進めるメリットは?効果の高い4つの方法や進め方をご紹介

「営業の業務効率化を図りたいが、何から始めるのが有効なのだろう?」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
自社に合う方法を選びながら、ポイントを抑え営業の業務効率化を実践することができれば、業務効率化によるメリットを享受できるだけでなく、業務効率化により浮いた時間を新規開拓や商談などへも充てられるため、営業にとって最も重要な「売上増加」も期待できるようになるでしょう。
しかし、やみくもに営業の業務効率化を進めようとしてしまうと、後で「余計な業務が増えただけだった」「自社には合わない方法だった」と困ってしまうことになるかもしれません。
そこで本記事では、営業の業務効率化を成功させたい方のために、以下の内容をお伝えします。
本記事で主にお伝えすること
- 営業の業務効率化へ取り組む際に優先すべき業務
- 営業の業務効率化を妨げている3つの問題
- 営業の業務効率化に役立つ方法4選
- 中長期的な売上拡大を目指す場合に検討したい業務効率化方法
最初に、営業の業務効率化へ取り組む際の優先順位や、営業の業務効率化が進みにくい理由などについて解説します。その後、具体的な業務効率化方法や、その進め方まで詳しくお伝えしていきますので、最後までお読みいただければ、自社の営業業務の効率化へ着手しやすくなるはずです。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.営業の業務効率化は、社内業務を中心に着手するのがオススメ
営業の業務効率化を図る際に、最初に意識すべきことは、「社内業務を中心に業務効率化へ取り組むことが重要である」ということです。
営業活動における社内業務とは、具体的にみると、主に以下のような事務作業や、社内での報告業務などのことを指します。
営業活動における社内業務例
- 提案資料作成
- 名刺管理
- 見積書の作成
- 見積書や提案資料の社内承認
- 日々の営業活動の社内報告
- 取引先や顧客との契約締結
営業の仕事というと、顧客との商談を含め、対外的なコミュニケーションがメインだと考えている方は多いと思います。しかしながら、商談やプレゼンテーションなどの業務は、対人業務であるため、効率化をしようにも難しい部分が多いという特徴があります。
こうした中、社内の事務作業であれば、各種業務フローや作業のオンライン化などによって、比較的すぐに業務を効率化することが可能です。1日の中で多くの時間を費やしており、かつ売上向上へはすぐに直結しない社内業務の効率化を図ることによって、浮いた時間を対顧業務へ費やすことができるようになるのです。
このように、営業の業務効率化に向けては、営業社員が社内で実施していて、かつ効率化を行いやすい事務的な作業を中心に進めることが重要になります。
2.社内業務の効率化を妨げている3つの問題
次に、営業の業務効率化を妨げている問題について詳しく確認していきましょう。営業の社内業務の中でも、特に問題となりやすいポイントを正しく認識しておくことにより、自社の状況に応じて「どのような改善(効率化)方法を選ぶべきか」が明確になるからです。
本章でお伝えする、営業の業務効率化を妨げている主な問題は、以下の3つです。
営業の業務効率化を妨げている主な3つの問題
- 営業活動前の準備や、営業活動後の情報管理に時間がかかる
- 社内文書の作成や承認に時間がかかる
- 社員によって営業スキルや推進方法が異なる
早速詳しく見ていきましょう。
2-1.営業活動の事前準備や、営業活動後の情報管理に時間がかかる
1つ目の問題は「営業活動の事前準備や、営業活動後の情報管理に時間がかかる」というものです。
例えば、「顧客との商談で契約を獲得する」という目標達成のためには、営業担当者は商談だけを行えばよいわけではなく、前後に以下のような業務が発生します。
営業活動の前後に発生する業務の例
- アプローチ候補となる顧客のリストアップ
- 顧客情報の収集
- 提案資料の作成
- 商談結果の社内報告
- 見積の提出
- 名刺管理
- 契約の締結
- 問い合わせ対応
このように、社内で対応しなければならない業務が多く、肝心の商談内容の検討や戦略を練るために時間を割くことができない、と困っている営業担当者は多いのではないでしょうか。
また、営業担当者が自分1人であれば、自身が分かるようにデータを保管できていれば良いかもしれませんが、多くの会社では複数の営業担当者がチームになっていることと思います。
すると、以下のような問題が発生することにより、業務に余計な時間がかかってしまうことがあります。
- 前任者の商談資料が見つからず、同じような資料を再度作ることになる
- 情報が一元化されていないため、同じ顧客へ別の営業担当者がアプローチしようとしてしまう
- 同じ業界の顧客向けの商談にも関わらず、担当者が個人で資料作成しているために、市場調査などを二重で行ってしまう
- 社内で名刺管理を共通化していないため、他部署から顧客へ連絡をしたいときに、営業担当者自らが改めて伝達しなければならない
これらの業務に共通する問題点は「社内で十分な情報管理・共有ができていないこと」です。
このような状況に悩まされている場合は、営業担当者が時間や場所を選ばず各種資料や情報、名刺データなどへアクセスできる「情報管理・共有の仕組み」を取り入れましょう。すると、営業の業務効率化を一段階先に進めることができます。
2-2.社内文書の作成や承認に時間がかかる
2つ目は「社内文書(会議資料や報告資料、その他の書類)の作成、承認に時間がかかる」というものです。
営業担当者が行っている社内文書関連業務には、以下のようなものがあります。
社内文書関連業務の例
- 社内報告資料の作成や承認
- 契約締結などに関する他部署への依頼書作成
- 請求書発行先など、取引先情報を他部署へ共有するための依頼書作成
これらの業務は、社内文書のフォーマットが統一されていなかったり、電子化ができていなかったりすると、作成や管理、承認までに時間がかかってしまいます。感染症流行による在宅勤務の増加などに伴い、社内文書の電子化がある程度進んできている企業も増えてきましたが、書類を手書きで作成している企業はまだ残っている状況です。
そのような企業は、社内文書のフォーマット統一や電子化、承認フローの電子化などにより、「社内文書関連業務を効率化すること」に取り組むべきだと考えられます。
社内文書の作成から承認までのスピードを短縮する、あるいは社内文書の管理や検索を容易にすることなどにより、営業担当者が他の重要な業務へ時間を割ける状態を作っていきましょう。
2-3.社員によって営業スキルや推進方法が異なる
3つ目の問題点は「社員によって営業スキルや推進方法が異なる」という点です。
営業の仕事は、単純作業ではありません。顧客のニーズを掴むこと、また、顧客ニーズに対して的確な提案を行うなどの能力が問われます。そのため、「営業担当者によって、営業スキルは違って当たり前」「優秀な営業担当者のスキルレベルまでは、個人の努力で追いつくことが重要」という認識を持っている方もいるかもしれません。
しかしながら、「顧客向けのプレゼンテーション資料を準備する」という業務一つとっても、優秀な社員が以前に作成した資料を誰でもすぐに参照できる、あるいは、営業成績が良好な担当者の資料作成・発表方法を学ぶことができれば、「プレゼンテーション準備にかかる時間の削減」や「顧客向けの提案の質の向上」などへ繋げることができるはずです。
そこで着手すべき取り組みが、「情報共有の効率化」です。
優秀な営業担当者が、彼らの知見として蓄えている業務遂行上の「コツ」や営業推進方法などを、他の担当者へも共有できる状態にすることで、営業担当者全員のスキルを上げていくことができます。
3.営業の業務効率化に役立つ方法4選
ここまで、営業の業務効率化を妨げる問題について詳しくお伝えしてきました。本章では、それらの問題を解消しつつ、営業の業務を効率化するための具体的な方法を見ていきましょう。
営業の業務効率化方法
- 社内・部署内の情報を一元化する
- 社内・部署内の紙の書類を電子化する
- 社内・部署内で用いる資料形式を統一する
- 社内・部署内の情報共有ルールを設ける
3-1.社内・部署内の情報を一元化する
一つ目は、「社内・部署内の情報を一元化する」という方法です。
例えば、商品情報が複数のファイルに分かれて作成・保存されていたり、取引先の資料が複数のフォルダに散在していたりすると、必要な情報を探すためだけに、社員の余計な時間がかかってしまいます。そのため、社内の複数箇所に分散されている情報は、可能な限り統一して管理することが大切です。
ただし、最初から全ての情報を一元管理することは困難です。
そこで、まずは一元管理することで業務効率が上がりやすい以下のような情報の集約から取り組んでみることをお勧めします。
一元管理することで効率化が期待できる情報
- 顧客情報
- 営業担当者のスケジュール
- プロジェクトの進捗状況
- 販促物のデータ
- 部内の会議で使用する資料
例えば、顧客情報の一元管理には、以下のようなメリットが想定されます。
顧客情報を一元管理するメリット(例)
- どの顧客を誰が担当しているかが一目でわかる
- 情報を可視化することにより、再購入や追加契約に繋がる可能性が高い顧客を絞りやすくなる
- 業界やエリア、規模などに応じて顧客を整理することにより、効率的な担当振り分けやアプローチ方法を考えることができる
- 顧客の連絡先が一元管理されることで、担当営業不在時にも連絡がスムーズに行えるようになる
- 自社との取引のきっかけ(展示会・テレアポ・紹介など)を記録しておくことにより、顧客との中長期的な関係構築へ活かせる など
顧客情報を一元管理することにより、上記のようなメリットを享受しながら、営業活動を効率化することが可能です。
顧客リストやデータベースを作成する際は、以下のような項目をExcelなどで管理、あるいはデジタルツール上へ蓄積したうえで、社内で共有し、共有後も各担当者新しい情報を入手した際は、情報を都度入力してもらうことが重要です。
顧客リストやデータベースで管理すべき顧客情報(例)
- 会社の基本情報(会社名、住所、社員数、拠点数、資本金、年間売上高、業種、URLなど)
- 自社との契約関係(昨年の取引額、契約中の商品やサービス、契約期間など)
- 担当者の名前、部署名、役職、連絡先(電話、FAX、メールアドレスなど)
- 取引のきっかけ(展示会・テレアポ・紹介など)
情報管理の効率化に向けた第一歩として、まずはこのようなリスト・データベースの作成を進めましょう。
さらに、上記のリストやデータベース作成にあたっては、名刺管理方法の改善も、重要なポイントの一つです。
名刺は一般的に個人間で取り交わされるものなので、その管理を個人に任せている企業は多いと思います。しかしながら、名刺に含まれる取引先の部署名や連絡先などは、企業全体の営業戦略を立てる上で重要な情報であり、大切な資産です。そのため、本来は企業主導でしっかりと管理すべきものだといえるでしょう。
ただし、営業担当者が、「名刺1枚1枚の情報を手作業でExcelやデータベースへ転記し、情報を集約する」という方法では、膨大な時間がかかってしまいます。そのため、以下のような名刺管理サービスを活用するのがおすすめです。
名刺管理サービスとは
- 名刺を専用のスキャナーやスマホのカメラで撮影するだけで、記載されている情報をデジタルデータとして管理できるサービスのこと
- 法人契約を行うと、組織内で名刺情報を共有することが可能に
名刺管理サービスを活用する主なメリット(例)
- 紙の名刺を保管する必要がなくなることで、管理の手間や保管スペースを削減できる
- 必要な名刺の情報は、データベース上で検索すればすぐに入手可能なため、名刺を探す時間を削減できる
- 顧客と自社の社員との繋がりを可視化することで、既存のコネクションを有効活用できる
上記のように名刺管理を電子化すると、顧客情報を探すためにかかっていた余分な時間の削減に役立つだけでなく、効率的な顧客開拓にも役立ちます。例えば、「自社の●●さんが、▲▲社の常務と名刺交換をしたことがあるようだから、そこを糸口にアプローチをかけてみよう」というように、実際の営業活動へ繋げることができた事例もあります。
そのため「現状は紙の名刺を机の中に保管しているだけで、有効活用できていない」「名刺管理は個人に任せている」という場合は、このような名刺管理サービスを活用することにより情報管理を効率化していきましょう。
3-2.社内・部署内の紙の書類を電子化する
営業業務の効率化の第一歩として取り掛かりやすい方法の一つに、手書きの書類や紙でやり取りされている書類を電子化することが挙げられます。
現在は、一から手書きで書類を作成する企業は少なくなってきていると思いますが、「パソコンで作成・印刷した書類を各部署で回覧したうえで、担当者がコメントなどを記入する」といった業務フローが残っている企業は多いのではないでしょうか。
しかし、手書きを含め、紙の書類には以下のデメリットがあります。
紙の書類のデメリット(例)
- 紙の書類の印刷・保管コストが発生する
- 過去の書類に記載された内容の再利用はできないことがあり、記入の手間を削減できない
- 書類内容に関して、部署をまたいで承認を得るときなどは、物理的に書類を移動させなければならないため時間や郵送費用がかかる
そのため、まずは現在手書きで作成している、あるいは紙で管理・回覧しているような書類をピックアップしたうえで、使用頻度の高い書類から優先的に電子化することをおすすめします。
具体的な方法は以下の通りです。
書類を電子化する方法(例)
- 複数の担当者が閲覧してコメントや評価などを入れる必要があるような書類の場合は、コメント履歴をリアルタイムで共有できるデジタルツールを活用する
- ワークフローシステム (申請作業や稟議作業などをオンライン上で行えるようにするデジタルツール)を導入する
- OCRツール(紙や写真に書かれた文字を読み取って、パソコンなどで使える電子テキストデータへ変換するデジタルツール)を導入する など
上記のような方法により、紙の書類の電子化、ならびにその書類のやり取り(作成・申請・承認など)をオンライン上で一貫して対応できるようになれば、場所や時間の制約を受けずに可能な業務の範囲が広がるため、業務効率化への近道となります。
3-3.社内・部署内で用いる資料形式を統一する
3つ目は、「社内・部署内で用いる資料形式を統一する」という方法です。
各種資料のフォーマットや、社内で使用するソフトが統一されていない場合、以下のような問題が生じる可能性があります。
資料形式が統一できていないときに生じる問題(例)
- 作成者によってプレゼンテーション資料の形式が異なるため、聞き手が内容を把握しにくい
- 資料フォーマットがバラバラなため、複数の取引先の情報を比較するときに、各フォーマット上で情報の過不足が発生し、スムーズに比較・判断できなくなる
- 資料を作成する際に、「どのような形式で資料を作るか」という部分から考えなければならないため、作成に余計な時間がかかる
- 社員によって使用するソフトが違い、他の資料の情報を容易に引用できなくなってしまう など
このような問題を防ぐため、社内や部署内で使用する資料の形式は統一していきましょう。
例えば、以下のような方法から取り組んでいくことは選択肢の一つです。
資料形式を統一する方法(例)
- プレゼンテーション資料作成時の社内ルールを決める
例)スライドのサイズは「16:9」にする、地の文字色は濃いグレーにする、色数は指定の3色しか使わないようにする、フォントは指定のものに統一する、など - 見積書や請求書はExcel、送り状はWord、のように使用ソフトに関する社内ルールを作る
- WordやPowerPointのフォーマットは、社内一律で設定したフォーマットを社員へ配布し、それを基に資料作成を行うようにする など
このような方法を取り入れると、資料上へ情報を取り纏める側と、資料から情報を受け取る側の、双方の負担を減らすことが可能です。
3-4.社内・部署内の情報共有ルールを設ける
最後の方法は「社内・部署内の情報共有ルールを設ける」というものです。
社内に何も情報共有ルールが設けられていない中で、各社員が自由に情報共有を行ってしまうと、以下のような問題が生じる恐れがあります。
ルールが設けられていない中で情報共有が行われた場合の問題(例)
- 社員によって、フォルダ名やファイル名が異なるため、欲しい情報の場所をすぐに把握できない
- 商談結果の共有を後回しにしたことにより、顧客フォローが間に合わなくなった
- すぐに対応しなければならない情報と、そうでない情報が混在する など
このような場合は、以下のような情報共有ルールを定めることにより、部署全体の業務効率を高めていくことが可能です。どれほど有用な情報も、必要な時に必要な人が入手できなければ、有効活用することはできません。効率的に情報共有が行える土台を作るという観点からも、情報共有ルールを定めることが重要です。
情報共有ルール(例)
- 検索性を高めるため、フォルダ名・ファイル名のルールを定める
- 商談結果は翌日午前中までに部内に共有する、などの共有タイミングを決める
- 緊急性の高いメールの場合はタイトルに【急ぎ】などの文字を入れるようにする
さらに、単純な「情報」だけでなく、言語化されていないような「ノウハウ」を蓄積・共有しておくことにより、情報をより有効に活用できるようになるでしょう。
具体例として本項では、テレアポ(電話によるアポイントメント取得)を取り上げます。テレアポは、熟練した担当者が行う場合とそうでない場合とを比較すると、1つの案件を成功させるまでにかかる時間や手間に大きく差が生まれやすい業務です。
そこで、社内の優秀な担当者が持っているノウハウを、他の社員へも展開して誰でも使えるようにすることにより、業務の事前準備や事後処理にかかる時間を効率化でき、さらにテレアポの成功率も高めていくことができるようになります。
実際に、テレアポのノウハウをマニュアル化し、エース社員が実践している技術を他の担当者も参考にできるようにしたことにより、チーム全体としての成約率が上がったという例も珍しくありません。
テレアポのノウハウを蓄積・共有するためにおすすめの方法は以下の通りです。
社内のテレアポのノウハウを蓄積・共有する方法(例)
- WordやExcelなどでテレアポのマニュアルを作成し、誰でも閲覧できるようにする
- テレアポ成功率の高い社員に、実践時のポイントなどを定期的に更新してもらう
- 社内チャットでテレアポ専用のスレッドを作り、チャット上でノウハウを共有する など
ただし、マニュアルを作成する際によくある失敗の一つに、最初にマニュアルを作ったきり、内容が更新されず古くなっていくという事態が考えられます。そのため、テレアポが得意な社員をマニュアル作成担当に任命し、「3ヵ月に1回は必ず更新する」などの更新ルールを最初にしっかり決めておくと良いでしょう。
テレアポに限らず、一定のルールの下に営業活動のノウハウを社内へ蓄積できれば、「営業が得意な人が異動や退職でいなくなったために、売上が大幅に下がってしまった」というような事態を防げるほか、担当者間の引き継ぎにかかる時間や手間も削減することができます。
営業の業務やスキルアップに必要な情報を、誰もが容易に手に入れられる環境を作ることにより、営業社員全員の営業レベルを向上させることが可能になるのです。
4.中長期的な営業の業務効率化を図るためには、売上拡大をサポートするデジタルツールの導入も有効
前章では、営業の社内業務を中心に、基本的な業務効率化方法をご紹介してきましたが、「社内業務を効率化する方法は理解したが、肝心の『売上拡大』を効率的に目指していける方法は無いだろうか?」と思った方もいるかもしれません。
そこで本章では、企業の中長期的な売上拡大を効率的にサポートするデジタルツールの例として、以下の2つをご紹介します。
- SFAツール
- CRMツール
ただし、このような一部のデジタルツールは、導入前に「社員の二―ズ調査」「要件定義」「導入準備」などが必要となり、実際に導入して効果が出るようになるまでに、数ヶ月単位で時間がかかってしまう場合があります。
また、利用者となる社員側にも、一定程度の「デジタルリテラシー(=デジタル技術を業務へ活用するための、『デジタル』に関する基本的な知識・スキル)」が求められます。
そのため、デジタル化に慣れていない会社や部署の場合は、まずはすぐに実践可能な業務効率化方法を取り入れて一定の効果を出した後に、既存の業務フローを抜本的に改革するためのデジタルツールの導入検討を改めて行う、という流れがおすすめです。
とはいえ早い段階から、売上拡大を効率的にサポート可能なデジタルツールにはどのようなものがあるのか、知識として知っておくことは重要です。ぜひ、本章を参考にしてみてください。
4-1.SFA
最初に紹介するのは、日々の営業活動の可視化に役立つ、SFA(セールスフォースオートメーション)です。
SFA(セールスフォースオートメーション)とは
営業の商談から受注までの進捗、顧客に対する社員の行動履歴など、営業活動に伴う様々な情報を可視化できるシステム
顧客と対面やメール・電話などでやり取りした内容は、営業担当者と上長間では日報などで共有されるものの、二者間でしか把握していないというケースが散見されます。しかしながらそのような場合は、他の上長や同僚、経理担当者などが商談の進捗や受注見込みなどをリアルタイムに確認することはできません。
SFAなどのデジタルツールでは、営業活動の様々な状況を可視化することが可能になります。すると、チーム内における情報連携がスムーズになるため、顧客対応に成功した事例や顧客反応が良かった提案書などの共有、困っている営業担当者のサポートなどを、迅速に行えるようになります。
このようにSFAは、営業部全体としての活動をレベルアップすることへ役立ちます。
4-2.CRM
次にご紹介するのが、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)です。
CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)とは
顧客情報や、顧客情報に紐づく営業活動(企業名、個人名、部署名、メール配信状況、問い合わせ履歴など)を一元管理できるツール
CRMでは、顧客の基本情報だけでなく、どのような問い合わせが過去にあったのか、どの営業担当者とどのような内容の話をしたのか、などといった情報を見やすく管理することができます。
SFAが、商談を含む営業活動を軸に各種データを一元管理するものである一方で、CRMは、顧客自体を軸に、自社との関係性に関する各種データを一元管理する点が特徴となっています。
顧客数(取引先数)が数十社程度であれば、Excelなどで顧客リストを作成する方法でも、顧客管理が可能とみられます。しかしながら、「顧客数(取引先数)が数百を超える」「Excelでは管理・共有しづらいような細かい内容も営業部内でシェアしたい」といった場合は、多くのデータをまとめて管理できる、CRMを活用すると良いでしょう。
なお、具体的に各デジタルツールの導入を検討するにあたっては、以下の7つのSTEPが想定されます。
営業の効率化を成功に導く、「初めの7STEP」
- アナログで非効率な業務をリストアップする
- リストアップした業務に「効率化すべき優先順位」をつける
- 業務効率化後のゴールや必要な条件を整理する
- 課題解決や業務効率化につながるデジタルツールを選定する
- デジタルツールの「デモンストレーション」や「無料トライアル」で使用感を確認する
- デジタルツールを営業部の数名でスモールスタートする
- デジタルツールを営業部全社員に向けて展開する
この流れに沿って、デジタルツールの導入や選定を行うことができれば、スムーズに営業の業務効率化を進めることが可能だと考えられます。
詳しくは、「DXの進め方7STEP!成功するためのポイントや失敗回避に向けたチェック項目を解説」のコラム記事も参考にしてみてください。
ここまで記事を御覧いただいた上で
「デジタルツールの導入は難しそう」
「自分で調べて対応する時間がない」
「一度、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
5.まとめ
この記事では、営業の業務効率化を推進するための方法を解説してきました。
最初に「社内業務を中心に業務効率化へ取り組むことが重要である」ということをお伝えした上で、社内業務の中でも、特に問題となりやすいポイントとして、下記の内容を解説しました。
営業の業務効率化を妨げている3つの問題
- 営業活動前の準備や、営業活動後の情報管理に時間がかかる
- 社内文書の作成や承認に時間がかかる
- 社員によって営業スキルや推進方法が異なる
上記のような問題を解消しつつ、営業の業務を効率化するための具体的な方法としては、以下の4つを紹介しています。
営業の業務効率化方法
- 社内・部署内の情報を一元化する
- 社内・部署内の紙の書類を電子化する
- 社内・部署内で用いる資料形式を統一する
- 社内・部署内の情報共有ルールを設ける
さらに、企業の中長期的な売上拡大を効率的にサポートするデジタルツールの例として、以下2つをご紹介しました。
営業の売上拡大サポートツールの例
- SFAツール
- CRMツール
最後までお読みいただいたことで、営業の業務効率化にはどのような方法があるのか、業務効率化を進めないことによるデメリット、進めることにより享受できるメリットなどを、具体的にイメージできるようになったのではないでしょうか。
営業の業務効率化検討にあたって、本記事が少しでもお役に立てたようであれば幸いです。