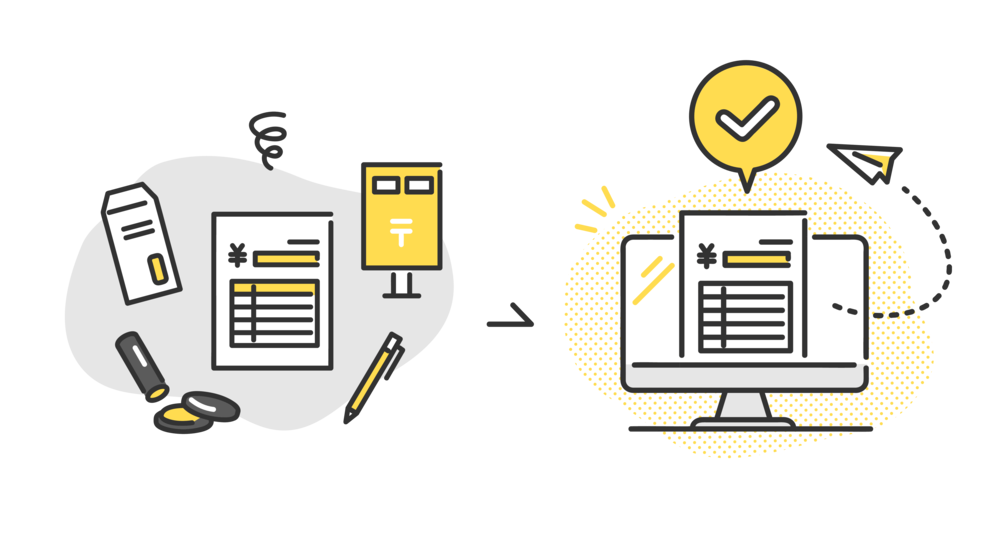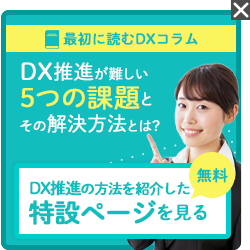更新日:
DXの進め方7STEP!注意すべきポイントやチェック項目を解説

「DXを推進したいが、失敗しないか不安だ…」
「成功する『DXの進め方』を知っておきたい!」
ある日突然、会社のDX推進を任されたとしても、DX推進の実務経験がなく、何から始めたらいいのか分からない、といった担当者の方も多くいらっしゃると思います。
はじめに、今回の記事ではDXを成功に導く、初めの「7STEP」をご紹介しています。
7つのSTEPの中では、DXを推進したことがない企業の方やDXの実務経験が少ない担当者の方に向けて、本格的なDX推進の足掛かりとなる「業務のデジタル化」へ特に重点を置いて解説しています。
「STEP1」から順に実行していけば、DXを着実に進めることが可能です。
| STEP1 | アナログで非効率な業務をリストアップする |
|---|---|
| STEP2 | リストアップした業務に「効率化すべき優先順位」をつける |
| STEP3 | 業務効率化後のゴールや必要な条件を整理する |
| STEP4 | 課題解決や業務効率化につながるデジタルサービスを選定する |
| STEP5 | デジタルサービスの「デモンストレーション」や「無料トライアル」で使用感を確認する |
| STEP6 | デジタルサービスを特定の部門・部署でスモールスタートする |
| STEP7 | デジタルサービスを全従業員に向けて展開する |
加えて、本記事では、DXの成功のために押さえておきたい2つの重要ポイントや、失敗回避に向けた5つのチェック項目についても解説します。事前にチェック項目を押さえたうえでDXに取り組むことにより、しっかりとした取り組み効果を期待することが可能です。
「手始めに、特定の業務や部署のデジタル化からスタートし、全社的なDXの足がかりにしたい」といった担当者の方にとって、ご参考になる記事となっています。
それでは早速、見ていきましょう。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.DXを成功に導く、初めの「7STEP」
それでは早速、DXを成功に導く、初めの「7STEP」を解説したいと思います。
なお、冒頭でご説明した通り本記事では、本格的なDX推進の足掛かりとなる「業務のデジタル化」へ特に焦点を絞って解説します。
【STEP1】「アナログで非効率な業務」をリストアップする
まずは、社内業務のうち「アナログで非効率な業務」のリストアップからスタートしましょう。
リストアップする業務を洗い出す手段には、さまざまな方法が考えられますが、例えば「各部署の従業員へのアンケート」や「聞き取り調査(インタビュー)」などがあります。
具体的には、以下のような質問項目が想定されます。
「アナログで非効率な業務」をリストアップするための質問項目例
- 担当している業務のうち、特に多くの時間を割いている業務は何ですか?
- (特に多くの時間を割いている業務について)「所要時間」「発生件数」「発生頻度」「業務対応に関わる従業員数」について、おおよその目安を教えてください。
- (特に多くの時間を割いている業務について)「デジタル化(デジタルサービスの導入)」によって作業工数を削減できそうな、または作業工数を削減したいと考える業務を教えてください。
「アナログで非効率な業務」をリストアップする過程では、上記の通り、作業に係る実際の所要時間や業務対応に必要な人数を聞くなどして、なるべく「業務量の定量化(数値や数量で表現すること)」に努めるようにしてみてください。すると、「解決すべき優先順位が高い業務」をピックアップしやすくなります。
業務量の定量化は、デジタルサービス導入後に「どの程度の導入効果があったのか」を検証し易くなる点でもおすすめです。
【STEP2】リストアップした業務に「効率化すべき優先順位」をつける
各部署の従業員への聞き取り調査が完了し、アナログで非効率な業務を洗い出すことができたら、各業務に「効率化すべき優先順位」をつけてみましょう。
優先順位をつける方法としては、「従業員の総作業工数=業務の所要時間(1人あたり)×発生件数×発生頻度×業務対応に関わる従業員数」で比較して、より多くの作業工数が割かれている業務の優先順位を高くする、というやり方も選択肢の一つです。
例えば、下記のように営業部内の「アナログで非効率な業務」2つ(下記図表:業務A、業務B)を比較した場合、業務Aの方が、従業員の作業工数が多いため、効率化すべき優先順位は高いと判断できます。
| 業務A | 業務B | |
|---|---|---|
| 業務内容 | 「名刺情報」のデータベース入力 | 「経費・出張費」の申請 |
| 所要時間(1人あたり) | 7分/1件 | 15分/1件 |
| 発生件数 | 7件/月 | 2件/月 |
| 発生頻度 | 4回/月 | 2回/月 |
| 業務対応に関わる従業員数 | 1人 | 1人 |
| 従業員の総作業工数 (業務の所要時間×発生件数×発生頻度×業務対応に関わる従業員数) |
計196分 | 計60分 |
| 解決すべき優先順位 | 高い(◎) | 低い(△) |
【STEP3】業務効率化後のゴールや必要な条件を整理する
アナログで非効率な業務について、自社で解決すべき優先順位をつけることができたら、実務担当者を交えてさらに詳しい聞き取り調査を行い、その業務を効率化できた後のゴールや必要な条件を整理しましょう。
例えば、営業部への聞き取り調査の結果、「名刺情報を顧客データベースに入力する作業」について、効率化すべき優先順位が高い業務だと判明した場合、以下のような追加質問が想定されます。
要件整理するための質問項目例
(営業担当者に対して)「名刺情報を顧客データベースに入力する作業や、名刺情報の活用において、このような問題が解決できたら助かる」という理想像や機能があれば、教えてください
想定回答例
- データベース入力にかかる作業時間を半分以下にしたい
- 名刺をスマホで読み取るだけで、自動的に「顧客情報」を入力できる機能があったら便利だと思う
- データベース登録した顧客のステータス(受注・失注・提案中)に応じて、セミナー案内などを名刺情報のメールアドレスへ一斉送信できるようにしたい
- 今は、社内でしか名刺情報を確認できない。外出先やテレワーク中でも、名刺情報を確認できるようにしてほしい
上記のように、実務担当者や関係部署へ詳しく追加の聞き取り調査を行うことなどにより、「自社にとって本当に必要なサービス(機能)がどのようなものか」も、浮き彫りになっていきます。
【STEP4】課題解決や業務効率化につながるデジタルサービスを選定する
STEP3で整理した効率化後のゴールや必要な条件に基づいて、課題解決と業務効率化につながるデジタルサービスを探しましょう。
少しでも気になる商品・サービスがあれば、それぞれの取扱事業者へ、資料請求や問い合わせを行ってみるのがおすすめです。
加えて、各事業者へは「費用対効果(予算をかけただけの効果が期待できるか)」や「社内システムとの連携が可能か」などについても確認することで、商品・サービス利用後の効果を得やすくなります。
「適切なデジタルサービスを比較・検討したい」という場合には、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
【STEP5】デジタルサービスの「デモンストレーション」や「無料トライアル」で使用感を確認する
気になるデジタルサービスをピックアップできたら「デモンストレーション」や「無料トライアル」を実際に利用することにより、サービスの実際の使用感を確認しましょう。
デジタルサービスのデモンストレーションとは
架空の利用設定条件やデモデータ(架空のデータ)を用いて、実際のサービス操作画面の閲覧や操作方法の確認を行うこと
デジタルサービスの無料トライアルとは
実際に、一定期間無料でサービスを利用してみること (無料トライアルは、利用可能期間や機能が制限されている場合もあります)
どれほど自社のニーズを満たすデジタルサービスだったとしても、高度な機能が多すぎて実際に従業員が使いにくい仕様であるなどした場合は、そのサービスが社内で浸透しない可能性は高くなってしまいます。
従業員がデジタルサービスを活用しなくなってしまえば、当初の目的である「業務効率化」を達成することはできません。
デジタルサービス導入失敗の可能性を最小限に抑えるためにも、使用感のチェックは必ず行うようにしましょう。
【STEP6】デジタルサービスを特定の部門・部署で「スモールスタート」する
無料トライアル等の結果、従業員からデジタルサービスの導入に前向きな声が挙がった際は、一部の部門や部署で「スモールスタート※」してみましょう。
※物事を小さい範囲で開始し、徐々に範囲を広げていくこと
実際に複数名の従業員がサービス利用を開始することにより、思わぬ不具合や、「本当はこんな機能が欲しかった」などの隠れた要望が分かる場合もあります。
「スモールスタート」を実施するなかで従業員から挙がる声の例
「無料トライアルでは使いやすいと思ったが、〇〇の機能がないと困ることに気づいた。このサービスには〇〇の機能は備わっているのか知りたい。」
「無料トライアルでは、△△の機能がいいと感じたが、実務ではそれほど使うシーンがない。それよりも××の機能の方が必要だ。」
なお、スモールスタート中に、一部の従業員が「より効率的な使い方」を発見するような場合もあります。
そのような場合は、本格導入の前に、発見された効率的な使い方をマニュアル化しておくことができれば、他の従業員にとっても心強いでしょう。
「思い切って最初から全社に導入してみたが、思っていたような業務効率化に繋がらなかった」という失敗にならないためにも、スモールスタートによる導入を心がけてみてください。
【STEP7】デジタルサービスを全従業員に向けて展開する
スモールスタートを経て、利用上の不具合や問題点がなければ、全社に向けたデジタルサービスの「本格導入」を行いましょう。
なお、本格導入前には、従業員へデジタルサービスの使い方を教える「ユーザー講習会」を開催するのがおすすめです。
どれほど使い勝手の良いデジタルサービスだったとしても、初めから全ての従業員が使いこなせるとは限りません。
デジタルサービス導入前の、従業員の不安・不満を少しでも取り除き、スムーズな形でサービス利用を開始するためにも、ユーザー講習会の開催は重要です。
その場で、基本的な使い方を解説しつつ、わからないことは気軽に質問できるような場にできるのがベストです。
以上7つのSTEPが、本格的なDX推進の足掛かりとなる「業務のデジタル化」への具体的な取り組み方法です。
ぜひ、参考にしてみてください。
2.DXを成功させるために押さえたい2つの重要ポイント
前章を通じて、DX推進の足掛かりとなる業務自体のデジタル化について、具体的なイメージが湧いたのではないでしょうか。
業務のデジタル化、ひいてはDXを成功させるうえで押さえたい「重要ポイント」は2つあります。
2つの重要ポイント
- デジタルサービス導入前に、実務担当者の課題を「本質的に」解決できるサービスなのか見極めること
- デジタルサービス導入後も継続的に「効果測定」すること
①デジタルサービス導入前に、実務担当者の課題を「本質的に」解決できるサービスなのか見極めること
デジタル化サービスを選定するうえで、もっとも重要なのが「実務担当者の課題を『本質的に』解決できるサービスなのか?」という視点です。
例えば、出退勤の都度、紙のタイムカードへの打刻によって行っていた面倒な勤怠管理を、PCやスマホアプリから出退勤打刻を完了させることが可能な「勤怠管理システム」に置き換えることを検討した場合、そのようなシステムを導入するだけでも、勤怠管理に係る手間を大幅に削減できることでしょう。
しかし、経理担当者の潜在的なニーズは「単なる勤怠情報の収集だけでなく、給与計算までをシステム上で纏めて行えたら…」というものかもしれません。
そのような場合は、給与計算も行うことが可能な勤怠管理システムが望ましいと考えられます。
このように、現場担当者へ「どこまで課題解決ができれば望ましいか」についてしっかりとヒアリングを行い、適切なデジタルサービスを選定することが大切です。
なお、選定にあたっては、デジタルサービスを導入した企業の「成功事例」や「お客様の声」などの情報を収集することや、デジタルサービスを提供している事業者に「導入企業で喜ばれている機能」について聞いてみることも、一つの方法です。
②デジタルサービス導入後も、継続的に利用状況の確認や効果測定を行うこと
デジタルサービスの導入後も、継続的にサービス利用状況の確認や効果測定(サービスの導入費用に対して、適切な効果が得られているか)」について検証するようにしましょう。
デジタルサービスの導入当初こそ、業務効率化につながっていたものの、社内外の環境変化とともに、デジタルサービスがほとんど使われなくなってしまう、といったケースは想定されます。
例えば、経理部の希望で「経費精算システム」を導入した場合、デジタルサービスの導入当初こそ、営業担当者の出張や会食など、頻繁に利用機会があったかもしれません。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大などに伴い、営業担当者へ「オンライン会議システム」や「リモートワークの導入」を行った場合には、経費精算システムの活用機会が大幅に減少してしまう可能性もあります。
また、導入当初こそ社内の号令の下に、多くの従業員が経費精算システムを使っていたものの、実はシステムの操作性が良くなく、従業員が徐々にシステムを利用しなくなってしまう、といったことも想定されます。
こうした事態が発生した結果、デジタルサービス(システム)があまり使われていないにも関わらず、サービス利用料金だけ支払い続けるような事態は避ける必要があります。
そのため、サービス導入後も、サービス利用状況や導入効果を継続的に確認・検証するようにしましょう。
以上2点が、業務のデジタル化、ひいてはDXを成功させるために押さえたい重要なポイントです。
ぜひ、参考にしてみてください。
3.DXの失敗回避のために押さえたい5つのチェック項目
前章では、DXを成功させるために押さえたいポイントをご紹介しました。
一方、DXには多くの人が陥りやすい失敗ポイントがあるため、失敗しないためのチェック項目として、本章では5つのチェック項目をご紹介しています。
DXで失敗しないために押さえたい5つのチェック項目
- 従業員の「デジタルスキル」を踏まえてデジタルサービスの選定を行う
- サービス導入検討時の決裁者への説明には「費用対効果」「無料トライアルを実施した際の従業員の声」などを用いる
- デジタルサービスの「サポート体制」を確認する
- デジタルサービスの「使い方マニュアル」を用意する
- デジタルサービスの検討に自信がないときは専門家へ「自社に合ったサービス」を相談する
これらのチェック項目を押さえれば、DXに失敗するリスクを最小限に抑えることができます。
ぜひ、参考にしてみてください。
①従業員の「デジタルスキル」を踏まえてデジタルサービスの選定を行う
従業員が抱えているアナログで非効率な業務の困りごとを解決して、業務のデジタル化やDXを推進することが、デジタルサービス導入の目的です。
しかしながら、従業員が使いこなせないデジタルサービスは、使われずに放置されてしまうことがあります。
デジタルサービスの選定を行う際は、どれほど業務効率化につながる多機能なサービスであったとしても、従業員のデジタルスキルを過度に超えるような、高度なサービスを選ばないよう注意しましょう。
デジタルサービス導入検討を行う担当者でデモンストレーション画面を閲覧するだけでなく、無料のトライアル期間中に実際に従業員へ利用してもらうなどして、従業員の現在のデジタルスキルも見極めながら、「従業員が無理なくデジタルサービスを利用することが可能そうか」を判断しましょう。
②サービス導入検討時の決裁者の説得には「費用対効果」「無料トライアルを実施した際の従業員の声」などを用いる
「実務担当者は、サービスの導入に前向きだが、決裁者の承認が得られない…」
このような場合、決裁者から「デジタルサービス導入メリット」について十分に理解を得られていない可能性があります。
中には、「導入して失敗するリスクを負うくらいなら、現状維持で良いだろう」と考える決裁者もいるかもしれません。
そのような際には、決裁者に対し、「費用対効果」「無料トライアルを実施した際の従業員の声」などを含めてデジタルサービスを導入検討すべき理由を伝えるようにしてみてください。
そうすれば、サービス導入検討について決裁者が前向きに考えてくれる可能性が高まります。
決裁者による承認を得るための説得例
費用対効果
「現在アナログで行っている作業には、従業員XX名の計〇分の時間がかかっており、時給換算では●万円の損失(コスト)が発生している状況です。新しく検討しているデジタルサービスは、初期費用は◇万円、月額費用は◆万円かかりますが、現状の業務で発生しているコストと比べて安価になっています。利用から1年で初期投資も回収できるため、費用対効果がとても高いサービスとみられます。導入を検討してはいかがでしょうか。」
無料トライアルを実施した際の従業員の声
「無料トライアルでは80%の社員から『新しいデジタルサービスは使いやすい』『実際に使ってみると、営業効率が上がる』といった声がありました。従業員の多くから、導入に対して前向きな声があがっている状況です。このサービスを前向きに検討してみてはいかがでしょうか。」
③デジタルサービスの「サポート体制」をチェックする
デジタルサービスの無料トライアル期間を経て「これなら、従業員も難なく使いこなせそうだ」と判断できたサービスについては、デジタルサービス提供事業者による「サポート体制」についても、チェックしましょう。
なぜならば、デジタルサービスの利用を進める中で、サービスに関して当初想定していなかった疑問点や不明点が出てきた際に、それらについてサービス提供事業者へ従業員自らが問い合わせを行うなどして解決することができれば、DX推進担当者や関連業務を所管する管理職の負担を最小限に抑えられるからです。
サポート体制について、以下のような事項を確認のうえ、全従業員へアナウンスすると良いでしょう。
サポート体制に関する確認事項例
- サポート担当者から受けられるサポート方法(メール/電話/チャット)
- サポート時間
- 基本的な操作方法に関する資料やよくある質問が掲載されているWebサイトのURL
④デジタルサービスの「使い方マニュアル」を用意する
デジタルサービスの利用開始前には、デジタルサービスの「使い方マニュアル」を社内に用意しておきましょう。
先述の通り、従業員が使いこなせるサービスだったとしても、想定外の不明点や「このような機能があるだろうか」といった疑問が出てくる可能性があるからです。
デジタルサービスの提供事業者側で、利用者用のマニュアルを用意していることも多くあります。
事業者側へも確認してみましょう。
⑤デジタルサービスの検討に自信がないときは、専門家へ「自社に合ったサービス」を相談する
「自社が導入すべきデジタルサービスがどれなのか、よくわからない」「適切なサービスを選定できているか、自信が無い」といった場合には、デジタルサービスに精通している専門家に相談することがオススメです。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
4.まとめ
業務のデジタル化の具体的な進め方や、DXで成功するため・失敗しないために押さえておくべきポイントなどについて、理解を深めることはできたでしょうか。
ここで本記事の内容を整理したいと思います。
| STEP1 | アナログで非効率な業務をリストアップする |
|---|---|
| STEP2 | リストアップした業務に「効率化すべき優先順位」をつける |
| STEP3 | 業務効率化後のゴールや必要な条件を整理する |
| STEP4 | 課題解決や業務効率化につながるデジタルサービスを選定する |
| STEP5 | デジタルサービスの「デモンストレーション」や「無料トライアル」で使用感を確認する |
| STEP6 | デジタルサービスを特定の部門・部署でスモールスタートする |
| STEP7 | デジタルサービスを全従業員に向けて展開する |
「DX」という単語から、何か大きな取り組みを想像してしまい、ハードルを高く感じてしまうのではなく、まずは上記の7つのSTEPにしたがって「業務のデジタル化」を少しずつでも進めていくことからでも、中長期的な視点でDXを推進することが可能です。
その中では、以下のようなポイントを押さえることが重要です。
DXを成功させるために押さえたい2つの重要ポイント
- デジタルサービス導入前に、実務担当者の課題を「本質的に」解決できるサービスなのか見極めること
- デジタルサービス導入後も継続的に「効果測定」すること
DXの失敗回避のために押さえたい5つのチェック項目
- 従業員の「デジタルスキル」を踏まえてデジタルサービスの選定を行う
- サービス導入検討時の決裁者への説明には「費用対効果」「無料トライアルを実施した際の従業員の声」などを用いる
- デジタルサービスの「サポート体制」を確認する
- デジタルサービスの「使い方マニュアル」を用意する
- デジタルサービスの検討に自信がないときは専門家へ「自社に合ったサービス」を相談する
デジタル化やDX推進にあたって、具体的にデジタルサービスの導入を検討する際は、デジタルサービスの導入前の準備段階から、実際のサービス利用開始後にかけて、このようなポイントを押さえておくことが重要です。
「デジタルサービスを導入したからデジタル化・DXが上手くいく」「デジタルサービスの機能が悪いから、デジタル化・DXが失敗してしまった」と一概に考えるのではなく、デジタル化・DX推進に向けた社内の現状把握や体制づくりも非常に重要です。
DXを進めるにあたり、本記事が参考になりましたら幸いです。