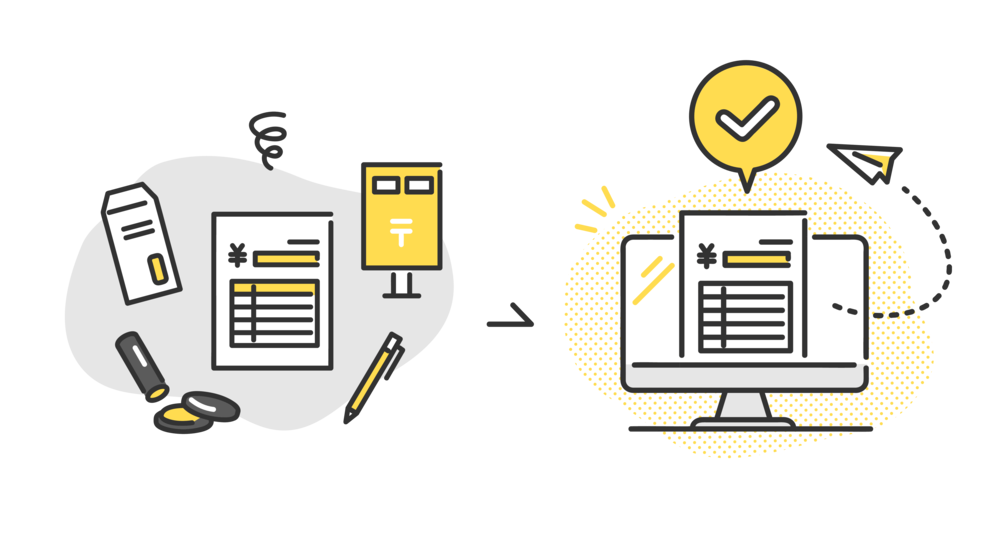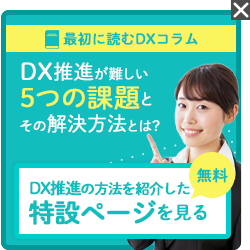更新日:
建設DXとは?建設業界のトレンドに出遅れないための基礎知識を解説

建設DXとは、建設業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を意味する言葉であり、デジタル技術を駆使して建設業の業務プロセスやビジネスモデルを変革することを指します。
建設DXは、建設業界が抱えている課題の解決策として期待されており、
- 業務プロセスの効率化・生産性向上
- 人手不足の解消
- 作業員の安全確保
- 職人の技術継承への貢献
といった多くのメリットがあります。
建設業に関係のある企業の方にとって、建設DXの遅れは、ビジネス上の機会損失へつながる可能性もあります。今後のさまざまな環境変化へ対応しながら事業を継続するためには、建設DXの実現に向けて、今から段階的に取り組んでいくことが重要です。
しかし、
「そもそも建設DXってどういうこと?」
「建設DXは自社にとって本当に必要なの?」
と感じている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、建設DXを理解し、その必要性を判断したい方に向けて、建設DXの基礎知識から取り組むメリット、自社に最適な建設DXを実現するためのポイントまでを解説します。
この記事でわかること
- 建設DXの意味や必要性
- 建設業界にDXが求められる背景
- 建設DXに取り組むメリット
- 建設DXで活用されるデジタル技術
- 建設DX実現に向けて意識するポイント
この記事を読むことで、建設DXによって自社のビジネスにどのような変化が期待できるのかを理解するとともに、DXに取り組む必要性を判断するための参考にしていただければと思います。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.建設DXの基礎知識を解説
「建設DX」とは、建設業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を意味する言葉です。
とはいえ、建設業のDXとはどのような状態を表すのかわからない方も多いでしょう。なかには、DX自体の理解があいまいな方もいるかもしれません。
そのためこの章では、建設DXの基礎知識として
- DXの定義とデジタル化との違い
- 建設DXとはどのような状態を表す言葉なのか
- 建設DXが求められている背景
を詳しく解説します。
本章で、まずは建設DXについての理解を深めましょう。
1-1.DXの定義とデジタル化との違い
建設DXを理解するには、そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)がどのようなことを意味するのかという定義から理解してみましょう。わかりにくい単語は、まず正確な意味を知ることが重要です。
経済産業省によると、DXは以下のように定義されています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
参考:経済産業省「DX推進指標」とそのガイダンス| [2019]
この定義を見て、「デジタル化と何が違うの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
DXとデジタル化は、最終的な目的が大きく異なります。
デジタル化は、「アナログな作業を電子化する」「デジタルツールを活用し業務を効率化する」ことを目的に実施されます。それに対しDXは、データやデジタル技術の活用にとどまらず、仕事のあり方や企業のビジネスモデルを変革し、新たな価値を創造することを目的に行うのです。
つまり、DX実現までの過程における一つの段階として、デジタル化がある、という構造になります。
1-2.建設DXとはどのような状態を表す言葉なのか
建設DXとは、デジタル技術を活用し、建設業の業務プロセスやビジネスモデルを変革することです。
単純に個々の作業や業務をデジタル化するだけにとどまらず、それらのデータを活用・連携して、業務横断的に情報共有の精度やスピード、品質を高めるなど、事業全体の高度化を実現することまでを含めて建設DXであると言えるでしょう。
具体的には、AIやICT、IoTなどのデジタル技術(詳しくは「3.建設DXで用いられるデジタル技術と活用例」で解説)を複合的に活用することで、測量や設計、施工管理などのあらゆる業務の変革が可能となります。
たとえば、従来の測量作業をみると、複数の作業員が現場に赴いて行う方法が一般的でしたが、現在ではドローンを使った3次元測量により、測量作業の省人化や作業時間の短縮が実現できます。さらに、3次元測量データを正確な位置情報と連動させることで、建機の自動制御による作業の効率化も期待できるでしょう。
このように、単純な業務効率化だけでなく、安全で快適な労働環境のもと、個々の社員が知識や経験問わず高度な作業を行えるようになれば、建設業界における人手不足などの大きな問題を解消できる可能性があります。
建設DXを実現することで、建設にかかわる業務や組織体制の大きな変革にも繋がるのです。
1-3.建設DXが求められている背景
建設DXは、各建設業務の課題解決だけが理由で注目されているのではありません。建設DXが求められる更なる背景には、DXの遅れが経済全体へ及ぼす影響への懸念や、国内インフラ維持のための建設サービスに対するニーズの高まりも存在しています。
建設業界が担う事業の特性上、建設DXの重要度は非常に高いといっても過言ではないでしょう。
本章では、建設業にDXが求められている背景として
- DXの遅れが経済損失を招く「2025年の崖」
- 国内インフラの維持に必要な労働力の確保
の2点を解説します。
1-3-1.DXの遅れが経済損失を招く「2025年の崖」
経済産業省は「2025年の崖」という言葉を用いて、建設業界のみならずあらゆる産業におけるDXの遅れが大きな経済損失につながると発表しています。
「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」に初めて登場した言葉です。企業の競争力維持・強化のためのDXの必要性は理解されつつあるものの、実際のビジネス変革には繋がっていない現状を指摘し、「2025年の崖」という表現で警鐘を鳴らしました。
DXレポートでは、企業がデータ活用や業務の見直しなどに取り組まずレガシーシステムを放置した場合、IT人材の不足やシステムのセキュリティリスクの高まりによって、既存システムの維持管理費が高額になることが予測されています。このままでは、結果的にDXが実現しないだけではなく、2025年以降は年間12兆円もの莫大な経済損失が発生する試算となります。
そのため、あらゆる産業の企業に対して、DXに向けた取り組みを実施し、環境変化への柔軟な対応力を身に付けることが求められているのです。
DXの必要性について、こちらの記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
『DXはなぜ必要』の理由3点!読めば自社のDX推進メリットが理解できる
1-3-2.国内インフラの維持に必要な労働力の確保
建設業が、国民の生活や経済活動に必要となる既存のインフラを維持するために重要な役割を果たしていることも、建設DXが求められている背景のひとつです。
国内インフラの多くは高度経済成長期に建設されており、今後は老朽化による点検・整備などの需要が高まることが予測されています。建設業界はインフラの建設や整備を担っているため、インフラの質や機能維持のために必要な労働力の中長期的な確保は、国土交通省においても重要な課題とされています。
一方で建設業界は、就業者数減少や長時間労働の常態化といった課題を慢性的に抱える傾向にあり、人材採用や働き方改革に向けた対策が必要な状態です。こうした課題が改善されないまま放置されれば、建設業務の機能維持は難しく、ひいては社会インフラの維持にも影響が出かねません。
そのため、生産性や働き方の抜本的な改革が実現できる建設DXが注目されているのです。
インフラを管轄する国土交通省としても
- ICT技術の全面活用による建設の生産性向上を目的としたi-Construction(ICTの全面的な活用等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取組)の推進
- インフラ分野のDX推進本部を設置
- 小規模を除くすべての公共工事で、2023年までに原則BIM/CIMを適用(従来の2次元図面を用いた建設生産・管理プロセスを見直し、3次元モデルにさまざまな情報を結びつけ利活用していくこと)
などの施策を検討・実施し、建設DXを推進しようとしています。
建設DXは、官民を挙げて対応することが求められる重要な課題です。国内インフラを中長期的に維持するため、建設DXの推進による省人化や建設業務の効率化に向けたビジネスモデルの変革が求められています。
<参考>
インフラ分野のDX推進について|国土交通省
インフラ分野のDXアクションプラン|国土交通省
2.建設DXに取り組む4つのメリット
ここからは、建設DXを実現することでどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
建設業界は、
- 就業者数の減少(職人の高齢化・若手の減少)
- 長時間労働の常態化
- 生産性の低さ
- 危険の大きい作業がある
など、さまざまな課題があります。
とくに長時間労働の常態化について、2024年4月1日から「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制が建設業へも原則適用されるため、早急な対策を実施しなければなりません。
参考:厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」 [2022]
このような建設業界が抱えているさまざまな課題の解決に役立つと期待されているのが、建設DXです。
具体的には、建設DXの実現には
- 業務プロセスの効率化・生産性向上
- 人手不足の解消
- 作業員の安全確保
- 職人の技術継承への貢献
などの大きなメリットがあります。
建設DXに取り組むメリットを、DXの過程で導入するデジタルサービスがどのように課題解決へ役立つかとともに、詳しく解説します。
2-1.業務プロセスの効率化・生産性向上
建設業務を効率化できることは、建設DXに取り組む大きなメリットです。さまざまなデジタル技術を活用し、アナログな状態で行っている多くの業務プロセスを効率化できれば、生産性の向上に役立ちます。
たとえば、クラウドサービスなどの業務全体の情報を一元管理可能なシステムを活用すると、発注者側や事務所にいる社員と現場の作業員が、リアルタイムで情報を共有できます。施工対象の仕様変更や現場の状況などを関係者が迅速に把握できるため、情報を確認する手間や時間のロスなく効率的に作業に取り掛かれるでしょう。
また、3Dモデルで構造物を確認することで、平面的な図面よりもイメージしやすくなり、認識のずれを軽減できます。リモートでも正確に状況を把握しやすく、設計に関する打ち合わせでもより簡単に意思疎通が可能です。
多くの業務が効率化され、情報共有や意思疎通がよりスムーズになれば、工期も短縮できるとみられます。生産性が高まるため、社員の負担を減らしながら効率の良い建設業務を実現できるでしょう。
2-2.人手不足の解消
建設DXにより、各業務に少人数で対応できるようになれば、建設業界の人手不足解消が期待されます。
近年、多くの業界が人手不足に陥っていると言われており、なかでも建設業界の就業者数減少は深刻な問題です。国土交通省によると、建設業の就業者数は2020年時点で平均492万人となっており、ピークだった1997年の685万人と比較すると約28%も減少しています。
肉体的な負担が大きく、長時間労働の常態化がみられる建設業界の現状を考えれば、就業者数減少の早急な解決は期待できません。就業者数の減少ペースからみると、職人一人ひとりにかかる負担は、年々大きくなっていると言えるでしょう。
建設DXでデジタル技術を導入すると業務の省人化が可能となるため、少ない人数で同様の作業が可能となります。
例えば、一人の職人が重機の遠隔操作によって複数の現場に従事したり、事務所などの離れた場所から現場の施工状況や資材を確認したりできるため、少ない人数で多くの現場に対応できるのです。
デジタル技術の活用によって建設業務や作業にかかる人手を無理なく減らせるため、人手不足の解消が期待できます。作業現場への移動時間や作業の待機時間も省けるため、長時間労働の改善効果も見込めるでしょう。
2-3.作業員の安全確保
デジタル技術の活用によって危険性の高い作業を機械に委ね、作業員の安全を確保することも可能です。 建設業には高所での点検や災害復旧といった危険性の高い作業も多く存在することから、作業員の安全確保は非常に重要な課題です。そのような危険性の高い作業にドローンや遠隔操作できる建機などを活用することで、作業員に危険が及ぶことを防げます。
たとえば、高所を点検する際、ドローンのカメラで地上から確認する方法を導入すれば作業員が高所に昇らなくても点検できるため、転落事故の心配がありません。災害現場などの危ない場所で作業が必要となった場合にも、遠隔操作建機を使用することで離れた安全な場所から操作できます。
デジタル技術を効果的に活用した業務形態へ移行することで、作業員が事故や災害に巻き込まれる危険を冒すことなく安全に作業を遂行できるでしょう。
2-4.職人の技術継承へ貢献
建設業界では、若手の職人への技術継承も大きな課題のひとつです。例えば、AIを取り入れることによって、職人の熟練した技術を無理なく継承することも可能です。
建設業界でも、他の業界と同様に高齢化が進んでいます。さらには若手の就業者数も減っているため、時間をかけて技術を受け継ぎ育成する時間もありません。このままでは、職人の引退によって熟練した技術が失われてしまう危険もあるでしょう。
そのような中、職人が持つノウハウの継承に、例えばAIの学習機能を活用する方法が注目されています。
職人の熟練した技術をAIに学習させることにより、職人から直接指導を受ける機会を持たない若手であっても、同じ業務を実行できるようなシステムの開発・研究が進んでいます。ほかにも、操縦技術を学習したAI搭載建機による自動操縦、点検業務における異常の自動検出など、AIの活用範囲はさまざまに広がりを見せています。
3.建設DXで用いられるデジタル技術と活用例
ここからは、建設DXで用いられている主なデジタル技術について、具体的に解説します。
活用すべきデジタル技術は、建設DXの目的や企業が抱えている課題などによって異なりますが、本章では主要となる
- クラウドサービス
- AI
- ICT
- IoT
の4つの技術について、詳しく紹介します。
各技術の特徴だけでなく、建設DXでの活用例も挙げて説明するため、自社で導入する際の活用方法を想像しながらお読みください。
3-1.クラウドサービス
クラウドサービスは、ネットワーク経由でソフトウェアやサーバー環境を提供する技術です。インターネット環境があれば、場所や利用する端末を選ばずにアクセスできることが特徴です。そのため、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
現状、様々なクラウドサービスがありますが、建設業でも活用できるものは多くあります。
このようなクラウドサービスを活用すると、建設現場等の離れた場所にいる職人や企業間での情報共有が容易になるため、部材の仕様や施工の進捗確認などを、時間のロスなく即座に把握できます。
図面情報を紙やデータ送信でバラバラに共有している場合は、クラウドサービスの利用により情報の一元的な管理が可能となるため、高い導入効果が見込めるでしょう。
建設DXを実現するうえで、クラウドサービスの導入は非常に有用です。
3-2.AI
AIとは、「Artificial Intelligence(人工知能)」の略称です。人が行う知的な活動を人工的に再現する、高度なコンピュータープログラムのことを指します。
AIには学習機能があり、非常に優れた計算・分析機能を有することが特徴です。
AIの活用により、IoT技術などで収集した大量のデータを分析・学習し、それを基に様々な動作や判断を行うことが可能となります。例えば、大量の設計データをAIへ分析・学習させることにより、建設物の構造上の問題点などをスピーディに解析することや、建設現場の画像から詳細に進捗状況を分析することなども期待できるでしょう。
他にも、インフラなどの点検作業では、従来から職人が現場に赴き目視で点検を行うことが一般的でした。AIの活用により、職人の点検技術と画像データをAIに学習させることで、センサーでの計測やモニタリングによる点検を可能にする研究も行われています。
AI技術は近年飛躍的に進展しており、建設業界でのさらなる活用が期待されます。
3-3.ICT
ICTとは、情報通信技術のことを指す「Information and Communication Technology」の略称です。パソコンやスマホなどのデバイスを用いながら、人がネットワークを通じて情報をやり取りする技術を意味します。
建設現場では、さまざまな業務でICTの導入が進んでいます。
ドローンを用いた3次元測量や、3次元データを活用した施工計画の作成などが一例です。人の手をかけて行っていた作業の工数削減や、正確な情報把握が短時間で可能となるため、省人化や工期の短縮効果が期待できるでしょう。
建設におけるICTの活用は国土交通省も推進しており、業務への積極的な導入が求められています。
3-4.IoT
IoTは「Internet of Things」の略称です。IoTは「モノのインターネット」と表現されるように、物自体に通信技術を搭載し、情報交換できるようにする技術を指します。
身近なものでは、スマート家電とよばれるような音声や外出先から家電を操作することができる家電や、腕時計のように装着し、脈拍や体温などの情報を確認できる装置が有名です。
建設DXにおいては、IoT技術により、センサーを搭載した無人の建設機械による施工が可能となります。センサーで収集した現場データを遠隔地で確認しながら操作できるため、危険性の高い場所や災害現場などでの活躍が期待されます。ドローンを使った高所の点検作業なども可能です。
4.建設DXは段階的に取り組むことが大切
建設業界では、受注者側の希望を受けて毎回異なるものを生産するため、一足飛びには作業の標準化が難しいという特徴があります。
また、若手が減少し、従業員の高齢化が進んでいることもあり
「建設DXやデジタル技術を導入しても対応できない」
「自社に建設DXは必要ない」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、建設DXはできる部分からでも段階的に進めていくべきです。
建設業務の品質を確保しながら事業を継続するためには、業務効率化や作業員の安全確保、高齢化に向けた技術継承といった課題解決を先延ばしにすることはできません。
そのため、段階的にでも建設DXに取り組み、一つひとつの課題を解決しながら大きな変革につなげることが大切です。
国もさまざまな建設DX推進施策を行っています。建設業界全体がDXを進めることにより、自社の建設DXの遅れは、ビジネスの大きな機会損失に繋がる可能性があります。このように、建設DXに取り組まないこと自体のリスクも高く、少しずつでも継続して取り組むことが必要なのです。
「建設DXは段階的に取り組むべき」と言える理由
建設DXに取り組む際は、段階的に導入を進めることが非常に重要です。
DXに関する新たな取り組みを無理に推し進めてしまうと、自社の従業員や、プロジェクトに関わる周りの企業から理解を得られず、反発を招く恐れがあります。
建設業界は一般的に重層下請構造になっており、一つのプロジェクトに対して多くの企業が関わっています。自社のDXを一気に進めると、導入したデジタル技術に対応できない企業がいないとも限りません。
他にも、デジタル技術の導入には一定のコストがかかるため、一度に導入すると投資負担の大きくなる場合があることも注意点の一つです。
また、新たなデジタル技術を導入する際は、高齢の職人やデジタル機器の扱いに慣れていない従業員が使いこなせるよう研修する必要がありますが、多くの技術を一度に導入すると、従業員を育成する時間も十分に確保できない可能性があります。
このように、一気に建設DXを完了させようとするとさまざまな問題が発生することから、長期的な視点で建設DXを捉え、段階的にデジタル技術を導入して建設DXを進めることが大切です。
5.建設DXを実現するために専門家のサポートを最大限活用しよう
建設DXに取り組む際は、専門家のサポートを活用することがポイントです。
建設DXは、デジタル技術を導入することが目的ではありません。単純に導入しただけでは、建設DXによる事業全体の高度化・変革は困難です。
建設DXで重要となるのは、自社の目的や課題に合わせて適切な技術を組み合わせ、導入することです。デジタル技術や導入方法についての豊富な知見がある人材が社内にいない場合、社内で自社のニーズに合わせた適切なデジタル技術を判断し、導入することのハードルは高くなりがちです。
このような場合、専門家に相談しながら進めると、豊富な知識をもとに導入すべき技術を的確に判断してくれます。自社にマッチした建設DXに向けて、全体像をしっかりと描きながら導入を進められるため、スピード感のあるデジタル技術の導入を行えます。
そのため、建設DXの実現に向けた取り組みは自社単独で考えるのではなく、専門家のサポートを活用してください。建設業界の抱えている課題を理解し、最先端のデジタル技術を熟知した専門家に相談することによって、自社のニーズや課題に即した建設DXを実現できるはずです。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
6.まとめ
建設DXとは、建設業のDXを指し、デジタル技術を活用して、建設業務のさまざまな業務プロセスやビジネスモデルを変革することを指します。建設DXは国も力を入れて推進しており、建設業界の課題解決へ貢献することが期待されています。
建設DXに取り組む主なメリットには
- 業務プロセスの効率化・生産性向上
- 人手不足の解消
- 作業員の安全確保
- 職人の技術継承へ貢献
の4点が考えられます。
クラウドサービスやAI、ICT、IoTといったさまざまなデジタル技術を活用し、生産性の向上や作業員の負担軽減、職人の技術継承などがより快適に行えるような研究開発が進んでいる状況です。
建設DXに取り組むにあたっては、周囲の理解や協力を得ながら段階的に取り組みましょう。自社の建設DXの遅れは、ゆくゆくは大きなビジネスの機会損失につながる恐れもあるため、長期的な視点を持ちながら建設DXに継続して取り組むことが大切です。
また、建設DXに取り組む際は、専門家のサポートを活用することをおすすめします。豊富な知識をもつ専門家が、自社の目的や課題に合わせたDXの推進方法を的確にアドバイスしてくれます。
建設業界のトレンドに取り残されないよう、専門家のサポートを最大限活用しながら建設DXを実現しましょう。