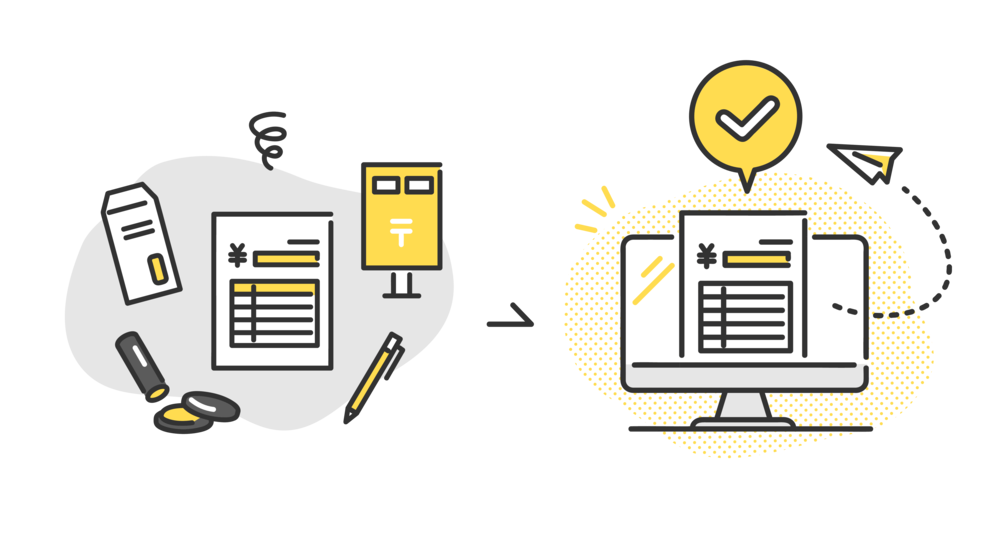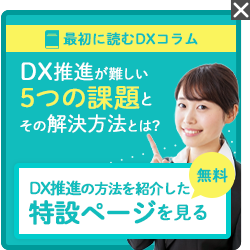更新日:
バックオフィスDXとは?重要視される理由や具体的な施策を解説
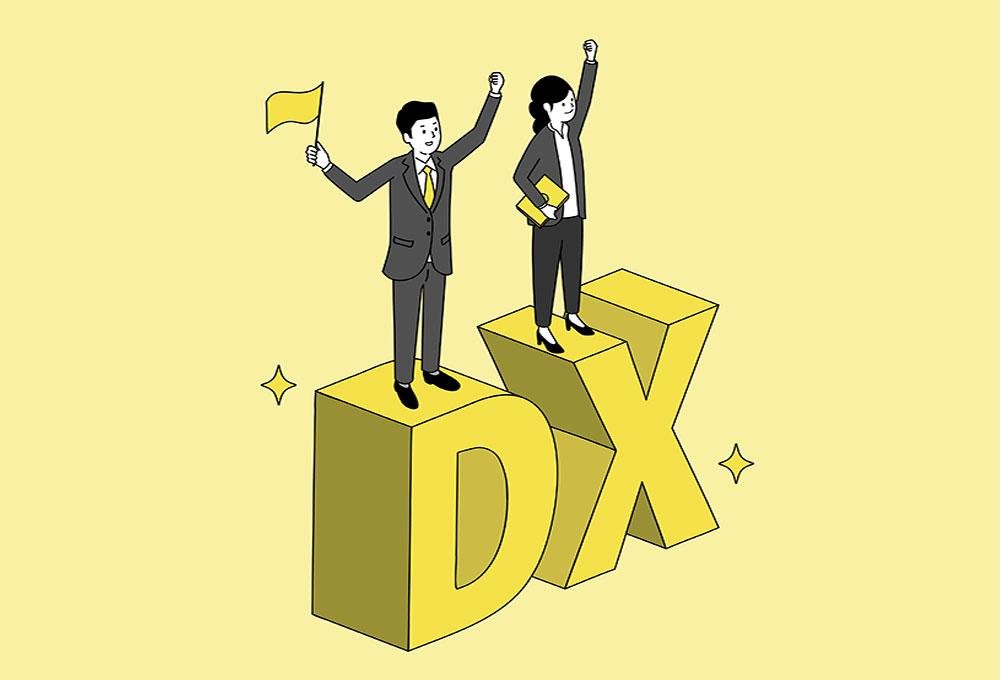
「そもそも、バックオフィス業務のDXってどんなもの?」
「バックオフィス業務のDXを具体的に進める方法は?」
昨今、耳にする機会が増えたDX(デジタルトランスフォーメーション)ですが、アナログな業務も多いバックオフィス業務では、どのように関係があるのか気になる方もいるかと思います。
バックオフィス業務のDX検討においては、そもそもなぜバックオフィス業務のDXが重要視され始めているのかといった背景や、各取り組みのメリット・注意点などを把握したうえで、段階的に進めることが大切です。
そこで本記事では、バックオフィス業務のDXを検討するうえで理解しておきたいポイントを、まとめて解説していきます。
この記事でわかること
- バックオフィスDXとは
- バックオフィスDXが重要視されている理由
- バックオフィスDXを推進する5つのメリット
- バックオフィスDXの具体的な施策
- バックオフィスDXを推進するときのポイント
この記事を最後まで読めばバックオフィスDXの重要性や具体的な方法を理解したうえで、自社の課題や目的に応じて段階的にDXを推進できるようになります。
バックオフィス業務はDXとの相性も良いため、どのように取り組むべきか参考にしてみてください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.バックオフィスDXとは
バックオフィスDXとは、一言で言うとバックオフィス業務のDXを推進することです。バックオフィス業務とは、「基本的に顧客と直接的な接点を持たない業務」を指します。例えば営業活動のように直接利益を生み出す活動はしませんが、会社運営に欠かせない後方支援を行う部署や職種が該当します。
バックオフィス業務には、下記のように経理や総務、人事などの部署で行われている業務が含まれます。
バックオフィスに含まれる主な部署・職種
- 経理
- 財務
- 総務
- 人事
- 労務 など
これらの部署・職種におけるバックオフィス業務は、属人化してしまっているケースが少なくない他、部署横断的な作業も多いため、手間や時間のかかる側面があります。
そこで、注目されているのがDXです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」を指します。
(引用)経済産業省「『DX推進指標』とそのガイダンス」[2019]
例えば、バックオフィス業務へ何らかのデジタルサービスを導入することにより、データの活用や業務効率化を進めることができれば、社員の業務時間や投資費用の捻出など、企業が新たな価値を創出するための基盤を整えることが可能です。
バックオフィス業務のDX推進は、企業がビジネスモデルの変革や競争優位性を高めるために、重要な役割を果たす可能性があるのです。
2.バックオフィスDXが重要視されている理由
昨今、バックオフィスDXが重要視されている理由としては、次の3点が挙げられます。
- 既存システムの老朽化
- 企業の人材不足
- 属人化しやすい業務
これらの3点は、バックオフィス業務のDXを積極的に検討するべきか悩んでいる場合はぜひ知っておきたいポイントなので、参考にしてみてください。
2-1.既存システムの老朽化
1点目に、バックオフィス業務で利用されてきた既存システムの老朽化が挙げられます。
バックオフィス業務は、企業の中でも、事業全体を円滑に運営するために非常に重要な役割を担っています。また、日常的に対応しなければならない業務も多いため、老朽化を感じていたとしても既存システムに頼りながら運営しているような場合もあるでしょう。経済産業省の「DXレポート」によれば、約8割の企業が「レガシーシステム(過去の技術や仕組みで構築されたシステム)」と抱えていると考えられています。
しかしながら、バックオフィス業務に老朽化したシステムが利用されている場合は、そのシステムに関して、今後充分なメンテナンスを実施できる人材が不足する可能性や、システム自体のサポートが終了してしまう可能性なども考えられます。その状態で使い続けるとセキュリティリスクが高まり、大きなトラブルにつながる懸念もあるでしょう。
企業全体がDXを実現し、ビジネスモデルの変革や競争優位性を高めるためには、事業運営の根幹を担うバックオフィス業務においても、レガシーシステムを使い続けるわけにはいかない状況にあります。
2-2.企業の人材不足
2点目に、企業の人材不足が挙げられます。生産年齢人口(15歳以上65歳未満)が減少する見通しであり、企業の人手不足感が高まるなか、特にバックオフィス業務には専門的な知識や経験が必要な業務が多く、バックオフィス業務を担う人材は、他部署との兼任や異動が難しいケースもあります。
人材不足のまま業務運営を継続すると、一人ひとりの社員の負担の大きい状態が続き、社員の離職や業務精度の低下に繋がる可能性があります。
そこで、バックオフィス業務におけるデジタルサービスの活用などにより、従来と比べて少ない人数で効率的に担当できるようになれば、人材不足をカバーできます。
2-3.属人化しやすい業務
一部のバックオフィス業務には、専門的な知識を要するために属人化しやすく、一人ひとりの社員の負担が大きいものがあります。例えば、「労務の書類作成はAさんしかできない」となった場合に、Aさんへ労務関係の業務が集中してしまうようなイメージです。このAさんが離職した場合や欠勤した場合には、Aさんが手掛ける業務自体の運営が難しくなり、結果的に会社運営へ影響を及ぼす可能性があります。
バックオフィス業務のフローを整理したうえで、他の社員も同じ業務が行えるようにDXを進めた場合には、属人化によるリスクを低減することが可能です。例えば、特定の業務に関するデータを一元管理し、どの社員でも閲覧・検索できるようにすれば、担当者が欠勤をしても必要な情報を活用できます。
このように、属人化した業務によるデメリットを低減できるところも、バックオフィスDXが重要視されている理由の一つです。
3.バックオフィスDXを推進する5つのメリット
バックオフィスDXを推進すると、例えば、下記のような5つのメリットが得られると考えられます。
- 業務効率化につながる
- 多様な働き方に対応できるようになる
- 長期的な目線でのコスト削減につながる
- バックオフィス業務の精度の向上
- BCP対策ができる
自社のバックオフィス業務のDXを推進した場合にどのようなメリットが見込めるか、想像しながらチェックしてみましょう。
3-1.多様な働き方に対応できるようになる
従来のバックオフィス業務では、「出社しないと経費処理の承認ができない」「オフィスでなければ勤怠記録が確認できない」などといった課題がありました。
こうした中、バックオフィス業務のDXが実現できれば、多様な働き方に対応できるようになります。例えば、経費処理が可能なクラウド型のサービス内で、申請された経費に関する承認ができるようになれば、わざわざ出社をして承認を行う必要は無くなります。
また、バックオフィス業務を依頼する側の社員も、システム経由で各業務を依頼することができれば、社員の誰がどこで業務をしていたとしても、滞りなく業務を進められるようになります。
企業が多様な働き方へ対応できるようになることは、採用活動にもメリットがあります。既存のバックオフィス業務について、社員の自宅をはじめとしたオフィス以外の環境でも対応できるようになれば、それを求人募集時のアピールポイントとすることも可能です。
また、バックオフィス業務に携わる社員が出社をしなければならない場合は、会社へ通勤できる範囲の人材のみが求人対象となりますが、そのような制約を設けることなく採用を行うことも可能です。優秀な人材の確保や人材不足の解消へ繋がる可能性があることも、利点だと言えるでしょう。
3-2.長期的なコスト削減につながる
バックオフィス業務のDXを進めるにあたって、企業の目的に応じたデジタルサービスの導入などにより、サービス導入時にはまとまったコストがかかる可能性はあります。しかし、長期的にみれば、下記のようなコストを削減可能です。
- 老朽化した既存システムのメンテナンスや管理・運用費用
- 紙代や印刷代、郵送費など、アナログな業務に伴う費用
- 非効率な作業に伴い、余分に発生している人件費
このように、バックオフィスDXの推進においては、備品購入費や保守管理費、人件費などさまざまな費用が削減できる可能性があるため、長期的に会社の事業運営に対しても大きなメリットをもたらすでしょう。
3-3.業務精度を向上させることができる
「2-3.属人化しやすい業務 」でも解説したように、従来のバックオフィス業務の精度は、担当社員個人のスキルや経験に依存しやすい側面がありました。特に、書類の作成過程などで手作業が伴うことの多い場合は、人的なミスの発生がどうしても課題になりがちです。
バックオフィスのDXに当たっては、バックオフィス業務におけるタスク管理機能や自動チェック機能などを備えたデジタルサービスの導入も一つの方法です。例えば、経費精算や給与計算を自動化することができれば、人的な計算ミスが起こる可能性を低減できます。他にも、契約書などの書類の記入項目を自動でチェックすることができれば、未然に記入漏れを防ぐことも可能です。
属人化していた業務へ必要に応じてデジタル技術やサービスを活用することで、バックオフィス業務の精度を向上できるのです。
3-4.BCP対策ができる
BCP(Business Continuity Plan)とは、事業継続計画のことです。自然災害やテロ、感染症の流行など、何らかの緊急事態が起きた際に、早期に緊急事態から復旧し、事業を継続できる対策や方法をまとめておくことを指します。
バックオフィスDXでは業務効率化とともに、下記のようなBCP対策を進めることができます。
| 資料や書類の一元管理やバックアップ | 会社へ物理的な緊急事態があった際に、機密情報や個人データを失わない備えができる |
|---|---|
| 遠隔操作への対応 | 社員が出社を行えない場合も、社内の情報やデータにアクセスできる |
| 在宅勤務のルール整備 | 緊急時に、必要に応じて社員を在宅勤務に切り替えさせる基盤が整っている |
| 安否確認システムの導入 | 緊急時に、社員の安否確認をスムーズに行える |
緊急事態にバックオフィス業務が滞ってしまった場合、例えば支払い処理がストップしてしまうなどで、一時的に事業運営を継続できない状況になる可能性があります。
バックオフィス業務のDXと連動してBCP対策を検討することが出来ていれば、緊急事態が起きた際も、冷静に対応することができるでしょう。
ここまで解説してきたように、バックオフィスDXの推進は、バックオフィス業務が抱える課題を解決し、多様な働き方への対応や業務精度の向上といった付加価値を創出します。
次の章では、バックオフィスDXの具体的な施策を解説していきます。DX推進に向けて、具体的にはどのようなことを実施したらいいのか、参考にしてみてください。
4.バックオフィスDXの具体的な施策
バックオフィスDXを推進するための具体的な施策としては、下記の5つがあります。
| 業務のペーパーレス化推進 | 紙面の書類を電子化し、紙面を使用しない業務フローへと移行する |
|---|---|
| 電子印鑑・電子署名の活用 | 印影データや電子署名を活用して、電子化した書類の真正性を確保する |
| RPAの活用 | ロボットを活用して業務を自動化・代替する |
| OCRの活用 | 紙面や画像に書かれた文字を認識してパソコンで利用できるテキストデータへ変換する |
| チャットボットやFAQの導入 | 社内向けチャットボットやFAQを導入し、業務に関する疑問を社員自らで解決できる体制を整備する |
すべてを導入するのではなく、現在の課題やDX化の進捗状況に応じて検討することが可能です。どのような施策を検討できるのか、参考にしてみてください。
4-1.業務のペーパーレス化推進
ペーパーレス化とは、今まで紙面で作成・管理していた書類を電子化しながら、その書類が関わる業務フロー全体を、紙面を使用しない運用方法へ変えることを指します。
バックオフィス業務では、契約書や請求書、納品書などさまざまな書類を作成・発行し、授受する機会や、長期間保存が必要な場合も多いため、ペーパーレス化によるメリットを享受しやすいと考えられます。
推進方法
例えば、請求書や契約書、納品書などの定期的に発行・授受する紙の書類を単純に電子化するには、書類を複合機やスマホによるスキャンなどによりPDF化する方法があります。
さらに、電子化した書類を用いて、バックオフィス業務に関する業務フロー全体のペーパーレス化を推進していくためには、専用のデジタルサービスを導入する方法も検討してみてください。具体的には、経費精算業務へクラウド型の経費精算サービスの導入を検討した場合、営業部での経費精算申請から経理部での精算処理までをシステム上で完結させることが可能になります。
メリット
ペーパーレス化の大きなメリットは、コスト削減と意思決定のスピード向上です。請求書や納品書、契約書など、日常的に発生する書類の利用機会を少なくできれば、結果的に紙面代や印刷代、郵送費などを削減することへ繋がります。多くの書類をペーパーレス化することほど、費用削減効果は大きくなるでしょう。
また、従来のバックオフィス業務では、契約書や請求書などについて、紙面に印刷された内容を担当者が目視で確認するフローを設けていることも多くなっていました。このような業務の際、担当者間で紙面の物理的な移動が必要になると、各書類への対応に時間を要することになります。
業務フロー全体のペーパーレス化を推進することにより、メールやシステムから書類を簡単に確認し、場所や時間を問わず各書類に係る対応を実行できるようになります。その結果、各業務の意思決定にかかる時間を短縮し、スピーディに業務を進めることができるようになるでしょう。
注意点
全社的にペーパーレスを推進するには、その方法に関し、社員へ十分な周知が必要なだけでなく、紙面で書類を授受している取引先や関連企業の理解を得ることも必要です。例えば、自社で発行している請求書について、電子化へ移行を検討した際に、請求書の送付先企業からも電子化への移行に関する理解を得ておかなければ、なかなか進めることはできません。事前に請求書電子化の目的や開始日などを送付先企業へアナウンスし、承諾を得てから進めるようにすれば、トラブルを回避できます。
4-2.電子印鑑・電子署名の活用
電子印鑑とは印影をデータ化したものです。電子印鑑・電子署名システムはそれぞれ、電子化された書類(請求書や契約書、給与明細書など)へ信頼性を持たせるために利用できます。
例えば、電子印鑑には、主に下記の種類があります。
| 印影をデータ化したもの |
|
|---|---|
| 印影データに識別情報が 付与されているもの |
|
また、電子署名とは電子化された書類が正式なものであることや改ざんされていないことなどを「電子証明書」を用いて証明するものを指します。
推進方法
印影をデータ化するだけであれば、印影をスキャンして画像化する方法や、無料のアプリケーションの利用などにより簡単に作成できます。印影データに識別情報が付与されているものを導入したい場合は、専用の有料サービスなどを利用する必要があります。一定のコストがかかってしまう可能性もありますが、印影をデータ化したものと比べて、一定のセキュリティが確保できます。
電子署名については、「電子署名」という単語だけ聞くと難しいイメージがあるかもしれませんが、コンピューターやデジタル技術などの専門知識が無くとも簡単に利用可能な、電子署名機能を持つ電子契約サービスなどを利用する方法が考えられます。
メリット
紙面の書類では、担当者が押印依頼を行う社員や取引先の元へ書類を届け、内容確認後に押印をもらい、再度担当者の手元へ書類を返却してもらうといった業務フローとなっていました。電子印鑑や電子署名システムを導入すれば、電子化された書類へも押印や締結の証明ができるため、書類に関する手間のかかるやり取りを大幅に削減できます。複数人の承認印が必要な書類でも、スムーズに対応を進めることができるでしょう。
また、インクで押印された印影や署名と異なり経年劣化がないため、書面の汚損や日焼けなどによる信頼性の低下がない点もメリットです。
注意点
単純な画像データを用いた電子印鑑は、簡単に複製されてしまう可能性があります。複製した印影を第三者が押印しても、時刻情報や改ざん情報が確認できなければ、その証明はできません。特に押印や締結したという事実へ確実性・信頼性が求められる書類については、識別情報が付与されている電子印鑑や電子署名を導入する必要があるでしょう。
4-3.RPAの活用
RPA(Robotic Process Automation)とは、これまで人間が対応してきた作業を、デジタル技術(ソフトウェアロボット)を活用して代替・自動化する仕組みのことです。
RPAは、複雑な作業の対応や個別判断の必要な対応は難しいため、一定のルールに従い同じことを繰り返し行う業務や、判断基準が明確な業務に適しています。
例えばバックオフィス業務では、経費の計算や仕分け入力といった、単純なデータ入力・転記作業などへの活用が想定されます。計算方法や抽出するデータの条件を設定することにより、大量のデータであっても自動で作業を行うことが可能です。
推進方法
RPAによる自動化が適した業務は、異例な対応が少ない定例作業(ルーティン作業)です。RPAは定例作業を業務フローに落とし込み、条件設定した通りに稼働するため、複雑な業務フローでは開発もメンテナンスも大変になってしまいます。適切な業務を対象としてRPAツールの導入を検討しましょう。
ただし、RPAツールは導入して終わりではなく、RPAへ指示した作業内容の見直しを定期的に実施することにより、作業精度の確認や向上を図ることが重要です。
メリット
RPAでは、大量のデータ入力や毎月発生する計算などの自動化が可能なため、社員の業務負担を大きく減らせる点がメリットになります。計算や入力スピードも、人間と比べて速いことが多いので、短時間で効率よく業務を進めることが可能です。
また、単純な作業や計算業務などが社員の手から離れることで、今まで取り組めなかった新たな業務を行う時間を創出できます。
注意点
RPA自体は、判断能力を持ち合わせていません。あくまでも事前に指示されたルールに沿ってしか作業ができないため、人間が作業指示を間違えると、大きなミスに繋がることがあります。
例えば「ExcelのE列とD列を足し算する」という指示を「ExcelのE列とF列を足し算する」と誤って伝えてしまうと、想定とは異なる計算結果が算出されてしまいます。そのため、作業指示が正確に、またより効率の良い条件設定で行えているかどうかは、定期的に確認しましょう。
4-4.OCRの活用
OCR(Optical Character Recognition/Reader)とは光学文字認識という意味で、紙面や画像データに記載されている文字を認識し、パソコンで利用できるテキストデータへ変換する技術のことです。
従来は、手書きのデータや一度画像化したデータは、手作業でシステムに打ち込むなどしてテキストデータ化する必要がありました。OCRを導入すると、カメラやスキャナーでデータを取り込みレシートや手書きの領収書などを簡単にテキストデータ化できます。
推進方法
OCRを活用するためは、対象とする書類やデータ変換の目的などに応じた適切なシステムを導入することが一つの方法です。インターネット上で入手可能な無料のソフトウェアもありますが、基本的には文字認識精度や機能を追求するほど導入コストが高くなる場合もあるため、費用対効果を念頭に置いて検討することが大切です。最近は、OCRとAIを組み合わせて、文字認識精度を向上させる技術も登場しています。
メリット
OCRは、手入力の手間や人的なミスを減らせるところがメリットです。例えばこれまでは、「テキストデータはないが、過去のこの資料をブラッシュアップして欲しい」と言われた場合には、過去の資料を見ながら手入力でもう一度資料を作成するしか方法がありませんでした。
OCRを導入すれば、カメラやスキャナーで取り込むだけで文字をテキストデータ化できるため、手入力の手間が省けます。それだけでなく、手入力でのミスが減らせるため、バックオフィス業務の精度を高めることが可能です。
注意点
OCRはシステムにより、文字認識精度や対応している出力方式などが異なります。精度の低いシステムを導入すると、小さな文字や読みにくい文字は認識できない可能性があります。また、さまざまなサイズの伝票や書類を扱っている場合は、その伝票や書類がシステムの対応範囲か、事前に確認を行うようにしましょう。
4-5.チャットボットやFAQの導入
バックオフィス業務では、社員からの問い合わせが業務の妨げや負担となることがあります。バックオフィス業務に関連して発生する作業への疑問について、社員の自己解決率を向上させるために、社内向けのFAQやチャットボットを導入するのも一つの方法です。
| FAQ |
|
|---|---|
| チャットボット |
|
FAQは、よくある質問と回答の組み合わせのことです。バックオフィス業務では、「経費精算の方法」など、複数の現場社員から同じ質問を受け、同じように回答しなければならない場面も多く想定されます。
チャットボットは、チャットを用いた自動会話プログラムのことです。社員からの問い合わせに、コンピューターが会話形式で応対するところが特徴です。例えば、「請求書の発行方法が知りたい」と質問があったときに、あらかじめ設定しておいた回答を表示することで、社員は疑問を自分で解決することが可能です。
推進方法
FAQの場合は、よくある質問と回答を洗い出したうえで、社内のポータルサイト内に「よくある質問集」を開設し、FAQ自体を掲載する方法などが検討できます。 チャットボットの場合は、チャットボットツールを導入して、質問者から想定されるよくある質問と回答を事前に設定することにより、回答作業をコンピューターで代替することが可能です。
メリット
FAQサイトやチャットボットツールは、バックオフィス業務との連携が必要な作業に対しての現場社員の疑問を、現場社員が自分で解決できるような体制を整備することにより、バックオフィス業務担当者への問い合わせ件数や回答時間を削減できる点がメリットです。
例えば、バックオフィス業務のフローについて全く知識の無い新入社員に対して、社内のFAQサイトやチャットボットツールをあらかじめ紹介することなども有用でしょう。
注意点
FAQサイトやチャットボットツールは、立上げまでにやや手間がかかります。どちらも社員から多く受けている質問を収集して、質問を体系化したうえで回答を纏めて準備しておく必要があります。
回答精度を高めるためにも、事前の情報収集は必要不可欠です。
5.バックオフィスDXを推進する際のポイント
最後に、バックオフィスDXを推進する際に知っておきたい、2つのポイントをご紹介します。
- デジタルサービスの導入は手段であり目的ではない
- 中長期的な視点で計画的に取り組む
バックオフィスDXを成功させるためにも理解しておきたいポイントなので、事前にチェックしておきましょう。
5-1.デジタルサービスの導入は手段であり目的ではない
バックオフィスDXに取り組む中で、デジタルサービスの導入を検討することがあるかと思いますが、デジタルサービスの導入はあくまでも手段です。最終的には各施策を、DX=競合他社と競争上の優位性を確立できるようなビジネスモデルの変革へ繋げることが欠かせません。
例えば下記のように、バックオフィスDXの先にあるゴールを明確にすることが必要です。
- バックオフィス業務のDXを推進することで創出できた時間を活用し、新たなサービスを検討する
- バックオフィス業務のDXを推進し働きやすい環境を構築することで、社員のエンゲージメントの高い会社を目指す
バックオフィス業務にデジタルサービスを導入し、一定の業務効率化を図れたことで目標達成とするのではなく、DXの目的を意識して各施策を検討するようにしましょう。
5-2.中長期的な視点で計画的に取り組む
バックオフィス業務のDXは、すぐに実現するものではありません。どの施策も、施策の取り組み背景と目的に関して、社員や周囲の理解が必要なほか、デジタルサービスは計画的・段階的な導入が必要だからです。
例えば、請求書の電子化は、明日から急に始められるものではありません。取引先に請求書を電子化意向である旨の連絡を行うことや、電子化に向けて導入するデジタルサービスの検討など、導入までに行うべきことは沢山あります。また、デジタルサービス導入後は、サービスの運用方法について、社員のサポートを行うなどして社内に浸透させる取り組みも欠かせません。したがって、短期間で急激にDXを推進することは非常に難しいでしょう。
そのため、バックオフィスDXについては、あらかじめ中長期的な視点で計画を立てて、少しずつ社内に浸透させていくことが大切です。具体的にどのバックオフィス業務からDXを目指し、どのようなスケジュールで進めていくのかを明確にしておくと良いでしょう。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
6.まとめ
いかがでしたか?最後まで読み、バックオフィスDXの必要性やメリット、具体的な施策が理解できたかと思います。この記事の要点は、下記のとおりです。
- バックオフィスDXとは経理・総務・人事などのバックオフィス業務のDXを推進すること
- バックオフィスDXは、バックオフィス業務に関する既存システムの老朽化や人材不足、業務自体が属人しやすい点などから注目されている
- バックオフィスDXには、多様な働き方への対応や業務精度の向上など、さまざまなメリットがある
- バックオフィスDXでは業務のペーパーレス化推進や電子印鑑・電子署名の活用、RPAやOCRの活用、社内用のチャットボットやFAQの導入など、業務課題や目的に応じた施策が検討可能
- バックオフィスDXへは、中長期的な視点で計画的に取り組むことが欠かせない
バックオフィス業務は属人化しやすいうえ、業務内容や今の取り組み方法によっては、一人ひとりの社員の業務負担が大きい側面があります。バックオフィスDXを推進することで、社員が働きやすい環境の構築や業務効率化が実現できるでしょう。その結果、新たな価値の創出や他社との差別化に繋がるはずです。
ぜひこの記事を参考に、自社の課題や目的に応じて、バックオフィス業務のDXを検討してみてください。