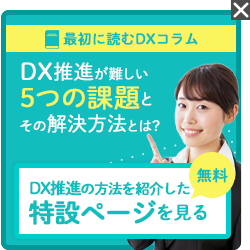更新日:
「脱ハンコ」とは?企業でスムーズに実現するために必要な知識や方法を解説!

昨今、印鑑による押印作業を無くす、「脱ハンコ」の流れが加速しています。行政手続きの書類から押印作業を無くそうとする動きと並行して、現在では、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の第一歩として「脱ハンコ」を進める企業も多くみられています。
しかしながら、「自社でも『脱ハンコ』の動きに取り組んだ方が良いのだろうか?」「『脱ハンコ』を実現したくても、反対している社員がいる」など、なかなか積極的になれない企業担当者の方もいるかもしれません。また、「せっかくテレワークを導入したにもかかわらず、押印作業のために出社しなければならない」といった状況は、業務効率も社員のモチベーションも下げてしまいかねません。
この記事では、「『脱ハンコ』を推進すべきかどうか」判断したい方へ向けて、「脱ハンコ」を進めるうえで注意すべきポイント、「脱ハンコ」を実現するための具体的な外部サービスや失敗しない進め方などを紹介していきます。
ぜひ記事を最後までお読みいただき、社内文書や社外文書の「脱ハンコ」を推進するきっかけにしてみてください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.「脱ハンコ」とは?
「脱ハンコ」を自社で進めるべきかどうかを検討する前に、まずは「『脱ハンコ』とは何か?」という基礎的な部分をしっかり理解していきましょう。
1-1.「脱ハンコ」とは押印文化から脱却すること
「脱ハンコ」については、2020年9月25日に、菅内閣の河野太郎大臣が「脱ハンコ」への動きを表明して話題となりました。河野太郎大臣が打ち出したこの「脱ハンコ」は、ハンコ(印鑑)自体を廃止する、というものではなく、あくまで「行政手続きにおける押印作業を廃止していく」というものでした。
その後、2021年9月にはデジタル庁が発足し、今では行政手続きに限らず、企業において押印作業から脱却する動きのことも、「脱ハンコ」と呼ぶことが多くみられるようになっています。
1-2.「脱ハンコ」に含まれる取り組み内容
「脱ハンコ」の流れには、大きく分けて2つの動きがみられ、「①紙の書類にハンコ(印鑑)を押さないことを許可する流れ」と「②紙とハンコを用いて書類を授受(契約・承認等)する形ではなく、電子的な授受へ移行する流れ」があります。最近では、後者の動きの方がメインで「脱ハンコ」と呼ばれることが増えています。
ここでは、企業で脱ハンコを推進する場合に、想定される具体的な取り組みを分類してみました。
| 対象書類 | 「脱ハンコ」の具体的な取り組み内容例 |
|---|---|
| 社内文書 |
|
| 社外文書 |
|
| 行政向け文書 |
|
このように、「脱ハンコ」に向けた取り組み例には様々なものが考えられますが、「脱ハンコ」へ向けて、具体的にどの文書からどのような方法で着手していくかについては、各企業で検討する必要があります。
2.脱ハンコを企業が推進する6つのメリット
ここからは、企業が「脱ハンコ」を推進することで得られる具体的なメリットについて解説していきます。
企業が「脱ハンコ」を進める具体的なメリット
- テレワーク等の柔軟な働き方が可能になる
- 契約や承認等にかかる時間を短縮できる
- 契約や承認等の進捗状況を管理しやすい
- さまざまなコストを削減できる(切手代・人件費など)
- 書類の改ざん・紛失リスクを低減できる
- 書類の管理・検索が容易になる
2-1.テレワーク等の柔軟な働き方が可能になる
企業で取り扱う書類について、契約や承認時にハンコを押すルールを設けていると、「ハンコを押す必要のある書類については、その書類の押印作業ために出社しなければならない」という非効率的な出社が発生します。また、外出している社員の押印が必要な場合にも、その社員の帰社まで押印作業が滞ってしまう可能性があります。
脱ハンコを推進して電子的に契約や承認が行えるようになれば、会社に来なくても当該手続きを進めることができるため、テレワークや営業先との直行直帰など、柔軟な働き方が可能になるでしょう。
2-2.契約や承認等にかかる時間を短縮できる
企業間の契約や社内文書の承認等を、押印作業無く電子上で行えるようにすることで、契約や承認等にかかる時間を短縮できるメリットもあります。
例えば、紙面で取引先との契約を行う場合、用意した契約書を印刷して相手先へ郵送し、相手先の担当者に捺印してもらい、その契約書をまた返送してもらう必要があります。それら時間を考慮すると、契約が完了するまでに少なくとも数日はかかってしまうでしょう。
このような場合には、「脱ハンコ」を推進して電子契約へ変更すれば、電子契約書を送信してすぐに契約を完了させることも可能になります。契約にかかる時間を大幅に短縮でき、スムーズに契約を進めることができるようになるのです。
2-3.契約や承認等の進捗状況を管理しやすい
紙面の書類によって契約や承認等を進める場合、「今、書類がどこにあるのか」「どの担当者の手元で作業が止まっているのか」などを把握しにくいというデメリットがあります。一方「脱ハンコ」、すなわち書類を電子化し、これらの契約締結や承認作業を電子的に行うようにできれば、社員が進捗状況をリアルタイムで確認可能になります。
例えば電子契約サービスの「SMBCクラウドサイン」をみると、契約書の承認者が複数人いる場合に、どの承認者までの承認が済んでいるのかというステータスを、Web上で確認することができます。
2-4.さまざまなコストを削減できる(切手代・人件費など)
「脱ハンコ化」を進めることで、さまざまなコストを削減できるメリットもあります。
取り組み内容にもよりますが、例えば以下のようなコストを削減可能です。
- 契約書や確認資料を印刷する費用
- ハンコ(印章)そのものの費用や維持費
- 契約書に貼付する印紙代
- 契約書を郵送するための切手代などの費用
- 書類を保管するスペースにかかる費用
また、書類の郵送作業や保管作業等にかかっていた業務時間分の人件費を削減することもできるでしょう。
2-5.書類の改ざん・紛失リスクを低減できる
紙面の書類の場合、書類を改ざんされるリスクや紛失してしまうリスクはどうしても拭えません。
「脱ハンコ」を進める過程で、適正な方法で文書の電子化を行えば、電子署名などが付与された改ざんできない書類として保存することができます。また、電子書類であれば紛失する恐れもなく、管理しやすいというメリットもあります。
2-6.書類の管理・検索が容易になる
「脱ハンコ」に伴い、押印済の書類を電子化することで、過去の押印済書類の管理や検索も容易になります。
紙面の書類では、その書類を保管するためのスペースが必要になることに加え、一定期間経過後に書類を探す場合には社員の手間が発生する可能性もあります。押印済の書類を電子化する、あるいは最初から電子上で電子署名等の対応を行うことにより、保管するための部屋や棚を用意する必要は無くなるうえ、過去の書類をキーワードなどで容易に検索できるようになります。結果的に業務を効率化することも可能でしょう。
このように、「脱ハンコ」にはさまざまなメリットがあります。「脱ハンコ」を進めることで業務効率化を図り、企業の生産性向上につなげることができるのです。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し競争力のある企業になるためにも、ぜひ「脱ハンコ」を推進していくことをおすすめします。
3.「脱ハンコ」を進める上で注意すべきポイント
前章では、「脱ハンコ」を実現することでどのようなメリットがあるかを具体的に解説しました。さまざまなメリットが見込まれるため、「我が社でも『脱ハンコ』を推進したい」と感じた方も多いのではないでしょうか。
ここからは、「脱ハンコ」を進めるうえで注意すべきポイントについても紹介していきます。「脱ハンコ」の良い部分だけでなく、注意すべきポイントも知っておくことによって、「脱ハンコ」を着実に進めることができるようになるはずです。
企業が「脱ハンコ」を進める上で注意すべきポイント
- 社内で「脱ハンコ」に向けた取り組みを推進するうえで、一定の労力やコストがかかる
- 取引先や顧客が「脱ハンコ」に消極的な場合がある
それぞれについて詳しく解説していきます。
3-1.社内で「脱ハンコ」に向けた取り組みを推進するうえで、一定の労力やコストがかかる
「脱ハンコ」を実現するためには、押印作業を行っていた契約書について電子契約サービスを導入したり、社内文書の決裁が行えるワークフローシステムを導入するために、一定のコストがかかります。
※具体的なサービスについては、「4.脱ハンコを実現するための手段(社内文書・社外文書)」で詳しく解説しています。
また、どのサービスを導入するのかを決めた後は、一定の社内調整が必要となる場合もあります。ハンコ文化に慣れ親しんできた社員の中には、「脱ハンコ」の取り組みに抵抗感を感じる社員がいるかもしれません。そのような社員からも取り組みに関する理解を得るなど、「脱ハンコ」に向けた動きを関係者全体へ浸透させるための労力がかかる可能性があります。
ただし、新しい取り組みを行うにあたっては、往々にして一定の労力やコストがかかります。「脱ハンコ」を推進することによって享受できそうなメリットが、初期の労力や投資コストを上回る可能性が高いと判断できそうな場合は、「脱ハンコ」を前向きに検討していきましょう。
3-2.取引先や顧客が「脱ハンコ」に消極的な場合がある
社内での承認や確認文書については、自社内での努力により「脱ハンコ」を実現できます。しかし、契約書等、取引先や顧客などが関係する文書での「脱ハンコ」を実現するためには、相手方の協力が不可欠となります。
社内で「脱ハンコ」を実現したとしても、取引先や顧客が「脱ハンコ」に消極的な場合、対外文書に関する押印作業の削減は思うように進まないことがあります。例えば、取引先へ電子契約を依頼した際に、取引先から「我が社では紙面の契約書によるやりとりしか認められていない」と断られてしまうような状況が考えられます。
「脱ハンコ」を社内だけでもなく社外とも進めていく場合には、取引先から事前に、自社の「脱ハンコ」に向けた取り組みに対する理解や協力を確認しておくと安心です。
4.脱ハンコを実現するための手段(社内文書・社外文書)
ここからは、「脱ハンコ」を実現するための具体的な手段について解説していきます。
「脱ハンコ」を実現するためには、外部事業者が提供するデジタルツールの活用が有効です。法的効力のある電子署名の要件を満たすようなシステムを自社で用意することは難しく、「脱ハンコ」を実現するために有用なデジタルツールは既に世の中に多く登場しているため、ぜひそのようなデジタルツールを活用していきましょう。
以下では、社内文書・社外文書の2つに分けて、「脱ハンコ」を実現するためのデジタルツールやシステムについて説明していきます。
4-1.社内文書(社内文書の承認・回覧・決裁など)
社内文書の「脱ハンコ」を実現するためのデジタルツールやシステムには、以下のようなものが挙げられます。
| ワークフローシステム | さまざまな社内申請を電子化し、回覧・承認できるシステム →稟議書の決裁、回覧文書の確認、報告書、各種の申請書の確認などにおける「脱ハンコ」を実現できる |
|---|---|
| チャットツール | 電子化した文書を回覧(共有)可能なシステム →簡単な報告や文書の確認、申請の承認などを「脱ハンコ」化できる |
なお、今までハンコを押していた全ての書類について「脱ハンコ」を目指すのではなく、「本当にその書類には押印や電子署名が必要なのか?」という視点を取り入れることも重要です。例えば、回覧文書を閲覧した証として取り敢えずハンコを押していたようなケースでは、個々人の電子署名が本当に必要なのか、単に文書を共有して終わりでも良いのではないかなどを検討しましょう。
4-2.社外文書(契約書・見積書・請求書などの授受、締結)
「脱ハンコ」を検討し得る社外文書には、契約書・見積書・請求書などが挙げられます。これらの「脱ハンコ」を実現するためのデジタルツールやシステムには、以下のようなものが挙げられます。
| 電子契約システム | 電子ファイル(PDF形式)の契約書を作成したうえで、インターネット上で契約先へ送付し、電子署名やタイムスタンプを付与することにより契約締結できるシステム →社外の取引先や顧客との契約を、「脱ハンコ」化できる |
|---|---|
| Web帳票発行システム | さまざまな帳票を電子ファイルで作成し、インターネット上で送付できるシステム →請求書や納品書、支払明細、領収書などを「脱ハンコ」化できる |
| Web請求書システム (クラウド請求書ソフト) | 請求書を電子ファイルで作成し、インターネット上で請求先へ送付できるシステム →取引先へ発行する請求書を「脱ハンコ」化できる(見積書を発行できるシステムもあり) |
社外文書の「脱ハンコ」化を行う場合には、まずどの文書を対象にしたいかを検討しましょう。文書の授受・締結にあたってのコスト(印刷費や郵送費等の費用や、時間的なコスト)が多くかかっているものから、優先度高く対応していくことも選択肢の一つです。
また、社外文書の「脱ハンコ」化を検討する際にも、社内文書と同様に、「その文書への押印や電子署名が本当に必要とされているのか」について、各種法令も参考にしながらしっかりと検討することが重要です。一部、書面での作成が義務付けられている契約書もあるので注意しましょう。
5.脱ハンコをスムーズに進める4ステップ
「脱ハンコ」を実現するための具体的なデジタルツールやシステムなどが分かったところで、スムーズに「脱ハンコ」を進めていくためのステップを紹介していきます。
「脱ハンコ」をスムーズに進める4ステップ
- 「脱ハンコ」の範囲(どの書類を対象とするか)を決める
- 「脱ハンコ」を実現する外部サービスを選定する
- 社内規程の変更を行う
- 「脱ハンコ」に向けた取り組みを社内外へ周知する
5-1.「脱ハンコ」の範囲(どの書類を対象とするか)を決める
ひとくちに「脱ハンコ」と言っても、紙面の書類への押印を単純になくすのか、書類を電子化しハンコの代わりに電子署名を適用するのか、対応方法が異なります。
どの文書を「脱ハンコ」化するかによって、適切な対応方法が変わるので、まずは「脱ハンコ」の対象とする書類の範囲をしっかり決めましょう。
5-2.「脱ハンコ」を実現する外部サービスを選定する
ステップ1で「脱ハンコ」の範囲(「脱ハンコ」を行う書類の対象)を決めたら、その範囲・対象の「脱ハンコ」を実現可能な、外部事業者が提供するデジタルツールやシステムを選定していきましょう。
外部事業者が提供するデジタルツールやシステムを選定する際には、無料トライアルなども利用して実際にツールを使う立場の社員の声も聞きながら、社員が無理なく利用できるようなシステムを選ぶことをおすすめします。また、既存のシステムとの連携性や、社員向けマニュアルの整備状況等もチェックしておくと良いでしょう。
どのツールを導入すれば良いか迷われた際は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
5-3.社内規程の変更を行う
「脱ハンコ」を行うためのデジタルツールの導入に伴って、今までの社内規程の変更が必要になることがあります。
例えば、これまで「契約書は押印のうえ保管する」という社内規程が定められていた場合などでは、契約書の電子署名を認めるための社内規程変更が必要となります。
また、押印作業のために出社を行わなくとも、さまざまな書類の授受や締結が可能になれば、自宅でのテレワークやサテライトオフィスでの勤務が可能になります。この場合、就業規則の改訂や、テレワーク勤務規定を付則として作成するなどの対応が必要となるでしょう。
従来とは異なるワークフローで承認や契約を進めることになるため、明確なルールを策定することをおすすめします。
5-4.「脱ハンコ」に向けた取り組みを社内外へ周知する
「脱ハンコ」が可能なデジタルツールを導入し、各種社内規程を変更した後は、新しいデジタルツールの使い方を記したマニュアルや、規程の変更点をまとめた資料などを従業員向けに用意しておき、必要に応じて説明会を開催することも検討しましょう。
社内だけでなく、社外(取引先や顧客など)への周知も重要です。これまで書面でやり取りしてきた取引先に対して、自社の「脱ハンコ」に向けた取り組みによりどのような影響があるのか、相手先に求める対応内容などを周知しましょう。
6.まとめ
この記事では、「『脱ハンコ』とは何か?」という基礎的な知識の説明から、「自社で『脱ハンコ』を進めるべきかどうか」を判断するにあたって参考となる、「脱ハンコ」のメリットや注意点、具体的な進め方などについて詳しく解説してきました。最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
昨今、行政にとどまらず、企業でも広く「脱ハンコ」の風潮が高まっています。 企業が脱ハンコを進めるメリットには、主に以下の6つが考えられます。
企業が「脱ハンコ」を進める具体的なメリット
- テレワーク等の柔軟な働き方が可能になる
- 契約や承認等にかかる時間を短縮できる
- 契約や承認等の進捗状況を管理しやすい
- さまざまなコストを削減できる(切手代・人件費など)
- 書類の改ざん・紛失リスクを低減できる
- 書類の管理・検索が容易になる
一方、企業が「脱ハンコ」を進める上での注意すべきポイントには、以下のような点が考えられます。
- 社内で「脱ハンコ」に向けた取り組みを推進するうえで、一定の労力やコストがかかる
- 取引先や顧客が「脱ハンコ」に消極的な場合がある
上記のようなポイントに注意しながらも「脱ハンコ」を進めることにより、業務効率化や生産性向上を図ることが可能です。競争力のある企業になるためにも、ぜひ「脱ハンコ」を推進することをおすすめします。
「脱ハンコ」を実現するための手段には、ワークフローシステム、電子契約システム、Web帳票発行システムなどの導入があります。これらの中から、自社が目指したい「脱ハンコ」の範囲に応じた外部サービスを選んでいきましょう。
もし「自社で『脱ハンコ』を実現したいが、どのデジタルツールを導入すればいいか分からない」「『脱ハンコ』からデジタル化にチャレンジしていきたいが、何から始めれば良いか分からない」といったお困りごとがあれば、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する