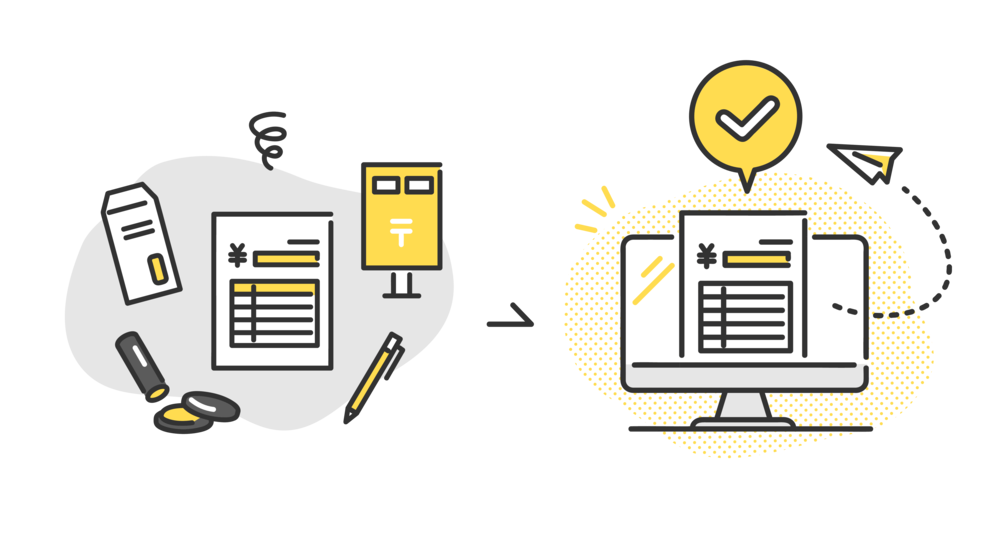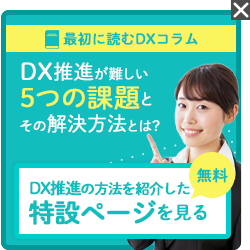更新日:
【厳選&成果別】顧客データ活用事例3選|売上アップする5STEP

「顧客データを活用して売上アップしたい。参考になる活用事例はないかな?」
あなたは、自社で保有する顧客データを活用して「売上拡大」を図りたいのではないでしょうか。
しかし、顧客データをどう活用したらいいのか、具体的なイメージが湧かず、先に進められないのかもしれませんね。
そこで本記事では、顧客データの活用事例を厳選して3つご紹介します。
BtoC企業の事例を中心に、得られる成果別(売上拡大/解約率の低下/業務効率化)に解説するため、参考になるはずです。
- 【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー
- 【解約率の低下】解約率が「17.8ポイント」ダウンしたヘアケア商品の販売会社
- 【業務効率化】修理対応時間を大幅に短縮できたコピー機メーカー
上記から、貴社のニーズに合致した活用事例を参考にすることで「売上アップ」できる可能性が高まります。
しかし、事例を知っただけで、満足するのは危険です。顧客データの活用には手順や押さえるべきポイントがあるからです。顧客データを十分に活用できず、失敗に終わってしまう可能性があります。
そこで、本記事では、成功確率を上げるために「顧客データの活用手順5STEP」も解説します。
「顧客データを有効活用して、売上拡大したい」
「顧客データの活用で、失敗したくない」
といった方に参考になります。それでは早速、みていきましょう。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.顧客データ活用の主目的はこの3つ!
昨今では「VOC(顧客の声)を活用した商品開発」や「顧客データを活用したマーケティング戦略」などが注目を集めています。
顧客データを活用するメリット・目的は3種類あります。
- 売上拡大
- 解約率低下
- 業務効率化
例えば「売上拡大」を実現したい場合には「新規顧客の獲得数を増やすこと」を目標に、顧客データの収集・分析を行ったり、相応のシステムを開発することが考えられます。
まずは上記の「顧客データの活用で、どのようなメリットがあるのか」をしっかりと押さえておきましょう。2章では3つのメリット別に、顧客データの活用事例をご紹介するため、具体的なイメージをもって、活用事例を理解できるようになります。
顧客データを収集・分析する方法例とともに、以下にまとめましたので、ご覧ください。
| 成果の種類 | 顧客データを収集・分析する方法例 | |
|---|---|---|
| ①売上拡大 | 新規顧客の獲得 | 「新規獲得につながった流入経路(広告・SNSなど)」を洗い出すことで新規獲得のヒントが得られる |
| アップセル(クロスセル) | 「上位製品の購入につながりやすい顧客像」「複数買いにつながったキャンペーン」を洗い出すことでアップセルのヒントが得られる | |
| LTV(生涯顧客価値)の向上 (=リピーター/ファン/ロイヤルカスタマーの増加) | 「リピーターの獲得につながりやすい打ち手」を洗い出すことで、LTV向上につながる施策のヒントが得られる | |
| 商品開発 | 「顧客が求める商品のアイデア」を洗い出すことで、商品開発のヒントが得られる | |
| ②解約率低下 | 「解約につながりやすい要因」「解約阻止につながりやすい打ち手」を洗い出すことで、解約率低下のヒントが得られる | |
| ③業務効率化 | 「時間がかかっている原因」「ボトルネックになっている原因」を洗い出すことで、業務効率化のヒントが得られる | |
なかでも、データ分析を行う大きなメリットが「①売上拡大できる」という点です。
例えば、若者に人気の街にあるオーガニック食材のスーパーがあったとします。 このスーパーは、20~30代の女性の来店が多い印象だったため、彼女たちをターゲットに、見た目が華やかなお惣菜を開発していました。
しかし、いざ顧客データを収集・分析してみると、40~60代の女性の方が「再来店率(=リピート率)」と「1回あたりの購入金額」が高いためことが判明しました。
顧客データの分析から、オーガニックスーパーを普段使いしている「ロイヤルカスタマー(優良顧客)」は、40~60代の女性であることが判明したのです。
そこで、スーパーは、40~60代の女性に好まれる「健康志向のお惣菜」の開発に注力しました。
その結果、アップセル(顧客単価の向上)、クロスセル(複数買い)、リピーター増につながり、売上拡大につながりました。
この例えのように顧客データを分析すると、なんとなくの「当て勘」に頼らず、客観的なデータを用いて「打ち手」を決定できるようになります。
その結果、売上拡大につながるといったことがメリットを享受できる可能性があります。
2.顧客データの活用事例3選
本章では「顧客データの有効活用した企業の事例」を紹介します。
「3つの成果別」に解説するため「顧客データをどのように有効活用すべきか」のヒントが得られます。
- 【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー
- 【解約率の低下】解約率が「17.8ポイント」ダウンしたヘアケア商品の販売会社
- 【業務効率化】修理対応時間を大幅に短縮できたコピー機メーカー
ひとつずつ、みていきましょう。
2-1.【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー
| 事業内容 | 食器メーカー |
|---|---|
| 課題 | 購買単価、購買回数の減少で、利益率が悪化していた |
| 顧客データの分析で得られた結果 | 既存顧客のリピート購入率を高めることで、利益率がアップすることがわかった |
| 分析をもとに実行したアクション(施策) | 既存顧客の顧客データや購買履歴データに基づいて、最適化された「ステップメール」を配信する |
| アクション(施策)によって得られた成果 | リピート購買率が約20%アップした |
| 向いている企業 | 「会員情報」を収集している企業すべて |
| 向いていない企業 | 「会員情報」の収集をしていない企業(飲食店など) |
企業Aは、食器を販売するECサイトを運営し、数万人もの会員を集めていましたが「購買単価」と「購買回数」が減少傾向にありました。利益率がいちじるしく悪化していたのです。
利益率をアップさせる方法を模索するなかで、顧客の会員データや購買履歴などを分析した結果、新規顧客を増やすのは費用対効果が悪いということがわかりました。
「既存顧客によるリピート購入率」を向上させることが、利益率向上のために実施すべき有効な戦略だとわかったのです。
この際、企業Aは、販売管理システムに蓄積されている顧客データのうち、以下のようにデータを比較し、戦略を打ち出したのではないかと考えられます。
顧客データの活用方法
「広告施策/販促キャンペーン」を打った際の「顧客別の売上」を、新規顧客と既存顧客とで比較し「どちらがよりコストパフォーマンスが高いのか」を比較する
- 新規顧客向けのキャンペーン費:100万円
→得られた売上300万円 - 既存顧客向けのキャンペーン費:50万円
→得られた売上400万円
→「既存顧客」向けのキャンペーンの方が、費用対効果が高い
→「既存顧客」に向けたアプローチを強化した方が得策との結論に至る
企業Aは、既存顧客の会員データと購買利益を分析して「ステップメールの配信」を行いました。
配信ターゲット、メールコンテンツ、配信タイミングなどを最適化した結果、リピート購買率が、約20%アップしました。
顧客データの活用によって、売上アップにつながった好例です。
2-2.【解約率の低下】解約率が「17.8ポイント」ダウンしたヘアケア商品の販売会社
| 事業内容 | ヘアケア商品の販売・サポート |
|---|---|
| 課題 | コールセンターの稼働枠の確保(問い合わせ数の減少) |
| 顧客データの分析で得られた結果 | 「商品の使い方がわからない」というのが「解約理由」の大きな割合を占めていることがわかった |
| 分析をもとに実行したアクション(施策) | 「商品の使い方動画」をホームページにアップするとともに、「チャットボット」を開設した |
| アクション(施策)によって得られた成果 |
|
| 向いている企業 | 「サブスク/定期購入/月額利用」の商品・サービスを販売している |
| 向いていない企業 | 「売り切り型」の商品・サービスを販売している |
企業Bは、自前でコールセンターを運営していましたが、売上拡大とともに、コールセンターの稼働がひっぱくするようになりました。
コールセンターの稼働枠を確保するために、とりわけ「解約に関する問い合わせ」の効率化を目指しました。
そうしたなかで「解約理由」に関する顧客の声(VOC)のデータを収集したところ「商品の正しい使い方が分からない」ことが、主因であることがわかりました。
この際、企業Bは、コールセンターに寄せられる顧客の声(解約理由)や「解約フォーム」で選択された「解約理由」を、内容別に集計・カテゴリー分けし、もっとも多い解約理由をあぶり出したのだと考えられます。
そこで、企業Bは「チャットボット」を導入しました。
チャットボットでは、顧客の問い合わせに応じて、必要な回答が即時表示されるため、顧客はスピーディに問題解決できるようになりました。
また、使い方動画もアップしたため、顧客が抱いた不明点を解決するための有効な手段になったものと考えられます。
その結果、企業Bは、問い合わせ件数を減らすことができました。
また、解約率は39.5%→21.7%となり「17.8ポイント」改善することができました。
当初の課題は「コールセンターの稼働枠の確保」でしたが、顧客データの分析を行ったことで「解約率の大幅な低下」も実現できたのです。
顧客データ分析の活用によって「解約率の低下」という嬉しい結果を得た好例です。
2-3.【業務効率化】修理対応時間を大幅に短縮できたコピー機メーカー
| 事業内容 | コピー機メーカー |
|---|---|
| 課題 | 修理完了までに時間がかかっていた |
| 顧客データの分析で得られた結果 | コピー機の壊れた箇所 |
| 分析をもとに実行したアクション(施策) | 複合機から送信される顧客データにもとづき、故障の検知や故障個所の把握を、顧客先への訪問前に行える仕組みを構築した |
| アクション(施策)によって得られた成果 | 「故障原因の究明」や「修理対応」にかかる時間が大幅に短縮された |
| 向いている企業 | 顧客対応にかかわる「人件費」を削減したい企業 |
| 向いていない企業 | 顧客対応が発生しない企業 |
複合機メーカーCでは、顧客先に設置しているコピー機の修理もワンストップで行っていました。
そうしたなかで、業務効率化の一環として、修理担当者が現場に行く前に、コピー機からの送信データに基づいて、故障の検知や事前の修理が可能になる仕組みを開発しました。
この際、複合機メーカーCは、複合機内で発生しているエラー箇所が、メーカーの修理担当者の管理システムに、自動で送信される仕組みを開発したのではないかと考えられます。
この結果、修理担当者が現場に行く前に、故障箇所の把握などが行えるようになったため、修理対応時間を、大幅に短縮することができました。
コピー機から得られる顧客データは、ビッグデータとして蓄積し「故障しやすい部品の洗い出し」にも役立ちました。
そのため、メンテナンス品質と、商品品質の向上につながったため、顧客満足度の向上も実現しました。
顧客データの活用が、「業務効率化」につながった事例です。
3.顧客データの活用手順「5STEP」
2章を読んで、顧客データの具体的な活用方法について、イメージが湧いたのではないでしょうか。
続く本章では「実際に、どのような手順を踏んで顧客データを活用していくのか」を解説します。
- 【STEP1】顧客データの活用で得たい「成果」を決める
- 【STEP2】一定量の顧客データを収集する
- 【STEP3】一定量の顧客データから「傾向」を分析する
- 【STEP4】アクションプランを策定・実行する
- 【STEP5】アクションの効果を検証する
3-1.【STEP1】顧客データの活用で得たい「成果」を決める
先述の通り、顧客データの有効活用によって得られる成果は、以下の3つに大別できます。
まずは「1.顧客データ活用の主目的はこの3つ!」や「2.顧客データの活用事例3選」を参考に、「自社は、顧客データを活用してどの成果を得たいか」を考えてみましょう。
- 売上拡大できる
- 解約率を低下できる
- 業務効率化できる
3-2.【STEP2】一定量の顧客データを収集する
得たい成果が決まったら「顧客データの収集」に取り組みましょう。 ここで知っておきたいのは、以下の2点です。
- どんな顧客データを集めればいいのか?(What)
- どうやって顧客データを集めるのか?(How)
どんな顧客データを集めればいいのか?(What)
顧客データは、大きく分けて「定量データ」と「定性データ」の2つがあります。
定量データは「数値化できるデータ」で、定性データは「数値化しにくいデータ」です。
具体的には、以下の通り分類できます。
| 定量データ |
|
|---|---|
| 定性データ |
|
いずれのデータを集めるべきかは「得たい情報」によって異なります。
例えば「2-1.【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー」の事例では、新規顧客/既存顧客別に実施した販促キャンペーンの費用対効果が知りたいため「キャンペーン費用(新規顧客向け/既存顧客向け)」と「得られた収益(新規顧客/既存顧客)」を収集・分析する必要があります。
そのため「定量データの収集」を行う必要があります。
一方「2-2.【解約率の低下】解約率が「17.8ポイント」ダウンしたヘアケア商品の販売会社」の事例では、顧客の解約理由を収集・分析する必要があります。
そのため「解約フォーム」で選択された解約理由を収集する(=定量データを収集する)とともに、カスタマーサポートに寄せられたVOC(顧客の声)の読み解きを行う(=定性データを収集する)のがベストでしょう。
従って「定量データ」と「定性データ」双方の収集が必要になる可能性があります。
このように「得たい情報」から「収集するデータ」を決定します。
どうやって顧客データを集めるのか?(How)
続いて知っておきたいのが「どうやって集めるか」です。
顧客データの収集方法は、「定量データ」と「定性データ」によって異なります。
以下を参考にしてみてください。
| 定量データ |
|
|---|---|
| 定性データ |
|
集めたデータは、視覚的に「グラフ化」するなどして整理しましょう。
分析しやすくなります。
3-3.【STEP3】一定量の顧客データから「傾向」を分析する
客データを収集・グラフ化したら、傾向の分析を行いましょう。
データを分析することで「どのような打ち手を行うべきか」が明らかになります。
分析は「分析ツール(SaaS/ソフト/システム)」を用いるのが基本です。
個別に開発するよりも、自社のニーズに適ったツールを導入したほうが、手間・コスト・時間がかからないため、おすすめです。
以下のようなツールがあります。参考にしてみてください。
| Microsoft Excel | 概要 Microsoft Excel はアドインの「分析ツール」を有効にすると、分散分析や基本統計量、相関などの「基本的なデータ分析」が行えます。導入コストがほぼかからないのが最大の魅力です。ただし、統計分析の基礎知識が必要なため、使いこなすには相応のスキルが必要です。また、顧客データの蓄積ができるプラットフォームではないため、データソースとしてCRMなどを別途用意する必要があります。 |
|---|---|
| おすすめな人 極力コストをかけずにデータ分析を始めたい人 |
|
| MAツール (マーケティングオートメーションツール) | 概要 MAツール(マーケティングオートメーションツール)は「見込み顧客」の行動分析ができるツールです。とりわけ、MAツールによるマーケティング施策の成否を分析するためのレポート機能が充実しているのが最大の特徴です。新規獲得のためのマーケティングに力を入れていきたい人におすすめです。 |
| おすすめな人 「見込み顧客」に対するマーケティング施策の成否をチェックしたい人 |
|
| CRM (顧客管理システム) | 概要 CRMは「既存顧客」の行動分析ができます。「CRM分析」という言葉があるくらい、顧客分析に使われる王道のツールです。基本的には、顧客情報を貯め込むシステムとして知られていますが、分析機能もあるため「LTVの向上に取り組みたい」といった場合におすすめです。 |
| おすすめな人 「既存顧客」のLTV向上に取り組みたい人 |
|
| BIツール (ビジネスインテリジェンス ツール) | 概要 BIツールは、ありとあらゆるデータを分析し、グラフ化/ビジュアル化できます。Excelと同様、データの蓄積機能がないため、データを蓄積するシステムとの連携が必須です。Excelよりも高速でデータ分析ができるほか、SFAやGoogleアナリティクスなど複数のデータソースを横断的に分析できるものもあります。大量のデータを素早くデータ化したい人に最適。 |
| おすすめな人 大量のデータを高速でデータ化したい人 |
|
| VOC分析ツール | 概要 VOC分析ツールは、顧客の声( Voice Of Customer )を収集・分析することで、商品開発やサービス改善などに役立てるものです。基本機能としては、通話解析、テキストマイニング、口コミ分析です。可視化しにくい定性データ(顧客の声(VOC))を、マーケティングにいかしたい方におすすめです。 |
| おすすめな人 「顧客の声(VOC)」を収集・分析して商品開発などに役立てたい人 |
データ分析には、大きく分けて3つの視点があります。
データを注意深くみて、いずれかに当てはまる傾向がないかをチェックしましょう。
| 「異常値」の発見 | 概要 データのなかから「突出する値」をみつける |
|---|---|
| 例 解約理由の50%を占めるのは「使い方がわからない」という理由であり、圧倒的に多いことがわかった |
|
| 「規則性」の発見 | 概要 データのなかから「一定のルール」や「規則性」をみつける |
| 例 年代問わず「商品購入額」が高い顧客ほど「メルマガ開封率」が高いという規則性があるようだ |
|
| 「因果関係」の発見 | 概要 ある事柄が、別の事柄に影響を与えている事象をみつける |
| 例 「気温が高いほど、アイスクリームが売れる」という因果関係があるようだ |
3-4.【STEP4】アクションプランを策定・実行する
得られた分析結果をもとに「アクションプランの策定&施策の実行」を行いましょう。
具体的には、以下の空欄を埋めるイメージです。
アクションプランの策定・実行のセオリー
「○○(誰)」に対して「××する(施策)」ことで「□□(弱点)」を「△△(改善目標)する」
例えば「2-1.【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー」の場合には、以下の通りです。
食器メーカーの場合
既存顧客の顧客データや購買履歴データに基づいて、最適化された「ステップメール」を配信する
こうしたアクションプランの策定により、狙った成果を得るのが、顧客のデータ活用の真髄です。
オンライン/オフライン問わず、さまざまな打ち手(=アクションプラン)があります。
以下は一例です。参考にしてみてください。
| ポップアップ表示 | 特定の属性の顧客に対して、Webサイト上で「おすすめの商品」をポップアップ表示して「アップセル」を実現する |
|---|---|
| レコメンド機能 | 顧客が閲覧している商品データから「一緒に購入されている商品」を紹介して「クロスセル」を実現する |
| オンライン接客の ブラッシュアップ | 顧客にインタビューをして「オンライン接客マニュアル」を改善して「新規獲得率」を上げる |
| デジタル広告の最適化 | 顧客の流入につながりやすいバナー広告を洗い出して「新規獲得率」を上げる |
| メールマガジンの配信 | LTVが高い顧客に対して「お得意様限定キャンペーン」をメールで配信して「売上拡大」を実現する |
| クーポンの配布 | 店頭で「2点購入したら30%OFFクーポン」を夕方に行うことで「売上拡大」を実現する |
| エントリフォーム最適化 | 問い合わせフォームから離脱した顧客の行動履歴をチェックして、離脱率低下につなげる |
| 商品の使い方ページの改善 | 「FAQコーナー(よくある質問)」を充実させたり「チャットボット」を導入したりして、使い方を理解させることで、解約率の低下につなげる |
| ロングセラー商品化 | 売上のよい商品を「ロングセラー商品」として店頭で売り続けることで「売上拡大」を実現する |
3-5.【STEP5】アクションの効果を検証する
アクションプランを実行したら「効果検証」もセットで行いましょう。
「想定した結果が得られたか」を確認し、相応の結果が得られれば、継続的にキャンペーンを実行するなどして、売上拡大につなげます。
一方、相応の結果が得られなければ、顧客データを再度収集したり、顧客データを別の視点から分析します。
顧客データの有効活用においては「PDCAサイクルを回し続ける」ことが大切です。
4.顧客データを活用する際に押さえたいポイント5つ
顧客データの活用手順について、理解が深まりましたでしょうか。
続いて、顧客データの活用で押さえておきたいポイントを解説します。
ポイントを押さえないと、思ったような成果が得られず、失敗に終わってしまう可能性がありますから注意が必要です。
- 「データドリブンマーケティング」を目的にしない
- 顧客データの分析ツールは「UI/UX」を確認してから導入する
- 顧客データの分析に知見のある「データサイエンティスト」や「専門家」を迎え入れる
- 社内に散らばったデータを統合して「データの有用性」を高める
- 「ファーストパーティデータ」だけでなく「サードパーティデータ」を活用する
一つずつ、みていきましょう。
4-1.「データドリブンマーケティング」を目的にしない
重要なポイントの一つが「データドリブン(データに基づいてビジネスの意思決定や課題解決をする)マーケティングを目的にしない」ということです。
データ分析そのものを目的にしても、時間を浪費するばかりで、なんら価値を生み出さないからです。
例えば、ある高級ブランドコスメが、顧客データを分析してみたところ、解約率が高い原因が「値段の高さ」だと判明したとしましょう。
その場合、データドリブンマーケティングに則るならば「値段を下げる」という打ち手に至るかもしれません。
しかし、高級ブランドコスメの場合「値段を下げる」というのは、よい打ち手ではありません。
値段を下げることによって、高級ブランドというイメージが崩れる可能性があるからです。
それよりも、顧客データの分析目的を「売上拡大」にして「LTVが高い顧客の特徴」を洗い出したり、「VOC(顧客の声)の分析」を行って「顧客の求める商品開発のヒント」を得た方が賢明でしょう。
このように、自社の商品やブランドイメージ、置かれている現状に即して、適切に目的を設定し、必要な顧客データ分析を行うことが大切です。
4-2.顧客データの分析ツールは「UI/UX」を確認してから導入する
MAツールやCRMなどの分析ツールは、導入前に「UI(ユーザーの視覚に触れるすべての情報)/UX(ユーザーが製品やサービスを通して得られる体験)」をチェックしましょう。
使い勝手がよくない場合や、使いこなせない場合には、ツール導入がムダになってしまう可能性があるからです。
「無料のトライアル期間があるか」「無料プランがあるか」「デモンストレーションを行ってくれるか」などを確認すると安心です。
4-3.顧客データの分析に知見のある「データサイエンティスト」や「専門家」を迎え入れる
いざデータ分析を始めようと思っても、データ分析の経験がない場合、戸惑ってしまう可能性が高いです。社内で、イチからデータ分析のスペシャリストを育て上げるのも、コストと時間がかかります。
そのため、外部からデータサイエンティストや専門家を雇って、データ分析を一任するのも手です。
「餅は餅屋」の発想で専門家に依頼した方が、スムーズに顧客データの収集・分析作業が進む可能性が高いからです。
外部から業務委託などの手段でサポートしてもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
4-4.社内に散らばったデータを統合して「データの有用性」を高める
顧客データの収集は、時間やコストがかかる作業です。
そのため、各部署が保有する「散らばった顧客データ」をかき集め、統合して、有用性の高い顧客データに仕上げるのが得策です。
そうすれば、質と量において満足できる「使えるデータ」を収集できるからです。
例えば、アパレルショップが、本店とフランチャイズ店で、別々のCRM(顧客管理システム)を利用している場合。
全社統一のCRMシステムを導入して、大量の顧客データを収集してマーケティングにいかすといったことが挙げられます。
本店・フランチャイズ店ともに、収益アップのために役立つ有益なヒントが得られるでしょう。
4-5.「ファーストパーティデータ」だけでなく「サードパーティデータ」を活用する
顧客データというと「自社が自力で集めるもの」と考えている方もいるかと思います。
しかし、顧客データは、自社が保有する「ファーストパーティデータ」だけではありません。
パートナー企業から提供してもらう「セカンドパーティデータ」と、第三者の組織・機関・企業などから提供される「サードパーティデータ」もあります。
具体的には、国や地方自治体による公開データや、データ収集を専門とする一般企業によるデータなどです。
自社のリソースのみに頼るのではなく、外部が提供するデータもうまくミックスすることで、データ収集の精度を高めたり、効率化できたりします。
例えば、大手のタクシー会社が、配車の需要予測システムを開発したい場合。
通信会社や人工衛星が保有しているGPS情報や、人数分布、移動変化のリアルタイム情報などの「サードパーティデータ」を活用することで、高精度なシステムを開発できるでしょう。
自社のタクシーで顧客を載せた走行データ(=ファーストパーティデータ)と組み合わせるなどすれば、高精度な配車予測が可能になるかもしれません。
このように、必要に応じて外部のビッグデータを活用するのも手です。
ここまで記事を御覧いただいた上で、
「顧客データの活用方法についてもっと知りたい…」
「自分で調べて対応する時間がない」
「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
5.まとめ
本記事では「顧客データの活用事例」について解説しました。
顧客データの活用で得られる成果は、以下の3つです。
- 売上拡大
- 解約率の低下
- 業務効率化
顧客データの活用事例(3つの成果別)は以下の通りです。
- 【売上拡大】リピート購入率が「約20%」アップした食器メーカー
- 【解約率の低下】解約率が「17.8ポイント」ダウンしたヘアケア商品の販売会社
- 【業務効率化】修理対応時間を大幅に短縮できたコピー機メーカー
顧客データの活用手順は「5STEP」で説明できます。
【STEP1】顧客データの「活用目的」を設定する
【STEP2】一定量の顧客データを収集する
【STEP3】一定量の顧客データから「傾向」を分析する
【STEP4】アクションを策定・実行する
【STEP5】アクションの効果を検証する
顧客データを活用する際に押さえたいポイントは5点あります。
- 「データドリブンマーケティング」を目的にしない
- 顧客データの分析ツールは「UI/UX」を確認してから導入する
- 顧客データの分析に知見のある「データサイエンティスト」や「専門家」を迎え入れる
- 社内に散らばったデータを統合して「データの有用性」を高める
- 「ファーストパーティデータ」だけでなく「サードパーティデータ」を活用する
顧客データの活用は、効率よく「売上アップ」を叶える最適の打ち手です。
眠った顧客データを活用してみてはいかがでしょうか。