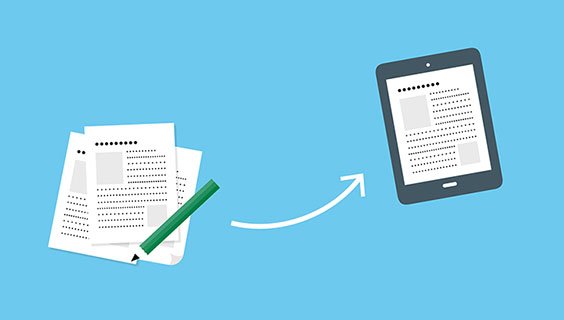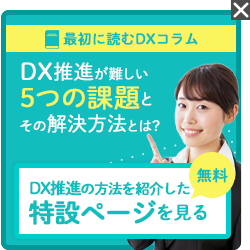更新日:
自動化可能な経理業務とは?社員の理解を得ながらスムーズに自動化を実現しよう

業務品質を落とさずに従業員の働き方を改善する施策として、業務の自動化へ取り組み始める企業が増加しています。なかでも、定型業務を中心に、経理業務の自動化に取り組もうと考えている経理部門責任者の方は多いのではないでしょうか?
経理業務は、データ入力や伝票発行といった反復操作を伴う定型業務が多く、業務の正確性や処理スピードが求められます。そのため、ITツールやシステムの導入・活用などによる自動化に適している業務が多いとみられます。一方で、すべての経理業務が自動化できるわけではありません。
また、企業によって自動化すべき経理業務の優先順位も異なるため、自社にとってどの業務から自動化すべきかを検討し、見極めながら取り組むことが非常に重要です。
経理業務の自動化には、経理部門の社員が一丸となって取り組むことが大切です。そのため自動化ツールやシステムを導入する際は、実際に業務をおこなう現場担当者の理解・協力が欠かせません。
なかには「機械に自分の仕事を奪われる」と誤解し、自動化に対しネガティブなイメージを持たれる方もいます。現場担当者が不安を感じている状態で自動化を無理に進めると、就業意欲の低下を招きかねず、結果的に自動化ツールやシステムのスムーズな導入は困難となる場合もあります。
そこでこの記事では、経理業務の自動化を成功させるために、以下のことについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- 自社が自動化すべき経理業務の見極め方
- 自動化できる経理業務と、自動化に適さない業務の特徴
- 経理業務を自動化する主な方法
- これからの経理に求められている能力やスキル
「経理業務の自動化をスムーズに実現したい」
「経理部門全員が一丸となって自動化に取り組むため、目指すビジョンを明確にしたい」
という方は、ぜひ最後までお読みください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.経理業務を自動化する際は、自動化すべき業務を見極めることが重要
経理は企業のお金の動きを管理する部門です。正確性が重要で、ミスが許されず、二重三重にチェック作業が発生する業務も多く存在します。
このような、数字の正確性や作業スピードが求められる経理業務の多くは、ITツールやシステムを使った自動化に向いています。
しかし、すべての経理業務を自動化できるわけではありません。経理業務を自動化する際は、自社のどの業務を自動化すべきか、見極めたうえで取り組むことが重要です。
業務処理にかかっている時間やコスト、経理担当者の負担は、企業ごとに異なります。経理業務にも、自動化に適している業務と、そうでない業務があるため、業務の特性を理解したうえで、自社における自動化の優先順位を判断する必要があります。
そのため、自動化に対する検討の前段階として、経理の業務工程を洗い出し、どのような業務にどの程度の時間やコストがかかっているのかを可視化することをおすすめします。ITツールやシステムを導入する前に、経理業務の自動化によって削減できる時間やコスト、どの程度効率化につながるのか等を検証することにより、得られる効果を最大に引き上げられるでしょう。
2.自動化に向いている経理業務3つ
経理業務には、自動化に向いている業務と、そうでない業務があります。
自動化に向いている業務は、作業の流れやルールが明確な定型業務です。自動化により高い効果が見込める業務として具体的には
- 経費精算業務
- 請求書発行や入金消込業務
- 仕訳業務
などが挙げられます。
各業務の特徴や、どのように効率化が実現できるのか等について、ひとつずつ解説します。
2-1.経費精算業務
経費精算業務は、自動化の効果が大きい業務のひとつです。
経費精算業務の自動化により、交通費や立替払いの精算など、全社員が定期的におこなう作業を効率化できます。経理部門のみならず、経費精算をおこなう必要のある大勢の社員の手間や作業時間の削減につながるため、企業全体の大幅な効率アップが見込めるでしょう。
経費精算の効率化はニーズが高いため、さまざまな企業が経費精算業務の自動化が可能なITツールやシステム開発に力を入れており、各社から提供されている機能も多種多様です。自社のニーズに合わせたサービスを導入することにより、より導入効果を高められます。
たとえば、交通系ICカードと連携し、定期区間を除いた交通費を自動計算できる機能や、不正申請を自動でチェックする機能なども開発されています。そのような機能を活用することによって、経理担当者が申請内容をひとつずつチェックし、間違いがあった場合などに差し戻しをおこなう、といった手間を大幅に削減できるでしょう。
経費精算業務を自動化することは、経費精算の申請者と、申請された内容を精査する経理担当者の、双方の業務効率化を実現することへ繋がります。経費精算業務は、企業において欠かせない業務のため、早急に自動化することをおすすめします。
2-2.請求書発行や入金消込業務
請求書発行や入金消込業務も、自動化が可能な業務です。
請求書の発行や入金消込業務は、一定の期間に業務が集中する傾向にあります。期間中、通常業務と並行してこれらの作業を進めなければならない経理担当者には、大きな負担がかかることも想定されます。
請求書発行や入金消込業務にかかる負担は、これらの業務を自動化することにより、大幅に軽減できます。
たとえば
- 販売管理システムなどから取り込んだデータをもとに請求金額を集計し、作成した請求書を取引先の希望に合わせてメールと郵送で送り分ける
- 金融機関の入金データを取得、照合して消込をおこない、未入金があれば催促をおこなう
など、さまざまな作業を自動でおこなうことが可能です。
現在手入力で請求書を作成し、郵送しているような企業であれば、自動化による効果は非常に大きいものとなるでしょう。
特定の業務の全工程を完全に自動化するのか、多くの手間がかかっている作業に限定して自動化を進めるのかは、コストや状況に合わせて判断することがおすすめです。
2-3.仕訳業務
取引データの仕訳業務も、自動化に適した業務です。あらかじめ設定した区分や勘定科目をもとに、取引データを自動で分類することにより、膨大な取引データを短時間で処理できます。
仕訳業務を自動化することで、業務時間を短縮できるうえ人的ミスの予防が可能です。すると、経験の浅い経理担当者であっても、限られた時間で仕訳業務に対応できるため、業務の属人化も防げるでしょう。
ITツールやシステムによっては、インターネットバンキングやクレジットカードの明細を取り込み、自動で勘定科目を判別して仕訳伝票を作成することも可能です。
また、AIを搭載した自動仕訳機能を持つITツールやシステムも登場しています。自動仕訳の訂正を都度学習し、次回以降の仕訳に活かすため、仕訳回数を重ねるごとに高い精度での自動仕訳が実現できるでしょう。
自動仕訳機能を活用すれば、経理担当者は最終的なデータを確認するだけで仕訳業務が完了します。勘定科目の選択で迷う時間もなくなるため、業務の手間や時間を大幅に短縮できます。
3.自動化が難しい経理業務2つ
経理業務の中でも自動化しやすい定型業務に対して、非定型業務の自動化はハードルが高くなっています。非定型業務とは、状況に応じて考える必要がある業務や、臨機応変に判断するような業務のことを指します。
柔軟な考えや判断が必要となるクリエイティブな非定型業務は、決まった仕事の流れが存在しないことやマニュアル化がされていないことも多いため、自動化が難しいといえるでしょう。
経理の非定型業務には、
- 企画・戦略立案業務
- システム運用管理やイレギュラーな事態へ対応する業務
などが挙げられます。
3-1.企画・戦略立案業務
経理担当者がさまざまな情報を取り入れて考える業務は、自動化が難しいと言えます。
- 経理業務で取り扱うデータを分析し、得られた事実を社内へ説明する
- データや資料をもとに、経理部門における今後の企画や戦略を立案する
といった業務は、変わらず人が対応する必要があります。
会計ソフトに備わっているAIにも学習機能はあるものの、データをもとに企画や戦略を立てることは現状できません。今後そのような機能が開発される可能性はありますが、これらの業務は、当面は人の力が必要となる業務のままでしょう。
3-2.システム運用管理やイレギュラーな事態へ対応する業務
システムの運用管理やイレギュラーな事態へ対応する業務は、自動化が困難です。
自動化のために導入したシステムやITツールについては、運用管理が必要になります。ただし、普段とは異なる条件で実施された取引に関わる経理業務や、エラー発生時の対応など、システムやITツールがそのままでは対応できないイレギュラーな事態が発生した場合は、経理担当者が個別に対応する必要があります。
そのため、経理業務を自動化したとしても、完全に業務が人の手を離れることはありません。
このように、対応手順や判断基準が明確に決まっていない業務は、自動化が難しい業務と言えるでしょう。
4.経理業務を自動化する3つの方法
経理業務を自動化する方法は複数ありますが、一般的に多く活用されている方法として
- Microsoft Excelなど表計算ソフトのマクロ機能の活用
- RPA(ロボティックプロセスオートメーショ)の導入
- 財務経理システムの導入
の3つの方法が挙げられます。
経理業務を自動化するための適切な方法は、自動化を導入したい業務の範囲や、使用するアプリケーションなどによっても異なります。
どの業務から自動化を進めるべきかを把握するためには、あらかじめ業務手順を棚卸しすることにより、経理業務全体の業務フローや作業を明確にしたうえで、総合的に判断することが大切です。
以下では、自社にとって最適な自動化の方法を判断できるよう、3つの自動化方法の概要や、自動化できる業務内容、各方法で自動化をおすすめしたい企業などについて解説します。
4-1.Microsoft Excelなど表計算ソフトのマクロ機能の活用する
自動化したい経理業務が、Microsoft Excel(以下Excel)などのOfficeアプリケーション内で完結する場合は、表計算ソフトのマクロ機能を活用して自動化できるかを検討しましょう。
Excelを使って、目視で内容の確認をおこないながら請求書発行業務や仕訳業務をしている場合は、マクロ機能を活用すると想像以上に業務負担が軽減される可能性あります。
マクロ機能はExcelが搭載されているパソコンであれば使用できるため、新たな導入コストがかからない点も大きな魅力です。
たとえば請求書発行業務であれば、請求データ一覧から取引先名や住所、担当者、金額をテンプレートに自動表示し、PDF化して、メールで送信するまでをマクロ機能で自動化できます。
仕訳業務であれば、事前に明細と勘定科目の対応表を作成することにより、クレジットカードの利用明細に勘定科目を自動反映させることも可能です。
ただし、マクロ機能を活用して複雑な操作を自動化するには、特定のプログラミング知識が必要となります。場合によっては、社員を育成する時間やコストがかかる可能性も考えられます。
そのため、社員が持つプログラミングスキルをしっかりと把握してから判断することが大切です。
もし社員にプログラミングの知識がほとんど無い状態で、自動化による抜本的な業務改善をスムーズにおこないたい場合には、次項以降で紹介するRPA(ロボティックプロセスオートメーション)や財務経理システムの導入が検討しやすいでしょう。
まとめると、Excelのマクロ機能を活用した自動化は
- Excelでまだマクロ機能を積極的に活用できていない
- RPAや財務経理システムの導入費用捻出が難しい
- 既存のシステムは維持したまま、自動化につながる工夫を取り入れたい
といった企業におすすめしたい方法です。
4-2.RPA(ロボティックプロセスオートメーション)を導入する
RPAは、パソコン上の操作を自動化できる方法です。
とはいえ、そもそもRPAがどのようなものかイメージが湧かない方も多いかと思います。そのため、まずはRPAの概要について詳しく説明します。
4-2-1.RPAとは
RPAとはRobotic Process Automationの略語であり、パソコンでおこなう業務をロボットに代替させる方法です。
自動化したい業務の操作をRPAツールに記録して実行タイミングを設定すると、記憶させたシナリオ通りにロボットが自動で業務を実施します。
RPAで自動化できる業務は定型業務に限られるものの、先ほどご紹介したマクロ機能を利用した方法とは異なり、複数のシステムやデータを横断的に扱う業務についても自動化できることが特徴です。
既存のアプリケーションや社内システムを変更せずに、現行の業務フローそのものをロボットに記憶させて自動化できるため、幅広い業務の自動化に役立ちます。
たとえば、手作業で交通費の経費精算業務をおこなう場合、従来は精算をおこないたい経費一件ごとに、以下のような手順を繰り返し、正しい経路・金額で提出されているか確認する必要がありました。
- 表計算ソフトで作成した交通費精算リストから乗車駅・降車駅を参照する
- インターネットで経路を検索し、正しい金額を調べる
- 正しい金額と交通費精算リストに記載された申請金額を比較し、誤りがないかを確認する
- リストに記載されている数だけ同様の操作をおこなう
RPAを活用すると、これらの手順をロボットで自動化することが可能です。
RPAでは、人の手でおこなっている定型業務の多くを自動化できます。ロボットが反復作業の多い定型業務を代替することで、業務時間を大幅に短縮できるでしょう。
4-2-2.RPA導入による削減効果の事例
RPAでは、パソコン上のさまざまな定型業務を自動化できるため、必要に応じたシナリオを作成することにより、定型業務にかかる時間の大幅な削減が期待できます。
会計事務におけるRPA導入により、パソコン作業時間を年間換算で約33,255時間以上削減する効果が出たという事例もあるようです。
RPA導入における業務効率化の一例として、会計事務でおこなっている6つの業務において、パソコンの作業時間をRPA導入前後で比較した表をご紹介します。
| 業務名 | パソコン作業時間 | 削減時間 | 削減効果 | |
|---|---|---|---|---|
| RPA導入前 | RPA導入後 | |||
| 支払関係業務 | 33,806時間40分 | 1,303時間55分 | 32,502時間44分 | 96.1% |
| 公会計財務諸表等の作成業務 | 327時間 | 14分 | 326時間45分 | 99.9% |
| 決算・収納データ提出業務 | 11時間36分 | 43分 | 10時間52分 | 93.7% |
| 旅費関係業務 | 286時間 | 10時間 | 276時間 | 96.5% |
| 人事・給与関係業務 | 140時間10分 | 6時間38分 | 133時間31分 | 95.3% |
| 物品調達業務 | 5時間50分 | 13分 | 5時間36分 | 96.2% |
| 6業務 合計 | 34,577時間16分 | 1,321時間45分 | 33,255時間30分 | 96.2% |
あくまで一例ですが、RPAの導入によって上記のように様々な業務にてパソコンでの作業時間を削減できる可能性があります。
さらに、これらの削減できた業務に従事していた担当者は、自動化によって捻出した時間を他のコア業務へ有効活用できるため、業務全体の質の向上に役立つ可能性もあります。
4-2-3.RPA導入に向いている企業
RPAの導入は、既存システムや業務フローを変えたくない企業や、抜本的な業務改革を求めている企業に向いている自動化方法です。
RPAはシナリオに沿って動くロボットを作成し、決まった手順を自動化する仕組みのため、基本的に作成したシナリオ通りにしか対応できません。シナリオ上で連携したツールのバージョンアップや法改正などにより、少しでも操作方法が変わると、シナリオを作成しなおす必要があります。
またRPAは、高額な導入コストがかかる場合があるほか、RPAに関する一定の知識がなければ対処の難しい事態が起きるケースがある点には、留意が必要です。導入後のRPA運用管理やメンテナンス、想定外のトラブルが起こった際などに備えなければなりません。
RPAは
- マクロ機能では対応不可能な、複数のシステムを横断的に使用する定型業務を自動化したい
- 既存システムを活用しつつ、自動化で抜本的な業務改革を実現したい
- 導入効果の高い自動化方法を検討している
といった企業におすすめの自動化方法です。
4-3.財務経理システムを導入する
自動化したい内容が一部の業務に集中している場合は、経理業務の効率化のために開発された専用システムを導入して、各業務を自動化する方法が効果的です。
経理業務でよく活用されるシステムには、以下のようなものがあります。
- 会計システム
- 請求書発行・受領システム
- 経費精算システム
たとえば経費精算システムであれば、
- パソコンやスマホから経費精算申請書を作成し、システム上で責任者に承認を依頼する
- 自動で定期区間を控除した交通費を算出し、申請ミスを防ぐ
- 承認や差し戻し作業をボタンひとつでおこなう
などの機能が搭載されていることにより、経費精算業務の自動化が可能です。
システムにはインストール型とクラウド型があります。クラウド型のシステムは、その機能や利用人数によって大きく価格に幅がありますが、比較的低コストで初期導入できるものもあります。
クラウド型は、インターネットを経由して操作するため、複数のデバイスからアクセスできるというメリットがあります。また、適宜アップデートされるため、法改正などへ対応しやすいことも特徴です。導入費用は、クラウド型のシステムには比較的低コストで導入可能なものも存在します。
このような、経理業務の自動化に役立つシステムは、一般企業による開発・提供が盛んにおこなわれており、種類も豊富であるため、自社にとって負担の大きい業務を確実に自動化できるよう、複数の企業のシステムや機能をしっかりと比較して選択すると導入効果を高めることができるでしょう。
まとめると、財務経理システム導入による自動化は
- 自動化を希望している業務が明確になっている
- マクロを活用した部分的な自動化ではなく、経理業務の一連の流れを自動化したい
- RPAのような高額な導入費用は捻出できないものの、高い導入効果を得たい
- 専門のツールを導入して、手間をかけずに自動化を実現したい
という企業におすすめの方法です。
5.これからの経理部門は柔軟に思考する力が必要
このように、経理業務の自動化に関する検討を進めていると、なかには「自動化を進めると、自分たちの仕事がなくなってしまうのではないか」と危機感を感じる社員が出てくるかもしれません。
たしかに、自動化によって大幅に業務効率が上がるため、経理の定型業務に従事する人数を減らすことは可能になります。したがって、自動化が浸透すると、経理部門から他部門への異動や、業務内容が変更される可能性は高くなるでしょう。
しかし、経理部門がなくなることはありません。
経理部門に求められるスキルや役割は変わっていくものの、自動化が進んでも人にしかできない経理業務はたくさんあります。
ここからは、自動化後に経理部門が果たす役割や、今後の経理部門に求められるスキルについて解説します。
5-1.自動化後に経理部門が果たす役割とは
経理業務の自動化が進むと、企業のお金の流れを詳細かつ正確に記録する役割は、システムやITツールが担うようになります。すると、経理部門の役割は、企業の利益を生み出すためことに集約されていくようになるかもしれません。
経理部門は、企業のお金の流れに関する情報を正確に読み解くことにより、経営者のサポーターとして活躍することが期待されるでしょう。
たとえば、経理部門がデータから企業の経営状態を総合的に分析し、会計情報を作成し報告することで、経営者は利益拡大に役立つ具体的な方針や施策を立てることができるかもしれません。
5-2.自動化後に経理部門が果たす役割とは
自動化が進むと、定型業務の多くが現在よりも少ない作業時間で実行できるため、経理担当者に必要とされるスキルも変わる可能性があります。
これからの経理部門で引き続き活躍する人材となるためには、
- 導入するツールやシステムの運用スキル
- データを分析し判断するスキル
の2つのスキルを身に付けることがおすすめされます。
5-2-1.導入するITツールやシステムの運用スキル
経理業務を自動化するITツールやシステムを導入する場合は、その運用管理やメンテナンスをおこなう人材が必要です。そのため、今後はRPAをはじめとするITツールやシステムの運用スキルが求められるでしょう。
自動化の検討段階から、現場の経理担当者にITツールやシステムの利用者研修へ参加してもらうことにより、自動化ツールのスムーズな導入へ役立つでしょう。
また、ウェビナーや情報サイトなどを活用し、ITツールやシステムの基本的な知識を身に付けておくだけでも、それらの初期設定をする際や、エラーが発生した場合などに落ち着いて対処できるようになります。
今後、自動化が一段と進めば、経理部門の人材にもITやプログラミングの知識が求められる時代が来るかもしれません。
5-2-2.データを分析し判断するスキル
業務の自動化が成功したのち経理担当者には、さまざまなデータを分析して判断するスキルが、今以上に重要となります。
経理業務を自動化しても、それらのデータを活用して何らかの判断をおこなう、データから業績などを予測して具体的な経営戦略を立てる、といった業務は非常に重要です。
定型業務の処理にかかっていた時間は、業務を自動化することにより大幅に短縮可能です。経理担当者は、今後はその時間を活用して、「自ら考えて動ける経理」に成長することが求められています。
6.まとめ
経理業務の自動化を検討する際は、どの業務を自動化すべきか検討し、見極めてから取り組むことが大切です。
経理業務にかかる時間やコスト、担当者の負担は、企業によって異なります。すでに一部の業務で導入済みのシステムが存在するケースも多いため、まずは業務ごとに自動化の優先順位を判断しましょう。
業務の自動化によって削減できる時間やコストを検証してから業務自動化を判断することによって、より高いコスト削減効果を得られるはずです。
経理業務のなかでも、自動化に適しているのは作業の流れやルールが明確な定型業務です。
とくに
- 経費精算業務
- 請求書発行や入金消込業務
- 仕訳業務
などは単純な手順を繰り返す作業が多いことから、高い導入効果が期待できます。
一方で、企画・戦略立案など考える必要がある業務、システム運用管理やイレギュラーな事態へ対応する業務などの非定型業務の自動化は難しいため、今まで通り人が対応する必要があります。
経理業務を自動化は、一般に
- Excelなどのマクロ機能の活用
- RPAの導入
- 財務経理専用システムの導入
によって進められるケースが多くみられています。
自動化したい業務の範囲や使用しているアプリケーションによって最適な方法が異なるため、全体の業務フローを総合的に考えて、自動化方法を選択しましょう。
ただし、経理業務の自動化が進んでも、すべての経理業務が機械に置き換わることはありません。これからの経理担当者には、企業の利益拡大に貢献できるよう、企業を取り巻く環境変化に柔軟に対応し、積極的に思考することが求められます。
自動化は、業務の効率アップはもちろんのこと、業務時間を削減することにより、働き方の改善へも役立ちます。自動化をスムーズに実現できるよう、経理部門全体で経理部の今後について議論・共有し、部門一丸となって自動化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
ここまで記事を御覧いただいた上で、
「自社にあった自動化の方法がわからない」
「導入を前提に、自社にあった財務経理システムを検討したい」
とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する