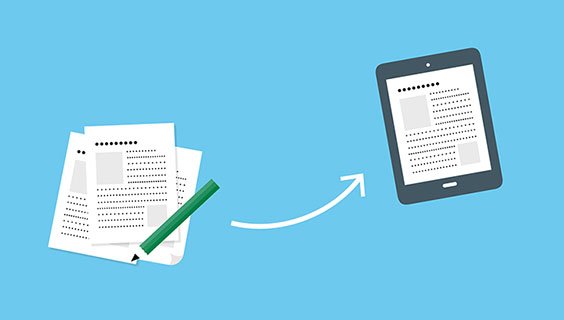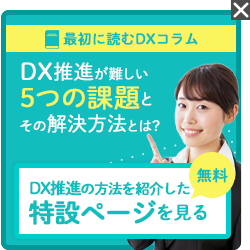更新日:
電子帳簿保存法対応システムとは?必須知識から最適なツール選びまで

電子帳簿保存法対応システムとは、電子帳簿保存法に対応する形で電子帳簿を保管できる「JIIMA認証」を得たシステムのことです。
電子帳簿保存法対応システムとは
電子帳簿保存法の要件を漏れなく満たしていることが照明されたシステム
電子帳簿保存法対応システムを選ぶことで、手間を省いて法改正への対応漏れをなくせるほか、経理業務を効率化できるなど、多くのメリットがあります。
多くのメリットがある電子帳簿保存法対応システムは積極的に導入していきたいツールです。一方で
「種類が多くて、どれを選べばよいのかわからない」
「選び方のポイントが知りたい」
という方も多いでしょう。
実際に、電子帳簿保存法対応システムはどれを選んでも同じではなく、使いたい書類に対応したものや、効率化したい業務に関係する機能が充実したものを選ばないと使いこなせません。
さまざまな種類がある中から、自社に最適な電子帳簿保存法対応システムを選ぶには、電子帳簿保存法の対象などに関する基礎知識や選び方のポイントなどを押さえておくことが必要です。
電子帳簿保存対応システムの選び方のポイント
- 対応書類の多いものを選ぶ
- システム化したい業務の範囲に合わせる
- 自動入力機能があるものを選ぶ
この記事では、電子帳簿保存法対応システムに関する特徴・メリットや、電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法、電子帳簿保存法対応システムの選び方などを解説します。
この記事の内容
- 電子帳簿保存法対応システムとは
- 電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法
- 電子帳簿保存法対応システムの選び方
今回ご紹介する内容を把握しておくことで、電子帳簿保存法対応システムについて、基本的なことを理解し、自社に最適なシステムを選ぶことができるようになるでしょう。
改正の機会が多い法令に漏れなく対応し、安心して業務を進めるためにも、自社のニーズに沿った電子帳簿保存法対応システムを選べるようにしましょう。
どのような電子帳簿保存法対応システムが自社にあっているかが分からない方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
目次
1.電子帳簿保存法対応システムとは
電子帳簿保存法対応システムとは、電子帳簿保存法に対応する形で、電子帳簿を保管できる「JIIMA認証」を得たシステムを指します。
JIIMA認証とは
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証。
電子帳簿保存法の要件を満たしていることが認められている。
上記のとおり、電子帳簿保存法対応システムは、電子帳簿保存法の要件を漏れなく満たしていることが証明された安心できるシステムです。
電子帳簿保存法の複雑な要件の全容を把握できていなくても、対応システムを選びさえすれば、手間をかけずに保存の要件にあった業務体制を構築できます。
ここでは、電子帳簿保存法対応システムについて、
- 必要とされる背景
- 電子帳簿保存法改正のポイント
- システムの特徴
- 導入するメリット
といった、正しいシステム選びに欠かせない基本的な事項を押さえておきましょう。
1-1.電子帳簿保存法対応システムが必要とされる背景
電子帳簿保存法対応システムが必要とされる背景には、法律の改正や新しい制度の施行により、企業を取り巻く環境が大きく変わっており、対応が求められていることが挙げられます。
主な変化を確認しておきましょう。
| 2022年1月 改正電子帳簿保存法施行 |
|
|---|---|
| 2023年10月 インボイス制度開始 |
|
参照元:国税庁:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
国税庁:電子帳簿保存法の内容が改正されました
以上のような法改正などに伴い、国税関係の帳簿や書類の取扱いに、複数の変更点が発生します。
そして、複雑な変更点に漏れなく確実に対応するため、電子帳簿保存法対応システムへの注目が集まっているのが現状です。
1-2.電子帳簿保存法改正による主な変更点
電子帳簿保存法改正に伴う、企業の対応に直接関係する主な変更点は、次の5つです。
| 電子取引データ保存時の要件義務化 |
|
|---|---|
| 事前承認手続き廃止 | 電子帳簿保存するときに事前に必要とされていた税務署長の承認が不要に |
| 適正事務処理要件の廃止 | 電子帳簿などをスキャナ保存するときに必要とされていた社内規程の整備などが不要に |
| タイムスタンプ要件緩和 |
タイムスタンプの要件が、以下のとおり緩和 【改正前】 |
| 検索要件の緩和 | 税務署職員の質問検査権行使に対し、すぐにデータがダウンロードできる状態になっているなら、以下の①②の検索要件は不要に ①日付または、金額の範囲を指定して検索できるようになっている ②2つ以上の項目を組み合わせた条件を指定して検索できるようになっている |
参照元:国税庁:電子帳簿保存法一問一答
国税庁:電子帳簿保存法の内容が改正されました
上記のとおり、法改正によって電子取引データ保存時は要件が厳しくなっていますが、承認手続きやタイムスタンプなど広い範囲で、要件が緩和されています。
なお、電子取引データ保存については、いくつかの要件を満たすことを条件に紙保存でも認めるとする猶予期間が、2023年以後も継続される予定(2022年12月時点)です。猶予期間中は紙で保存することで、要件義務化による影響を回避できますが、猶予期間がいつ終わるのか現時点では未定ですので、電子帳簿保存法の要件に沿った業務体制の構築は余裕をもって実施することが推奨されています。
1-3.電子帳簿保存法対応システムでできること
電子帳簿保存法対応システムとは、次のような機能を備えたシステムのことです。
| 真実性を担保する機能 | データに対するタイムスタンプの付与などに対応 |
|---|---|
| 検索機能 | 取引先・日付や金額など、さまざまな基準で検索可能 |
| スキャン機能 | スキャナ保存制度の要件を満たして、紙の資料をスキャンできる |
| OCR機能 | 画像の文字情報を認識してデータ化できる |
以上のとおり、電子帳簿保存法に対応した保存方法を実現する機能が充実しているのが特徴です。
なお、電子帳簿保存法の対象となる文書や、その保存方法について「2. 電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法」で改めて解説します。
ここでは、電子帳簿保存法に対応する機能が網羅されているシステムであるという点を理解しておきましょう。
1-4.電子帳簿保存法対応システムを導入するメリット
電子帳簿保存法対応システムを導入すると、企業には次のようなメリットがあります。
電子帳簿保存法対応システムを導入する主なメリット
- 法改正への対応漏れをなくせる
- 経理業務を効率化できる
- 不正防止になる
「法改正への対応だけなら、わざわざシステムを導入しなくても」と思いがちですが、実際には多くのメリットを備えているのが、電子帳簿保存法対応システムです。
1-4-1. 法改正への対応漏れをなくせる
電子帳簿保存法対応システムを導入する大きなメリットは、法改正への対応漏れをなくせることです。
法律の改正や制度の変更は、不定期にたびたび実施されるので、つい対応が後手に回りがちになります。
また、法律や制度の内容は複雑で細かいので、対応したつもりでもうっかり対応できていない箇所が出てしまいがちです。
しかし、オンラインの電子帳簿保存法対応システムを導入していれば、法改正の内容を把握できていなかったとしても、常に最新の改正・制度に対応した業務環境を整備できます。
1-4-2. 不正防止になる
電子帳簿保存法対応システムで帳簿や書類を保管することで、改ざんなどの不正を防止できます。
電子帳簿保存法対応システムでは、保存したデータについてタイムスタンプを付与したり、修正履歴を保存したりする機能があります。履歴が残ることで、帳簿を不正に書き換えることが難しくなるので、内部統制の強化に役立ちます。
1-4-3. 経理業務を効率化できる
電子帳簿保存法対応システムは、経理業務の効率化にも効果を発揮します。
検索機能の充実したシステムで帳簿や書類を管理すれば、欲しいデータをすぐに見つけることができます。また、紙の帳簿のように保管場所を必要としないため、余計なスペースを確保しなくて済みます。
2.電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法
最適なシステムを選ぶためには、押さえるべき電子帳簿保存法の基本的なポイントがあります。
具体的には、電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法を把握しておくことで、自社の業務に最適なシステムはどのようなものかを見極めやすくなるでしょう。
| 対象となる文書は3種類 | 国税関係帳簿・国税関係書類・電子取引の3種類が対象となる |
|---|---|
| 書類ごとの保存方法3つ | 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データの保存の3つ |
| 真実性と可視性を確保 | 真実性とは、改ざんの心配がないこと 可視性とは、閲覧や検索が簡単にできること |
参照元:国税庁:電子帳簿保存法一問一答
国税庁:電子帳簿保存法の内容が改正されました
それぞれの内容について、もう少し詳しく説明します。
2-1.対象となる文書は3種類
電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書は、国税関係帳簿・国税関係書類・電子取引の3種類です。
| 国税関係帳簿 |
|
|---|---|
| 国税関係書類 |
|
| 電子取引 |
|
参照元:国税庁:電子帳簿保存法一問一答
国税庁:電子帳簿保存法の内容が改正されました
上記のとおり、電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書は多岐にわたります。業務で取り扱う文書の範囲を把握し、その文書がシステムの対応範囲かどうかを確認して、導入するシステムを選ぶようにしましょう。
2-2.書類ごとの保存方法3つ
電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書の保存方法は、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データの保存の3つです。
| 電子帳簿等保存 |
|
|---|---|
| スキャナ保存 |
|
| 電子取引データの保存 |
|
電子帳簿保存法では、文書の種類によってさまざまな保管方法が認められていることを、覚えておきましょう。
2-3.真実性と可視性を確保しよう
電子帳簿保存法に沿って電子データを保存するときに満たすべきポイントが、真実性と可視性です。それぞれどういう意味なのか、確認しておきましょう。
| 真実性 |
|
|---|---|
| 可視性 |
|
導入するシステムを選ぶときは、自社の業務の形態に応じて、上記の真実性や可視性の要件を満たしやすい機能が充実しているかどうかを、チェックするとよいでしょう。
電子帳簿保存法対応システムの選び方については、重要なポイントなので、次章「3. 電子帳簿保存法対応システムの選び方」でさらに詳しく紹介します。
3.電子帳簿保存法対応システムの選び方
業務フローに適して、使いこなしやすい電子帳簿保存法対応システムを選ぶには、以下のようなポイントを押さえましょう。
電子帳簿保存法対応システムの選び方
- 対応書類の多いものを選ぶ
- システム化したい業務の範囲に合わせる
- 自動入力機能があるものを選ぶ
それぞれ、どのような点が重要なのか、以下で解説します。「電子帳簿保存法対応システムの導入を検討している」「最適なシステムを選びたい」という方は、ぜひ目を通しておいてください。
3-1.対応書類の多いものを選ぶ
電子帳簿保存法対応システム選びで迷ったら、対応書類が多いものを選ぶのがおすすめです。
電子帳簿保存法対応システムと一言で言っても、「満遍なく対応」「請求書を中心に対応」など、対応している書類の範囲は異なります。
多くの書類に対応しているシステムを選ぶことで、
- 1つの電子帳簿保存法対応システムで処理を完結させられるので、業務を効率化できる
- 将来的に取り扱う書類が増えた場合も、スムーズに使い続けられる
といった利点があります。
企業におけるペーパーレス化の重要性は、今後も高まっていくものと考えられます。現在は紙で扱っている書類も電子化する可能性があることを念頭に、対応書類の多いシステムを選びましょう。
3-2.システム化したい業務の範囲に合わせる
使い勝手のよい電子帳簿保存法対応システムを選ぶには、システム化したい業務の範囲に合わせることも大切なポイントと言えます。システムによって、充実している機能や対応している処理などが異なるからです。
例えば、紙でやり取りをした請求書などを電子データで保存する機会が多い場合は、スキャナ機能が充実しているものが使いやすくなります。
また、電子データを保存するだけでなく帳簿作成なども行いたい場合は、作成機能を備えたシステムや、帳簿作成システムと連携がスムーズなシステムを選ぶことがおすすめです。
以上のとおり、システムを選び始める前に、システム化する業務の範囲を明確にしておくことで、より使いやすいシステムを選べるようになります。
3-3.自動入力機能があるものを選ぶ
業務効率化に役立つ電子帳簿保存法対応システムを導入したいなら、自動入力機能があるものを選びましょう。具体的には、精度の高いOCR機能を備えるシステムがおすすめです。
OCR機能とは、画像の文字情報を認識してデータ化できる機能のことです。OCR機能があることで、特に紙の請求書や明細書などを電子データにして整理する際の手間を大幅に減らすことができます。
業務の手間を最小化したいなら、電子帳簿保存法対応システムを検討する際に、OCR機能の有無をチェックしてみましょう。
4.まとめ
電子帳簿保存法対応システムとは、電子帳簿保存法に対応する形で電子帳簿を保管できるシステムのことで「JIIMA認証」を得たシステムのことを意味します。
JIIMA認証とは
- 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証
- 電子帳簿保存法の要件を満たしていることが認められている
法律の改正や新しい制度の施行により、企業を取り巻く環境が大きく変わっており、対応が求められていることから、電子帳簿保存法対応システムが必要とされています。
電子帳簿保存法対応システムの対象となる文書・保存方法は、以下のとおりです。
| 対象となる文書は3種類 | 国税関係帳簿・国税関係書類・電子取引の3種類が対象となる |
|---|---|
| 書類ごとの保存方法3つ | 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データの保存の3つ |
| 真実性と可視性を確保 | 真実性とは、改ざんの心配がないこと 可視性とは、閲覧や検索が簡単にできること |
業務フローに適し、使いこなしやすい電子帳簿保存法対応システムを選ぶには、以下のポイントを押さえましょう。
電子帳簿保存法対応システムの選び方
- 対応書類の多いものを選ぶ
- システム化したい業務の範囲に合わせる
- 自動入力機能があるものを選ぶ
改正の機会が多い法令に漏れなく対応し、安心して業務を進めるためには、法律に対応したシステムを導入することが一番確実です。
今回ご紹介した内容を参考に、自社のニーズに沿った電子帳簿保存法対応システムを選べるようになりましょう。
どのような電子帳簿保存法対応システムが自社にあっているかが分からない方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。
SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。
しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
DXについて相談する
(※)2023年6月29日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。
(※)本記事は税理士の意見等を基に作成しておりますが、内容の信ぴょう性について保証するものでございません。法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。